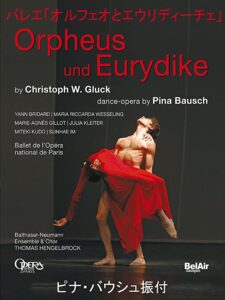ダンス、バレエ、オペラ、演劇、文楽、歌舞伎、ミュージカル……〈舞台芸術〉のあらゆるジャンルを縦横無尽に鑑賞し、独自の切り口で世界を見わたす舞踊・演劇ライターの高橋彩子さん。
「いろんなジャンルを横断的に観ると、舞台はもっとおもしろい!」ーー毎回ひとつのキーワード(テーマ)をピックアップして、それぞれの舞台芸術の特徴やおもしろさ、共通するところや異なるところに光を当てていただきます。
***
約束
人は日々、些細なものから重大なものまで、様々な約束をする。気軽に相手と連絡が取れる時代、ひょっとしたら約束の重みはかつてほどではなくなったかもしれない。昨今の政治家が何かを約束する言葉はなんとなく軽くなり、国民も約束が守られないことに慣れてしまった感がある。しかし、昔の人にとって、それは今以上に絶対的なものだった。舞台芸術では、約束を必死で守ろうとする人や、約束を守らなかった結果、大変な事態を招く人が描かれている。
約束を懸命に守る〜文楽&歌舞伎『心中天網島』『夏祭浪花鑑』〜
約束を死守しようとする人々が多く登場するのが、文楽や歌舞伎。一つには、儒教道徳が日本に入り、独自の「義理人情」の考え方となって浸透していたことが考えられる。と言っても、実際には誰もが模範的に生きていたはずはないが、「義理人情に厚い人間であるべき」「そうした姿は美しい」といった考え方があったから、作品にも取り入れられたのだろう。
例えば、文楽や歌舞伎の『心中天網島(しんじゅう てんのあみじま)』では、一人の男の妻と愛人が、互いに相手の女性を想い、約束を果たそうとする。
- 〈あらすじ〉
- 紙屋の治兵衛は妻子がありながら紀伊国屋の遊女・小春と深い仲になり、二度と会えなくなる時は共に死のうと心中の誓いを交わしている。治兵衛の兄である孫右衛門は心中を諦めさせようと侍客に扮し、小春に会いに来る。「心中の約束をしてはいるが本当は死にたくないから、阻止してほしい」と孫右衛門に頼む小春。こっそり店を訪れて聞いていた治兵衛は怒り狂い、心中の誓いを印した“起請”を小春から取り上げるが、孫右衛門はその際、小春が治兵衛の妻・おさんからの手紙を紙入れの中に大事に持っているのを見てしまう。
数日後、治兵衛の紙屋の店先。治兵衛が、小春が太兵衛に請け出されるくらいなら死ぬと言っていたにもかかわらず自分と別れた途端に太兵衛に請け出されようとしていることへの怒りと悔しさを爆発させる。しかし、妻のおさんは、小春と心中しそうな治兵衛の命を救うため、自分が小春に心中せず別れてほしいと頼んだのであり、これを承諾した小春からの手紙を大事に取ってあると語る。頼みを聞いてくれた小春は死ぬつもりなのだと察したおさんは、商売用の金や自分と子供の着物を質に入れ、小春を身請けしてくれと治兵衛に頼む。しかし、その支度をしているところへ、おさんの父・五左衛門が現れ、事態に呆れておさんを連れ帰り、離縁させてしまう。
結局、治兵衛と小春は心中するのだった。
恋しい治兵衛との心中の約束を、相手の妻から頼まれたがために、治兵衛に明かすこともなく一度は諦めた小春。そんな恩ある小春の命を救うため、夫に身請けを促すおさん。互いを思いやり、約束を果たそうとする女性二人の姿は、現代ではなかなか考えられないほど義理堅い。のっぴきならぬ状況の中で、心中という当初の約束もまた、遵守されてしまうのだが……。
『夏祭浪花鑑(なつまつり なにわかがみ)』にも、同様に義理堅い人々が多数登場する。
- 〈あらすじ〉
- 玉島家の子息・磯之丞は傾城・琴浦と恋仲となり、琴浦に横恋慕する佐賀右衛門に陥れられて窮地に陥る。玉島家に恩義のあるお梶は磯之丞を救うために奔走するが、お梶の夫・団七は佐賀右衛門の手の者と喧嘩になり牢に入り、磯之丞は勘当される。団七が牢を出る日、団七と親しい老侠客の釣船三婦は、家を追い出されてお梶を頼ろうと大阪に向かう途中でトラブルに遭っている磯之丞をみつけ、ひとまず馴染みの茶屋へ向かわせる。晴れて出獄した団七は、その磯之丞を追いかける途中で佐賀右衛門に追いつかれてしまった琴浦を助け、磯之丞の居場所を知らせる。その団七に、佐賀右衛門の手下から頼まれて喧嘩をふっかけたのが徳兵衛だったが、仲裁に入ったお梶は徳兵衛の恩人であり、徳兵衛自身も玉島家の家来筋にあたる身だとわかり、団七と徳兵衛は、共に磯之丞の世話をしようと約束し、義兄弟の誓いを結ぶ。
さらに様々な出来事を経て、磯之丞は琴浦と共に三婦の家に匿われることに。そこへ徳兵衛の女房・お辰が、徳兵衛と共に里へ帰るということで挨拶に来る。三婦の女房・おつぎは磯之丞を預かってくれるよう頼み、お辰は快く引き受けるが、それを聞いた三婦は、色気のあるお辰のもとに若い男を預けることはできないと反対する。すると、お辰は、自分にとっても夫にとっても主筋に当たる玉島家の子息を預からないようでは、自分と夫の面目が立たない、と、そばにあった焼ごてを顔に当てて醜くしてみせ、磯之丞を預かる。
一方、残された琴浦は、団七の舅である義平次が、団七からの迎えだと言って駕籠に乗せて連れて行く。ところが、それは佐賀右衛門に琴浦を渡そうという義平次の悪巧みだった。これを知った団七は、長町裏で舅に追いつき、金を渡すからとなだめて琴浦を戻す。しかし実際には団七が金を持っていないことがわかり、義平次は団七を散々に罵倒。団七はひょんなことから義平次を斬ってしまう。団七は井戸の水で身体を洗い、その場を立ち去る。
三婦も団七も徳兵衛も、任侠を重んじる男たちであり、その妻たちもまた、夫と同じく義侠心をもって生きている。そこでは、恩義や誓い=約束が何よりも優先される。それゆえにこそ舅を殺してしまった団七が、夏祭りの祭囃子が高まる中、全身の鮮やかな刺青をあらわにするクライマックスは、凄絶美を極める。
この『夏祭浪花鑑』を、大阪の国立文楽劇場では夏休み文楽特別公演として上演。夏の大阪が舞台の物語を、夏の大阪で観るのは格別だ。

『夏祭浪花鑑』お辰(左)と三婦 提供:国立文楽劇場

『夏祭浪花鑑』団七(左)と義平次 提供:国立文楽劇場
約束を破ったがゆえの悲劇〜オペラ&ダンス『オルフェウスとエウリディーチェ』、オペラ『夕鶴』〜
約束は守らなければならない。だからこそ、約束を破るという行為も存在する。特に何かを禁止されると、一旦は同意はしても破りたくなってしまうのが人情というものだ。面白いことに、「見てはいけない」と禁じられたものを見てしまったがために悲劇が起きるという物語は、世界各地の神話伝承によく似た形で描かれ、「見るなのタブー」と呼ばれている。
例えば、ギリシャ神話のオルフェウスとその妻エウリディケの物語は、日本神話のイザナギとイザナミにそっくりだ。
- 〈『イザナギとイザナミ』あらすじ〉
- イザナギは、妻のイザナミが火の神を生んだことで命を落としたため、黄泉の国に向かい、黄泉の国の御殿で妻を発見する。しかしイザナミは黄泉の国の食べ物を食べてしまったために戻ることができない。
そこでイザナミは黄泉の国の紙に相談することにするが、相談の最中は決して覗き見をしないことをイザナギに約束させる。
しかし、妻が戻らないことに不安を覚えたイザナギが御殿の中を覗くと、そこには腐敗して蛆にたかられた醜い姿のイザナミが。驚いたイザナギは逃げ、追いかけてきたイザナミと黄泉国と地上との境である黄泉比良坂で決別する。
一方の、ギリシャ神話は、こうなる。
- 〈『オルフェウスとエウリディケ』あらすじ〉
- 愛する妻エウリディケが毒蛇に噛まれ、命を落としたため、詩人オルフェウスは黄泉の国へと向かい、竪琴を奏でて黄泉の国の人々を涙させる。
黄泉の国の王ハデスも妃ペルセポネに説得され、エウリディケを返してやることにする。その際、ハデスは、黄泉の国を出るまで、決して後ろにいるエウリディケを振り返らないことを約束させる。
しかし、あと一歩で黄泉の国を出るというところで、オルフェウスは不安を抑えきれず妻のほうを振り返ってしまう。するとエウリディケは黄泉の国へと引き戻されてしまったのだった。
愛を誓い合った夫婦の片方が不意にいなくなってしまう哀しみは、いつの世も変わることがない。愛妻を迎えにわざわざ黄泉の国まで出向き、妻を取り戻しそうになりながらも、見てはならないとされた妻を見て、永遠に失ってしまうーー。こんなにドラマティックな瞬間があるだろうか。
**
余談になるが、能『清経』では、源氏に攻められ行く末を悲観して入水した平清経の遺髪を、妻が手渡され、再会を約束したのに討ち死にでも病死でもなく自ら死んだ夫を恨み、見るたびに辛いからと遺髪を返納する。すると妻の枕元に夫の亡霊が現れ、遺髪を返した妻への恨み言を言い、互いに嘆く。死者を呼び戻しには行かないけれど、悲しみに暮れる夫婦の姿に心動かされる作品だ。
**
閑話休題。「オルフェウスの冥府下り」は数多くの芸術作品になっている。舞台芸術としてはオペラとの縁が深く、現存する世界最古のオペラと言われるヤコポ・ペーリ作曲『エウリディーチェ』、モンテヴェルディ作曲『オルフェオ』、シャルパンティエ作曲『オルフェウスの冥府下り』……と、1600年代からこの題材で幾つもの作品が生まれている。
中でも高い人気を誇る作品の一つが、1762年にグルックが作曲したバロック・オペラ『オルフェウスとエウリディーチェ』。ウィーンでの初演版にはないのだが、その後のパリ初演版には「精霊の踊り」と呼ばれる名曲が入っている。オルフェウスがエウリディーチェを迎えに行った黄泉の国で流れる曲で、優美なフルートの音色が特長。ピナ・バウシュは1975年、このグルックの音楽に基づき、ダンス・オペラ『オルフェオとエウリディーチェ』を振付けている。「精霊の踊り」では女性ダンサー達が幻想的に舞い、オルフェウスとエウリディーチェが地上へ向かう場面では、顔を見合わせることのないダンスの果てにオルフェウスが振り向き、二人が抱き合ってエウリディーチェが崩れ落ちるまでを、ダンサーとオペラ歌手の両方が舞台上で演じる。
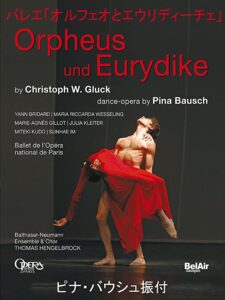
ピナ・バウシュ振付 ダンス・オペラ『オルフェオとエウリディーチェ』
来年のことになるが、このグルックのオペラは、新国立劇場で上演され、舞踊家の勅使川原三郎が演出・振付を手がける。舞踊とも縁の深いこの作品が、どのような姿で現れるのか注目したい。

勅使川原三郎 ©Norifumi Inagaki
さて、この「見るなのタブー」にはもう一つ、有名な話がある。助けた鶴が人間の女性となって現れ、恩人のために自らの羽を抜いて美しい布を織るが、禁じたにも関わらず織っているところを恩人に覗かれたため、鶴となって帰ってしまうという、民話『鶴の恩返し』だ。
この物語を劇作家の木下順二が戯曲化した『夕鶴』は、教科書などにも掲載されていたので、ご存知の方は多いだろう。木下は、恩人であり夫となる与ひょうをひたすら愛する鶴の化身・つうと、次第に金に目がくらんでいく与ひょうの姿に、経済至上主義への批判を込めたとされる。木下のミューズであった山本安英が幾度も演じ、その後は坂東玉三郎が演じて話題を呼んだ。漫画『ガラスの仮面』で北島マヤと姫川亜弓が主演の座を争う名作『紅天女』のモデルも『夕鶴』だと言われている。
そして、木下の戯曲の言葉を変えることなくオペラ化したのが、作曲家の團伊玖磨の同名作。抒情的・幻想的な美しい音楽が魅力で、上演頻度の高い人気オペラだ。今から楽しみなのが、今年10月に劇作家・岡田利規が演出を手がけて上演されること。岡田は、
「『夕鶴』では、現代を生きるわたしたちが現代を生きるために自明のものとして受け入れてしまっている問題が扱われている」「その問題は、そんなふうに受け入れてしまって良いとは思えない問題」とし、「『夕鶴』はわたしの物語であり、あなたの物語です。あなたの居心地を悪くする物語です。なぜ『夕鶴』の物語があなたの居心地を悪くするのか? それは、与ひょうはあなただからです」
と断じる。ダンス集団TABATHAの岡本優と工藤響子も出演。現代社会への警鐘にもなり得るこの作品を、岡田は今、どのように描くのだろうか?

岡田利規 © 山貴久子
悪魔との約束の果てに〜ゲーテ『ファウスト』、オペラ『ファウストの劫罰』『ファウスト』〜
大小様々な約束の中でも、特に怖ろしいのは、悪魔との約束だろう。ゲーテがファウスト伝説に基づいて書いた大作戯曲『ファウスト』は、悪魔と契約を交わしてしまった男の話だ。
- 〈あらすじ〉
- 悪魔メフィストフェレスが神に人間の愚かしさを話したところ、「常に向上の努力を成す者」の代表としてファウスト博士の名が挙がる。メフィストフェレスはこれを聞いて、ファウストの魂を悪の道へと引き摺り込めるかどうかの賭けを神に持ちかけ、ファウストを誘惑することにする。
さて、当のファウストは、研究に没頭して老いた人生を振り返り、結局は何もわからなかったと悲観して自殺しようとする。そこへメフィストフェレスが現れ、「あらゆる欲望をかなえる代わりに、満足したら『時よ止まれ、お前は美しい!』と言って、魂を悪魔に与える」という契約を結ぶ。
魔法で若者に戻ったファウストは、町娘グレートヒェンと恋に落ちるが、グレートヒェンはファウストと逢うため母に飲ませた睡眠薬の分量を間違え、母を死なせてしまう。グレートヒェンの兄はファウストに決闘を申し込むが、メフィストフェレスに殺される。精神を病んだグレートヒェンは、ファウストとの間にできた子供を殺して牢に入り、やがて死ぬ。
絶望するファウストだったが、メフィストフェレスに連れられ、ギリシャ神話の世界へ赴く。そこでファウストは絶世の美女ヘレネーと結婚し、子供を授かるが、その子は若くして死んでしまう。しかしファウストは、メフィストフェレスの力を借りてローマ皇帝を助けて戦に勝ち、領地を譲り受ける。その土地の干拓事業に着手したファウストだったが、立ち退きを求める老夫婦を悪魔のせいで死に至らしめ、「憂い」の霊に息を吹きかけられて失明してしまう。目が見えなくなったファウストは、メフィストフェレスらが彼の墓を掘る音を、工事のつるはしの音だと思い、人々の役に立っているとの幸福感から、「時よ止まれ、おまえは美しい!」の言葉を口にする。
こうしてファウストは死ぬが、その魂は天上の霊となったグレートヒェンのおかげで救済され、メフィストフェレスの手から逃れて神のいる天へと上っていく。
賭けをし、契約したにもかかわらず、その約束が神によって反故にされるのだから、悪魔にしてみれば理不尽極まりない話だ。この理由については諸説あるが、壮大で深淵なテーマを持つ世界なので、ぜひ戯曲をじっくりと読んで考えてみよう。

この物語は、ベルリオーズ作曲のオペラ『ファウストの劫罰』やグノー作曲のオペラ『ファウスト』になっている。どちらもメトロポリタン歌劇場(MET)のサイトから、7日間の無料トライアル、その後は$4.99で視聴可能。METの『ファウストの劫罰』はロベール・ルパージュの演出がアイデア豊かで非常に美しい。『ファウスト』は舞台を20世紀初頭に移したデス・マッカナフ演出が刺激的だ。
約束事
最後に、舞台における“約束事”についても、少しだけ触れておきたい。この連載では、多様な舞台ジャンルに触れてほしいという思いのもとで越境的に作品を紹介しているが、見慣れない人にとって、そのジャンルならではの約束事は奇異に見えるもの。
例えば、筆者の知人は、「バレエは言葉を発しないので見ていて息が詰まる」と言った。「能は動かない」もよく聞く意見。「ミュージカルは突然歌い出すところに違和感がある」というのは、タモリをはじめ多くの人が口にしている。しかし、本当にそうなのだろうか?
確かに多くのバレエは喋らないが、バレエファンなら、ダンサーがどれだけ饒舌に語っているか、知っているだろう。いわゆるマイムはもちろん、それ以外の動き、表情、身体のライン……など、全てが感情を表わしている。ここで言う感情とは、個々のキャラクターの喜怒哀楽にとどまらず、微細な情緒・ムードを含む。狭義の言葉がないからこそ、そうした言語の豊かさが伝わってくるのだ。逆に言えば、それを饒舌にこなせる技量がなければ、どれだけ動いても何も見えては来ない。
能もこれに近いものがある。三間四方(約6メートル四方)と限られた能舞台で行われる能は、確かに抑制された動きの世界だ。しかし、その抑制の中にも感情の起伏があり、時にそれは、驚くほど激しい。シテがじっと座っているような時でも、シテやワキや地謡(じうたい)の謡(=台詞や歌)が濃厚な空気を作って、能舞台という宇宙に充満しており、優れたシテならばただの静止ではなく、高速回転する独楽が動かないように見えるのと同じように、そこに生きて動いているのだ。わかりやすく派手に動くとは限らないからこそ、見ていて感情が滲み出し、観る者の心にも染み渡っていく。
ミュージカルはどうか。歌の入り方は作品によって様々だが、その前までの物語や演技があってこそ、自然に繋がっていく。もちろん、敢えて唐突に歌に突入することもあるが、それが違和感のまま残るとしたら、歌に入り方の問題ではなく入ってからの問題、つまり、歌や踊りを異質なままにして劇の中に消化できない演じ手のこなし方に原因があるのではないだろうか。
つまり、優れた演者にかかれば、各ジャンルの約束事は、ただの枷ではなく、より大きな効果へと昇華していくもの。そうした演者との出会いによって、私達の素晴らしい鑑賞体験は「約束」されるのだ!
★次回は2021年8月1日(日)更新予定です