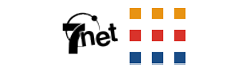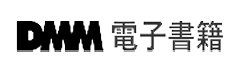“Contemporary Dance Lecture for Ballet Fans”
ダンスにおける「美しさ」問題〜それは疑いつつ信じ抜くもの〜
舞台芸術の中でも、バレエといえば美の極致。
バレエダンサーは人間という限りある身でありながら、終わりなき究極の美の体現者たることを求められる。
あらゆる面で完璧であること。そこには往々にして身体的な美しさとともに容姿も含まれる。
しかし現代では容姿への評価が、人間の能力や価値まで左右してしまう「ルッキズム」への批判も高まってきている。
「見る芸術」「身体表現」であるダンスにおける「美しさ」のあり方についてみてみよう。
「若さ」と「美しさ」の楽園
●役割としての「美しさ」
クラシック・バレエの登場人物は、男女ともにたいてい若くて美しい。
もちろん身体表現の美しさを競うわけだが、王族・貴族など「国民皆が憧れ、誇りに思う人々」を前提とした役柄を演じることも多い(たまに魅力的な踊り子だったり純朴な村娘だったりもするが)。
バレエにおける美とは、まさにプラトンのイデア的な、「この世を越えたところにある完全なる美」に少しでも近づこうとする終わりのない営み、あるいは業である。
目鼻の配置のバランスが良いといったような世俗的な基準など遠く超えたところにあるものだ。
しかし昔はわりと「女性の評価には容姿の美しさが重要」という考えが、無自覚に当然の前提とされていた。というかいまだに「○○美人コンテスト」と題されたイベントが日本のあちこちで行われているのが実情である。
●作られた「美談」
つい最近、しかもよりにもよって東京オリンピック・パラリンピック2020(2021年実施)の開会式イベントの責任者が、太めの女性芸人を豚に例えた演出案を出したことが発端となって辞任する騒ぎになった。
その際に、他の芸人の側から「でもその芸人は太った身体のネタで売れてきたのに、今後はやりにくくなるのでは」という声もあった。
たしかにお笑いの世界では「チビ・デブ・ハゲ・ブサイク」など、外見を揶揄する言葉が飛び交ってきた。
しかもそれは長いこと、こんな「美談」として語られてきたのである。
「小さい頃からずっと容姿でいじめられてきたが、いまでは容姿を武器として使って笑いをとれるようになった」
逆境を跳ね返した、強くなった、素晴らしい、というわけだ。
●その異常さに気づけない
この「美談」が異常なのは、「いじめる側」のことを全く責めていないことだ。
「いじめられる側」だけが耐えて、努力し、加害者も含めた人々を楽しませることができたら居場所を与えていただける。そんなことが美談だろうか。
「武器」に変えられたごく一部以外の大多数の人々は、容姿を馬鹿にされても耐え続けていけ、ということではないか。
「残念だけど、いじめや差別は人間の本性なので、なくならない。しょうがないよ」という考えが基本にあるのだろう。
では攻撃欲や破壊衝動、他人の物を欲しくなるのも人間の本性なので、お前は自分より力の強い者からいきなり殴られたり身ぐるみを剥がれても「人間だもの」と笑顔で差し出すのか。
そんなことのないように人権という概念が生まれ、人権を守るために法律がある。
全ての人は平等に幸せに生きる権利があるからだ。
しかしなぜかいじめに関しては「いじめる側の理屈」が優先される。その要因のひとつに「アイツを見てるとイライラする」といったルッキズムが加担していることは否定できないだろう。
もっとも最近は笑いの世界でも、若い女性芸人が「デブやブスといった見た目のいじりはしてほしくない」とはっきりとメディアで発言するようになってきた。「そんなことを言っていたら、お笑いなんてできなくなる」という声もあったが、大きな漫才大会の決勝に残ったネタが、いずれも「他人を傷つけないネタ」だったりしている。
できなかったわけではない。
しなかっただけなのだ。
バレエ作品の「美しくない人々」
●「美しくなければ死ぬ」の法則!?
……いやべつに、この連載はお笑いを熱く語るものではないのだが、全く無関係というわけでもない。
美の結晶のようなバレエ作品では敵役すらスタイリッシュなため、主要登場人物が「美しくない姿」で登場することはあまり多くない。
歪んだ顔の人形の『ペトルーシュカ』や、『ノートルダム・ド・パリ』のせむし男カジモド、といったところだろうか。
ミュージカルでも『美女と野獣』(デヴィッド・ビントレーがバレエ化している)や『オペラ座の怪人』など、姿が醜い者は人目を避けて暮らさねばならない。
もっとも『美女と野獣』のビーストは、グリム童話の『カエルの王子様』同様、「魔法で姿を変えられていたが、王子様に戻れた者」なので、最後はお姫様と結婚できる。
つまり、バレエにおいては「醜い者は死ぬ。ただし美しい姿に戻った者は生きる」の法則があるのだ(私見です)。
たとえば『ノートルダム・ド・パリ』(原作はユーゴーの小説)のカジモドはエスメラルダの無念を晴らすが、最後は骨となって発見される。『オペラ座の怪人』のファントムも、生きていることをほのめかしつつ死んだことになる。
舞台上のファントムは仮面が小さいこともあり火傷と思っている人も多いが、先天的な奇形である。とはいえカジモド同様、病気や先天的な疾患による症状を「醜い」と書くのは間違っているが、作品の中ではそういう位置づけで描かれている、ということでご容赦願いたい。
―― この続きは電子書籍でお楽しみいただけます ――
※この記事ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。