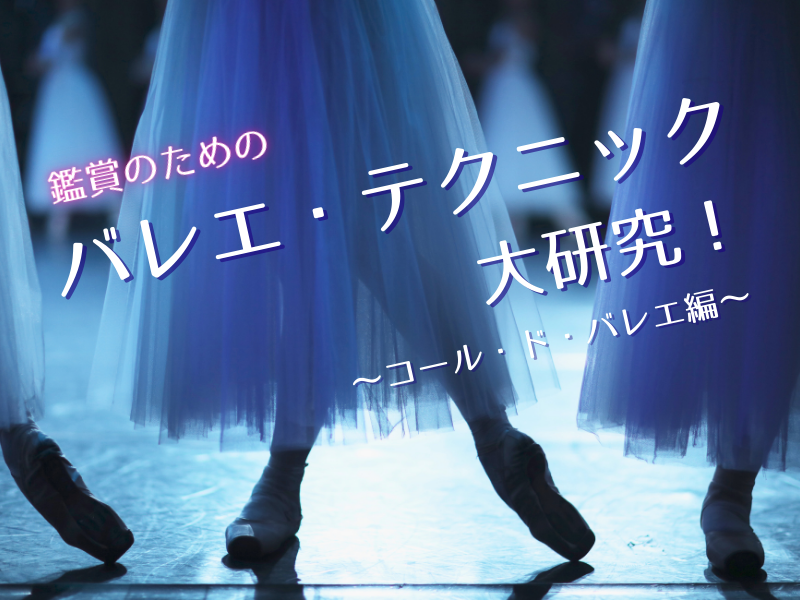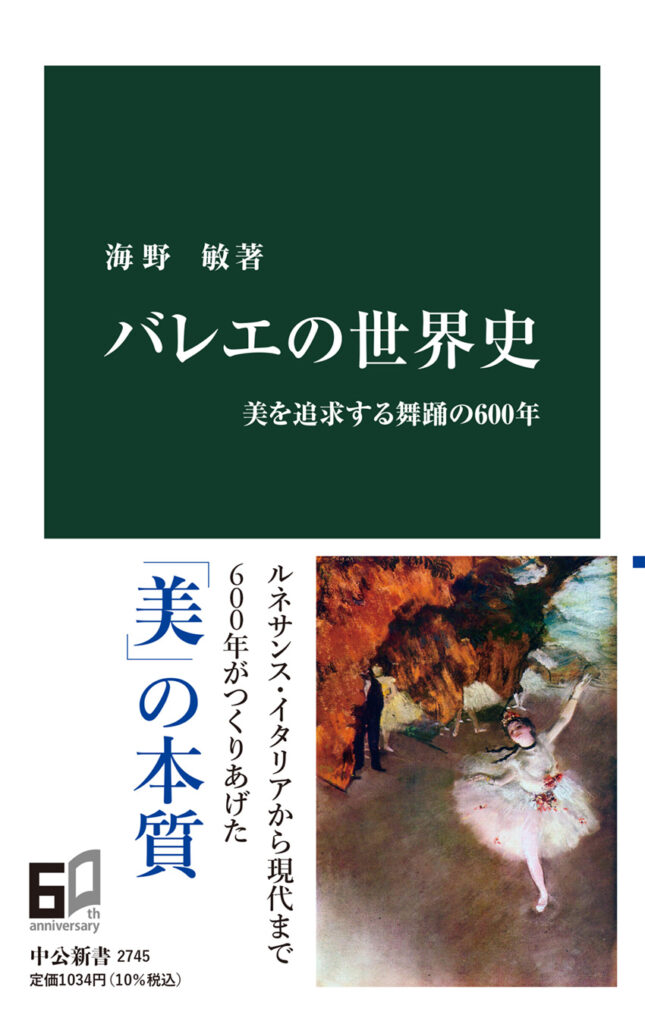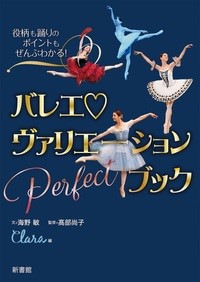文/海野 敏(舞踊評論家)
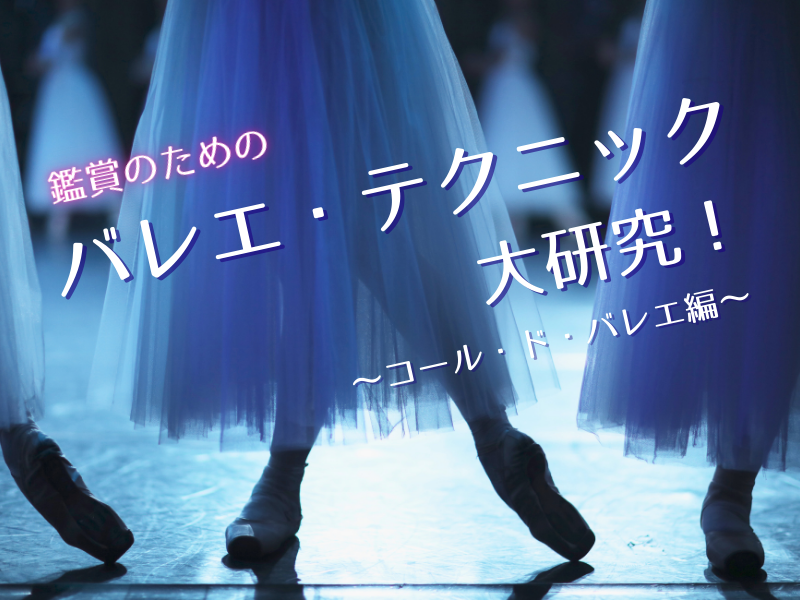
第72回 バランシン作品のシンメトリー
■ジョージ・バランシン
前回(第71回)は美しいシンメトリーが現れる古典作品を紹介しましたが、じつはシンメトリーと聞いて筆者が真っ先に思いつくのは、ジョージ・バランシン(1904-1983)の振付作品です。
バランシンはディアギレフのバレエ・リュスで振付家として活躍した後に渡米し、のちのニューヨーク・シティ・バレエとなるバレエ団を創設して、アメリカに独自のバレエ文化を根付かせた人物です。渡米後の作品の多くは筋書きがない「プロットレス・バレエ」であり、「アブストラクト・バレエ」の完成者と言われています(注1)。
本連載では、これまでバランシンの作品として、『チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ』(第1、47、51回)、『ウエスタン・シンフォニー』(第5、64回)、『アレグロ・ブリランテ』(第69回)を取り上げています。今回はまだ取り上げていない作品で、彼がシンメトリーの美を徹底して追究した2つの傑作を紹介します。
■『シンフォニー・イン・C』のシンメトリー
『シンフォニー・イン・C』は、バランシンがパリ・オペラ座バレエのために振付けた約40分の1幕物です。初演は『水晶宮』という題名でしたが、その後ニューヨーク・シティ・バレエの上演時に改訂され、『シンフォニー・イン・C』と改題しました。日本では新国立劇場バレエ団がレパートリーとしているので、ご覧になったことのあるファンは多いでしょう。
音楽は、ビゼーが17歳の時に作曲した「交響曲 ハ長調」で、各楽章の上演時間と出演ダンサーの人数は次の通りです(注2)。
第1楽章 … 約8分 … 11~14人(女9~11人、男3人)
第2楽章 … 約10分 … 11人(女9人、男3人)
第3楽章 … 約5分 … 11人(女9人、男3人)
第4楽章 … 約10分 … 48~52人(女36~40人、男12人)
各楽章には、それぞれ「主役男女1組+ソリスト男女2組+群舞女性6~8人」が配置されています。第4楽章では、最初に同楽章の「主役+ソリスト+群舞」が踊った後、第1~3楽章のダンサーたちが順番に加わり、約50人でフィナーレとなります。このような同型反復の構造じたい、シンメトリーの一種です。
バランシンの美しいシンメトリーへのこだわりはすべての楽章に共通していますが、ここでは第1楽章と第4楽章を紹介します。
第1楽章は「アレグロ・ヴィーヴォ」(活発に速く)。幕が上がると女性ダンサー10人(ソリスト2人+群舞8人)が「板付き」(舞台にあらかじめ出ている状態)で、左右対称に並んでポーズをしています。冒頭から約40秒は、左右5人ずつが完璧に対称な動きをします。次の約40秒は左右が少しタイミングをずらして対称に動き、さらに左右5人ずつの位置が入れ替わったところで主役の女性が登場するという流れです。その後、男性3人が登場してからは、主役2人を中心にしてソリスト男女4人と女性群舞が左右に分かれ、対称に動く場面が続きます。
- ★動画でチェック!★
- ニューヨーク・シティ・バレエ『シンフォニー・イン・C』より第1楽章の映像です。こちらの映像では、男性3人が登場したあとのシーンから観ることができます。左右対称の美しいシンメトリーをご覧ください。
第4楽章は「アレグロ・ヴィヴァーチェ」(快活に速く)で、第1楽章よりさらに速いテンポ。後半、4つの楽章のダンサーが揃ってからは、フィニッシュまで豪華なシンメトリー構図の連続です。まず女性群舞約30人が舞台をコ(冂)の字(第68回)で囲い、左右対称またはユニゾンで踊ります。そして群舞のコの字に囲まれて、主役女性4人、主役男性4人、女性ソリスト8人が順番に踊り、全員が揃います。さらに男性全員が跳躍を繰り返す短いユニゾン、主役4組の踊り、女性のみ全員の踊りが続き、フィニッシュへと向かいます。フィニッシュの瞬間を詳しく説明すると、主役4組が中央に並んでポーズし、その左右に4人ずつ女性ソリストがアン・オー(両腕を頭上に高く上げて楕円を作るポジション)の姿勢で男性ソリストにショルダー・リフト(第36回)され、その後ろに数十人の女性群舞全員がアン・オーでポワントで立つという圧巻の絵柄です。
- ★動画でチェック!★
- ボストン・バレエ『シンフォニー・イン・C』より第4楽章の映像です。女性群舞に囲まれて主役女性4人が登場するところから観ることができます。50人ほどのダンサーによる、華やかなシンメトリーをお楽しみください。
■『ジュエルズ』のシンメトリー
『ジュエルズ』は、バランシンがニューヨーク・シティ・バレエのために振付けた約90分の1幕物です。3部構成で、第1部「エメラルド」、第2部「ルビー」、第3部「ダイヤモンド」と標題が付けられており(注3)、それぞれの宝石の輝きを、異なる時代の作曲家の音楽と異なるバレエ様式で表現しています。
音楽は、「エメラルド」がフォーレの「ペレアスとメリザンド」と「シャイロック」、「ルビー」がストラヴィンスキーの「ピアノとオーケストラのための奇想曲」、「ダイヤモンド」がチャイコフスキーの「交響曲第3番」です。それぞれ振付は、19世紀前半のロマンティック・バレエ風、20世紀初頭のバレエ・リュス風、19世紀後半のクラシック・バレエ風に作られています(注4)。
鑑賞の手引きとして、長くなりますが全14曲の上演時間と出演ダンサーの人数をリストしておきましょう(注5)。
第1部「エメラルド」
第1曲 … 約5分 … 12人(女11人、男1人)
第2曲 … 約2分 … 1人(女1人)
第3曲 … 約4分 … 1人(女1人)
第4曲 … 約3分 … 3人(女2人、男1人)
第5曲 … 約3分 … 2人(女1人、男1人)
第6曲 … 約4分 … 17人(女14人、男3人)
第7曲 … 約4分 … 7人(女4人、男3人)
第2部「ルビー」
第1曲 … 約7分 … 14人(女9人、男5人)
第2曲 … 約6分 … 2人(女1人、男1人)
第3曲 … 約6分 … 14人(女9人、男5人)
第3部「ダイヤモンド」
第1曲 … 約8分 … 14人(女14人)
第2曲 … 約10分 … 2人(女1人、男1人)
第3曲 … 約6分 … 6人(女5人、男1人)
第4曲 … 約10分 … 34人(女17人、男17人)
この作品も、全編通してどこを切り取ってもバランシンの「シンメトリー愛」に溢れています。例えば、3部それぞれの第1曲は曲調が異なるにもかかわらず、その冒頭は、幕が上がると板付きの左右対称フォーメーションで始まる点で共通しています。しかも冒頭の数分は、いずれも全員が左右に分かれて完璧に対称な動きをする振付になっています。
第2部「ルビー」の振付は、手首や肘を直角に曲げたり、腰を突き出して全身を歪めたり、四肢をねじるようなポーズをしたり、かなりクラシック・バレエとは異質な動きを加わえています。しかし、それでも全体にシンメトリーの美は貫かれているのが鑑賞のポイントです。
- ★動画でチェック!★
- 英国ロイヤル・バレエの『ジュエルズ』より「ルビー」の第2曲のパ・ド・ドゥです。特徴的な動きが振付の随所に散りばめられています。
一方、第3部「ダイヤモンド」の振付は、古典的なバレエの様式美で作られています。第1曲は「アレグロ・ブリランテ」(華やかに速く)。12人の女性群舞が、3人ずつで1辺を作る横長の菱形(◇)フォーメーションで踊る場面が繰り返されます。菱形はダイヤモンドを表わしていると思われます。この菱形フォーメーションになると、3人ずつが同じステップで動くのですが、全体で左右対称の動きをする振付になっています。
- ★動画でチェック!★
- オーストラリア・バレエの『ジュエルズ』よりフォーメーションにフォーカスした映像です。「エメラルド」「ルビー」「ダイヤモンド」の美しいシンメトリーを観ることができます。40秒から始まる「ダイヤモンド」の第1曲の菱形のフォーメーションに注目です。
第3部第4曲は「アレグロ・コン・フオーコ」(情熱的に速く)。まず16組の男女が下手奥から2列になって、ポロネーズ風に登場します(第62回「2列で進む(2)」)。終盤、音楽のテンポが少し緩やかになると、主役男女を中心にして34人が舞台一面に広がり、男女が手をつないで全員ユニゾンで踊り始めます。17人の女性が男性にサポートされて一斉にアラベスク・パンシェ(第27回)をした後には、主役男女以外の32人が左右に16人ずつ分かれ、片膝を床に突いてシンメトリーな構図になります。そこから全員でのユニゾンまたは左右対称の振付が約1分間続き、最後は主役男女を囲む32人で、「女性の前に男性が跪くポーズ」が左右に8組ずつ並ぶ逆V字(∧)を作ってフィニッシュします。「ダイヤモンド」という標題にふさわしい豪華絢爛なコール・ド・バレエを是非味わって下さい。
- ★動画でチェック!★
- 英国ロイヤル・バレエの『ジュエルズ』より「ダイヤモンド」の第4曲です。ぜひ、華やかなコール・ド・バレエをお楽しみください。
(注1)バランシン自身は、自分の作品が「アブストラクト」(抽象的)と呼ばれることを嫌っていました。しかし彼のプロットレス・バレエは、物語を欠いていることに加えて、喜怒哀楽などの感情や心理を表現しようとせずに「音楽+ダンサーの美しい姿勢と動作」のみで構築されている点で、抽象主義的なバレエであることは間違いありません。
(注2)女性群舞の人数は、バレエ団によって多少の差があります。
(注3)各部の原題は複数形なので、「エメラルズ」(Emeralds)、「ルビーズ」(Rubies)、「ダイヤモンズ」(Diamonds)と表記されることも多いです。なお、バランシンはこの作品をニューヨークの宝飾店ヴァンクリフ&アーペルの宝石に触発されて作りました。
(注4)あくまで「~風」であり、作品全体にはバランシン振付の様式が一貫しています。
(注5)第1部は、第4曲と第5曲の間にパ・ド・ドゥを1曲挿入した改訂版もあります。また第7曲のパ・ド・セット(7人の踊り)を上演しない場合もあります。
(発行日:2025年7月25日)
次回は…
第73回は、舞台上のダンサーの人数が増えてゆく演出の効果について考えます。発行予定日は2025年8月25日です。
- 【鑑賞のためのバレエ・テクニック大研究!-総目次】
- http://bibliognost.net/umino/ballet_tech_contents.html
\NEWS!/
本連載の著者・海野敏さんによる書籍が発売されました! ルネサンス期イタリアから21世紀まで、バレエという舞台芸術の600年を通覧する内容です。
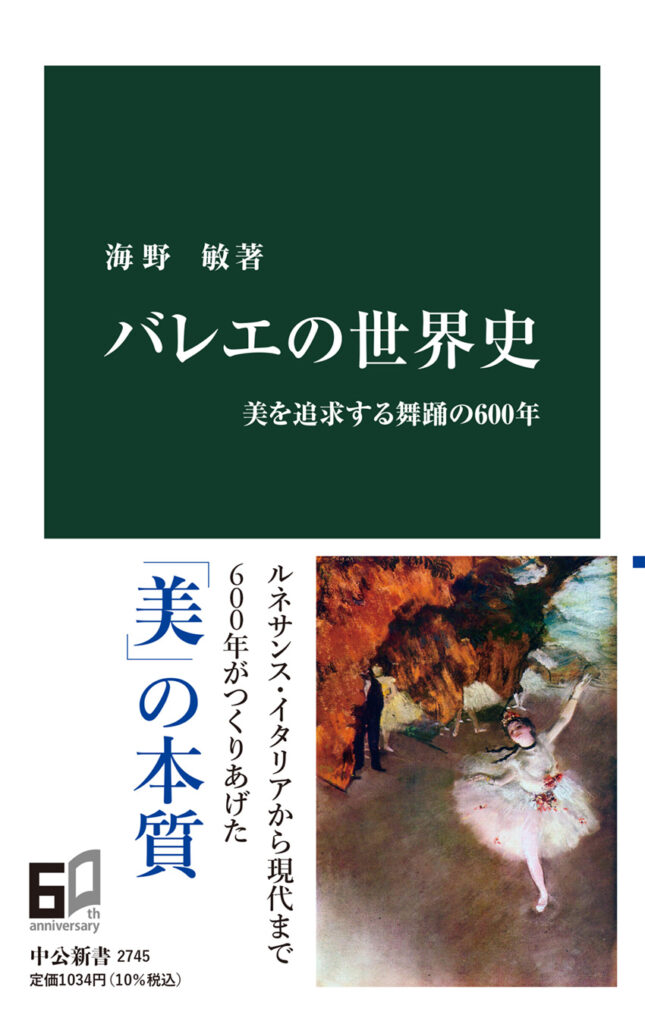
『バレエの世界史:美を追求する舞踊の600年』
海野敏=著
中央公論新社 2023年3月(中公新書2745) 940円(税別)
★詳細はこちら
*
【こちらも好評発売中!】
オーロラ、キトリ、サタネラ、グラン・パ・クラシック、人形の精……等々、コンクールや発表会で人気の 30 のヴァリエーションを収録。それぞれの振付のポイントを解説しています。バレエを習う人にも、鑑賞する人にも役立つ内容です。ぜひチェックを!
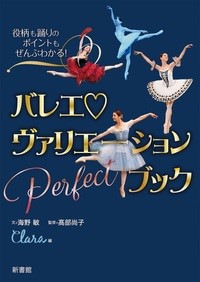
『役柄も踊りのポイントもぜんぶわかる! バレエ♡ヴァリエーションPerfectブック』
海野敏=文 髙部尚子=監修
新書館 2022年3月
★詳細はこちら