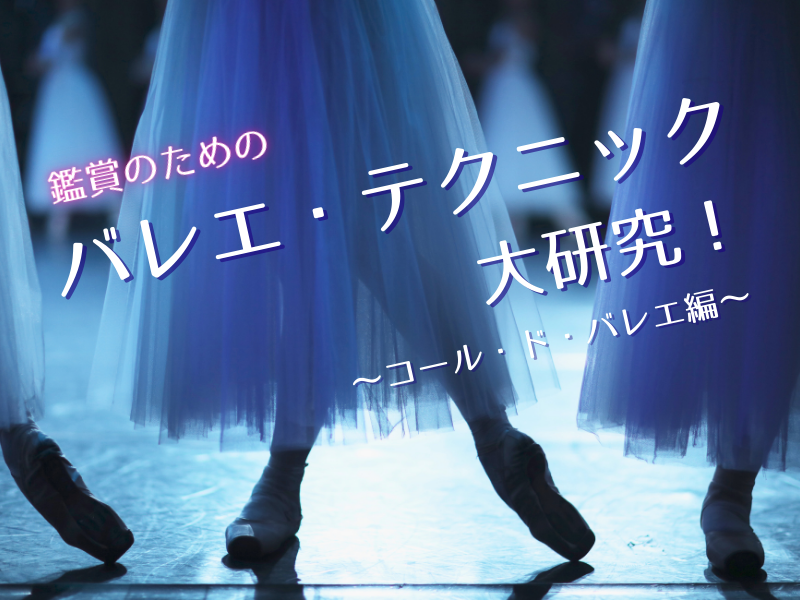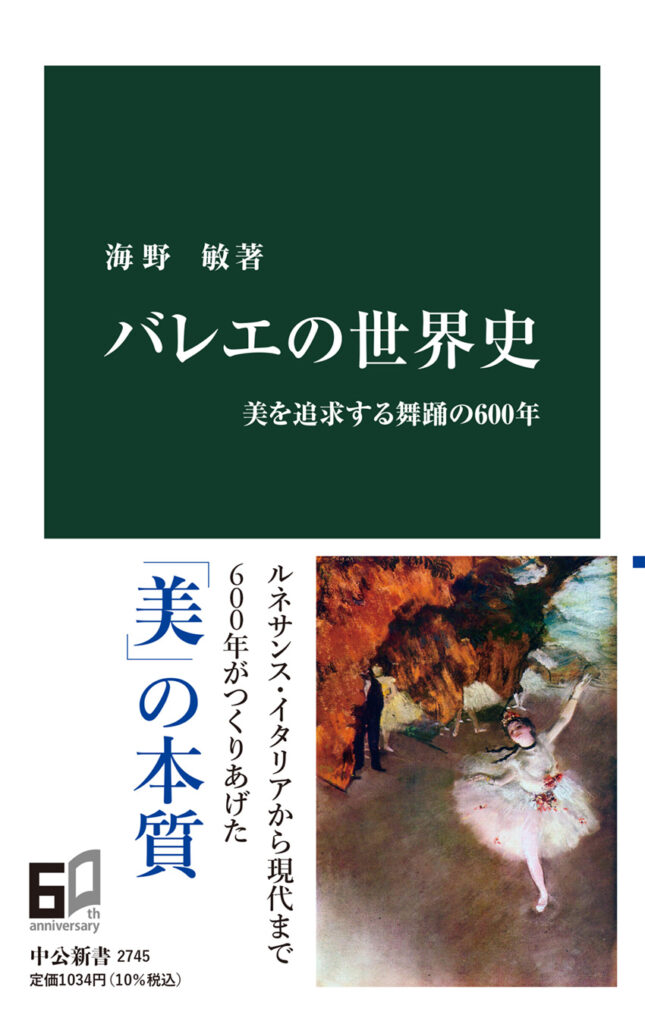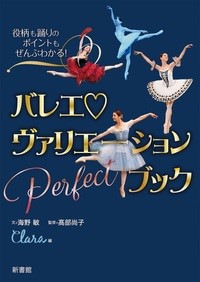文/海野 敏(舞踊評論家)
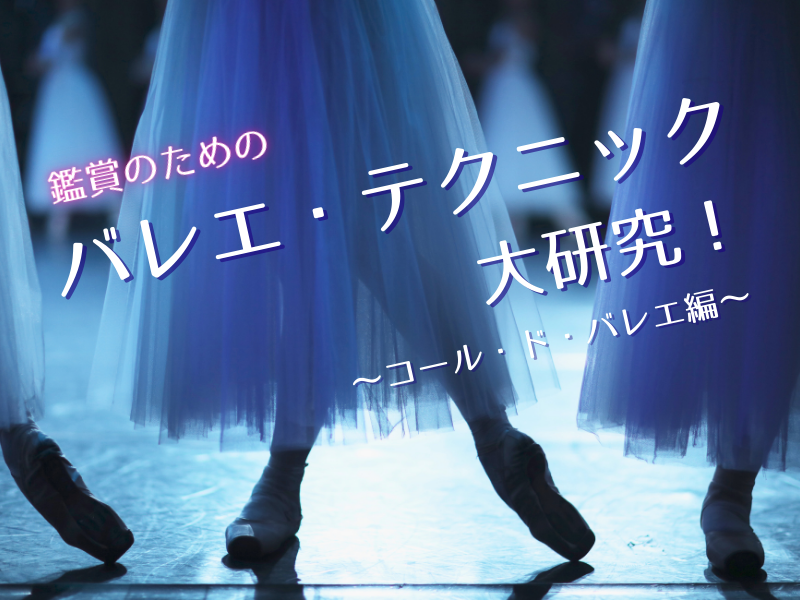
第70回 2群が交差する
■2群に分かれた群舞の動き
前回(第69回)解説した十字またはX(エックス)字のフォーメーションは、群舞が2つに分かれて直線に並び、列の中央付近で交差して大きなかたちを作るフォーメーションでした。今回は、群舞が2つに分かれたまま動くフォーメーションを考えてみましょう。
振付のパターンとしては、①2群がはっきり分かれたまま踊る、②2群がさらに分かれて(例えば4群になって)踊る、③2群が接近して合体し、別なかたちに移行する、④2群が接近してすれ違うなどがあります。これらのパターンは古典全幕作品で、バレエ・ブラン、キャラクター・ダンスのいずれの場面でもよくに目にすると思います。1曲のなかで、①~④の複数のパターンが登場することも珍しくありません。
今回紹介するのは④のパターンです。これも3~8人ずつの2群が互いに近づいてすれ違う振付は、きわめて頻繁に用いられる手法でしよう。しかし、もっと多人数の2群がそれぞれ四角に並び(第64回)、近づいてすれ違う振付が定番となっているものと言えば、『ジゼル』と『白鳥の湖』です。
■『ジゼル』の2群交差
『ジゼル』第2幕の前半では、ウィリの女王ミルタが登場して長いソロを踊った後、支配下のウィリたちを墓地の地下から呼び覚まします。すると左右の袖から、少し俯いて両手首を胸の前で交差させたウィリたちがゆっくり歩み出てきます。左右12人ずつ、4×3列の四角形に整列して登場することが多いです。さらにミルタの部下のドゥ・ウィリ(ズルマとモイナ)も登場します。
そして全員で踊り始めて約4分半後、4×3列の2群が舞台の左右に分かれ、上手側は下手へ、下手側は上手へ向かって、まずその場でアラベスク・ホップ(第22回)を繰り返します。次にドゥ・ウィリも加わって、2群は1小節に1回ずつアラベスク・ホップをしながらじりじり前進を始め、交差します。さらにすれ違った後、全員がフェッテで180度向きを変え、再びアラベスク・ホップの連続で前進して2度目の交差をします。
これは、精霊であるウィリたちが空中で群れをなし、浮遊しながら離合集散する様子を表現した振付だと思われます。アラベスクの後ろ脚を水平に保ちながら進むのは難しいテクニックですが、26人(コール・ド・バレエとドゥ・ウィリ)全員の後ろ脚が水平にそろっているとたいへん美しく、しばしば客席から拍手が起こる名場面です。
- ★動画でチェック!★
- パリ・オペラ座バレエの『ジゼル』第2幕より。映像の冒頭からウィリたちが交差する名場面を観ることができます。
『ジゼル』は、第1幕にも2群の交差が定番の踊りがあります。村人たちが広場で踊る葡萄収穫祭の踊りの序盤で、2群に分かれたダンサーたちが左右から「ジュテ→パ・ド・ブーレ」を繰り返して接近し、すれ違います。1度の交差ではなく、180度向きを変えて2回目、さらに3回目の交差をします(注1)。
- ★動画でチェック!★
- オランダ国立バレエ『ジゼル』の映像より。冒頭の10秒から「ジュテ→パ・ド・ブーレ」を繰り返して交差するシーンを観ることができます。
第1幕終盤、ヒラリオンがアルブレヒトの秘密を暴露する直前の踊りでも、2群の交差が定番です。やはり村人たちが広場で踊る時、2群に分かれたダンサーたちが左右から「ソテ→ソテ→ソテ→ジュテ」で接近し、互いに向きを変えて3、4回交差します。第2幕のウィリたちとは違い、テンポが速く、楽しげに見えるでしょう。しかし、鑑賞のポイントとしては、この踊りの振付は第2幕と呼応しており、人間の世界とウィリの世界、現世と冥界の対比が印象づけられる場面であることを意識してご覧下さい。
- ★動画でチェック!★
- 英国ロイヤル・バレエの『ジゼル』より。わずかですが、映像の4秒から村人たちが楽しげに交差するシーンを観ることができます。
■『白鳥の湖』の2群交差
『白鳥の湖』第2幕で、白鳥たちが1列で進んで登場する場面は、本連載「コール・ド・バレエ編」の初回(第58回)に詳しく解説しました。白鳥たち全員が登場して四角形に整列した後に、2群の交差する定番の振付があります。白鳥たちが2群に分かれ、「ソテ→パ・ド・シャ」を2回繰り返して交差し、腕を大きく回して2度羽ばたいた後、全員が向きを変えて再び「ソテ→パ・ド・シャ」を2回反復して交差する場面です。白鳥たちが羽ばたきながら水面で跳ねている描写でしょうか。
- ★動画でチェック!★
- イングリッシュ・ナショナル・バレエ『白鳥の湖』第2幕より。41秒から交差する振付を観ることができます。
第2幕では、オデットと王子のアダージオの前に白鳥たちが踊るワルツでも2群の交差が見られることがあります。第4幕の湖畔の場面も、いくつかのグループに分かれた白鳥たちが行き交い、すれ違う振付が多く、2群の交差も見られます。しかし、これらは各バレエ団の採用しているヴァージョンごとの差異が大きくて、いずれも定番の振付とは言い切れません。
- ★動画でチェック!★
- パリ・オペラ座バレエ『白鳥の湖』第4幕の映像です。交差する振付は48秒から。自在に変化するフォーメーションをご覧ください。
■その他の作品での2群交差
『眠れる森の美女』第2幕、王子がリラの精に導かれて森でオーロラの幻影と出会う場面でも、森の精たちの踊りで2群の交差が見られることがあります。例えば英国ロイヤル・バレエのダウエル版では、8人ずつの森の精がソテ・アラベスクとアラベスクを繰り返して左右から交差します。
同じ場面の踊りで、パリ・オペラ座バレエのヌレエフ版は、やや複雑な振付を採用しています。森の精たち5×4列がソテ・アラベスクとアラベスクを繰り返して上手へ向かい、上手端になった4人1列が順番に方向を逆転して他のダンサーとすれ違ってゆく振付です。コール・ド・バレエ全体が上手端で方向を180度変えて折り返す動きになっています。
- ★動画でチェック!★
- ローマ国立歌劇場の『眠れる森の美女』第2幕より。1時間30分33秒から交差するシーンを観ることができます。こちらはジャン=ギヨーム・バールによる振付で、ヌレエフ版に近いやや複雑な動きになっています。
ほかにも『ドン・キホーテ』の森の場面(ドン・キホーテの夢の場)で2群の交差が見られることがあります。
(注1)交差をせずに、2群が分かれたまま踊る振付もあります。また、村人たちのこの踊りは、ダンサーたちが6人ずつ腕を組んで踊ることがあります。
(発行日:2025年5月25日)
次回は…
第71回は、コール・ド・バレエにおけるシンメトリーの美について考えます。発行予定日は2025年6月25日です。
- 【鑑賞のためのバレエ・テクニック大研究!-総目次】
- http://bibliognost.net/umino/ballet_tech_contents.html
\NEWS!/
本連載の著者・海野敏さんによる書籍が発売されました! ルネサンス期イタリアから21世紀まで、バレエという舞台芸術の600年を通覧する内容です。
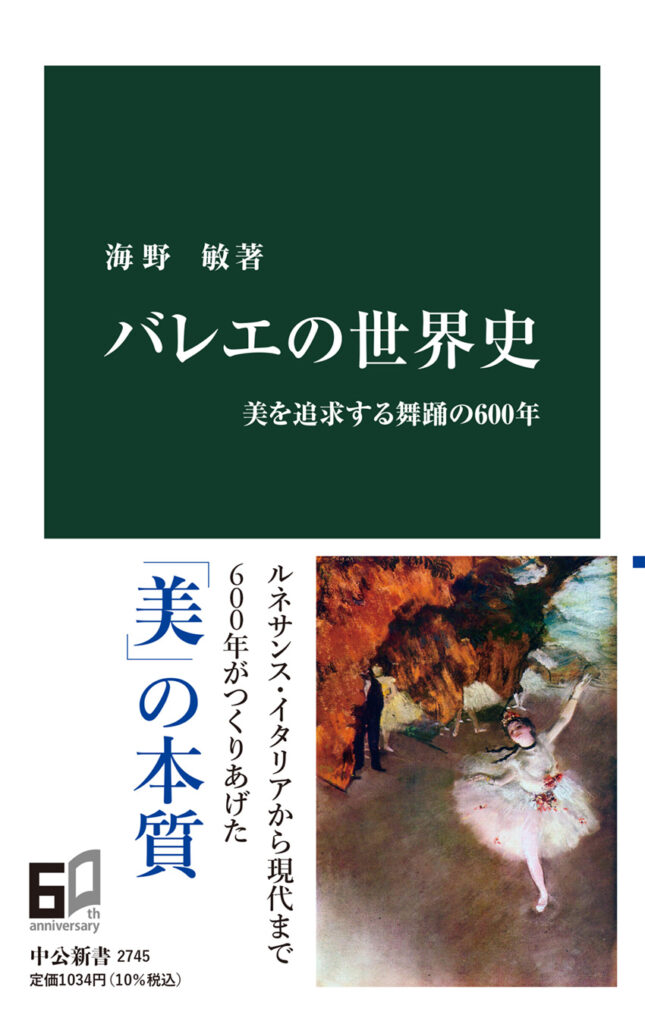
『バレエの世界史:美を追求する舞踊の600年』
海野敏=著
中央公論新社 2023年3月(中公新書2745) 940円(税別)
★詳細はこちら
*
【こちらも好評発売中!】
オーロラ、キトリ、サタネラ、グラン・パ・クラシック、人形の精……等々、コンクールや発表会で人気の 30 のヴァリエーションを収録。それぞれの振付のポイントを解説しています。バレエを習う人にも、鑑賞する人にも役立つ内容です。ぜひチェックを!
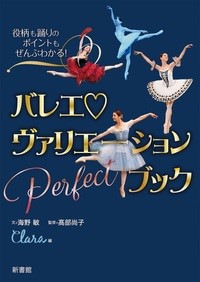
『役柄も踊りのポイントもぜんぶわかる! バレエ♡ヴァリエーションPerfectブック』
海野敏=文 髙部尚子=監修
新書館 2022年3月
★詳細はこちら