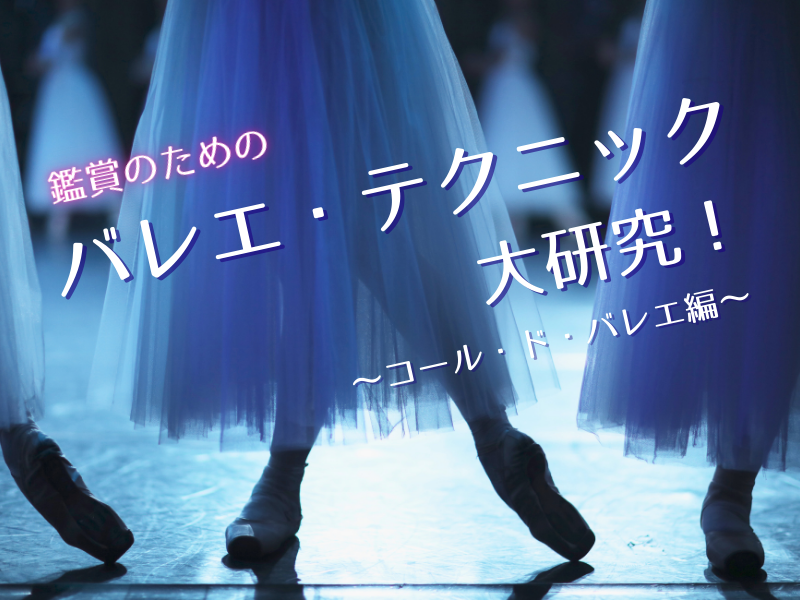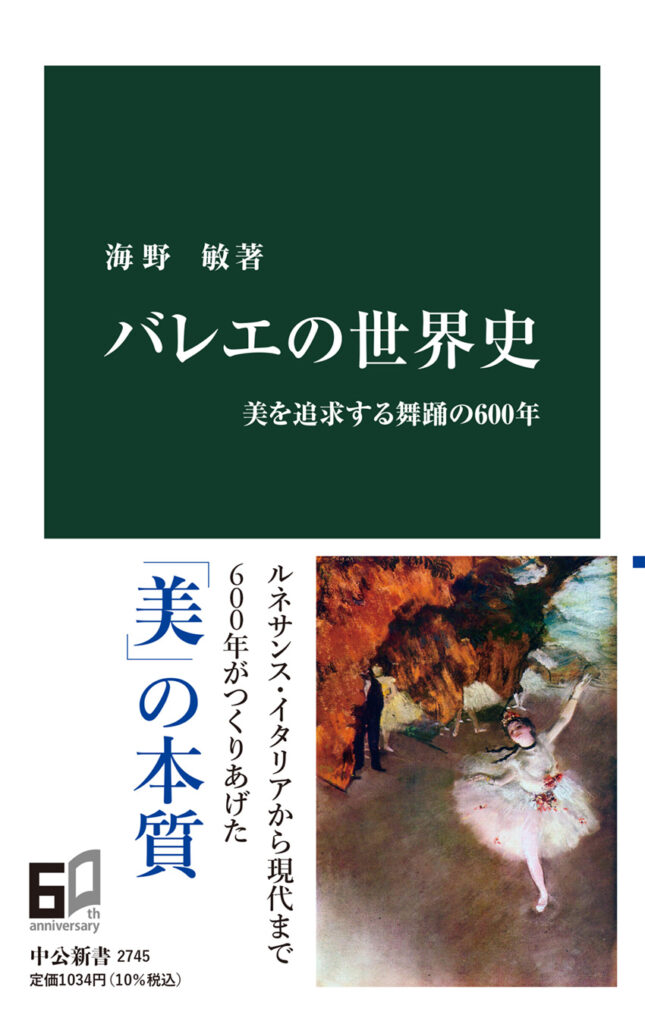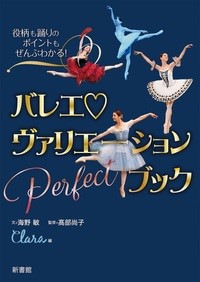文/海野 敏(舞踊評論家)
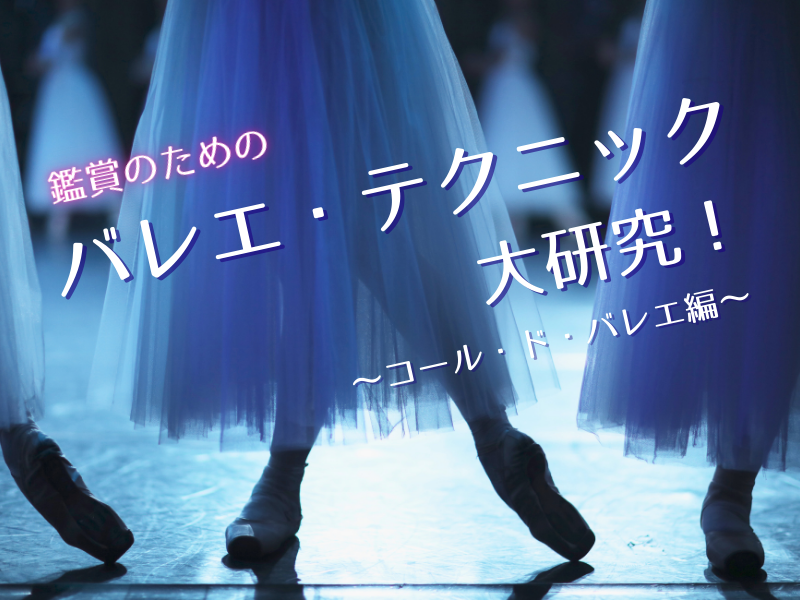
第69回 十字とX字
■2列が交わるフォーメーション
横1列の並びと縦1列の並びが舞台中央で交差すると、十字のフォーメーションとなります。また、上手前から下手奥の並びと下手前から上手奥の並びが舞台中央で交差すると、X(エックス)字のフォーメーションとなります。
コール・ド・バレエのダンサーたちにとって、等間隔で1列に美しく並ぶだけでもたやすいことではありません。2列の交差は、さらに難しくなります。その上、十字やX字のフォーメーションは、その形状を維持したままで回転することがあり、そうするとテクニックの難度がいっそう上がります。
以下、美しい十字とX字の群舞が登場する作品をいくつか紹介いたします。
■『ジゼル』の回転する十字
十字が回転する群舞と聞いて、多くのバレエファンがまず思い出すのは『ジゼル』第1幕前半のコール・ド・バレエでしょう。ジゼルとアルブレヒト(注1)は村の広場でしばらく二人だけの時を過ごしますが、そこへヒラリオンが乱入してひと悶着あり、その後、ジゼルの友人たちが集まってきて、みんなで踊る場面です。
ジゼルを中心にした踊りに続き、それを踊らずに眺めていたアルブレヒトもジゼルに誘われて踊りに加わります。二人で揃ってバロネ(第21回)を繰り返して前へ進む振付が印象的です。しばらくすると突然ジゼルが胸を押さえて苦しそうにしますが、すぐに踊りに戻ります。そしてコール・ド・バレエが十字のフォーメーションになって時計回りに回転を始めると、ジゼルとアルブレヒトは一番外側の対称的な位置について、群舞越しに目を交わしながら、みんなの回転を追い越しつつ踊ります(注2)。回転するので、群舞のかたちは「十字→X字→十字→X字→…」と変わってゆきます。
ジゼルにとって、仲の良い友人たちと一緒に、恋人を伴って踊るのは、とても幸せな瞬間だったに違いありません。観客は、数十分後のアルブレヒトの裏切りを知っていますから、幸せそうに見えるほど痛ましくも見えるのではないでしょうか。
- ★動画でチェック!★
- パリ・オペラ座バレエ『ジゼル』第1幕より。映像の冒頭から一連のシーンを観ることができます。十字の回転は1分30秒から。
■『レ・シルフィード』のX字
『レ・シルフィード』は、ミハイル・フォーキンの振付けた1幕物の作品で、シンフォニック・バレエの古典です。音楽はショパンのピアノ曲をグラズノフが編曲したもので、『ショピニアーナ』の題名で上演されることもあります。一人の男性の詩人が空気の精(シルフィード)たちと踊るという設定ですが、とくにストーリーはありません。
この作品の最後は、全員が「華麗なる大円舞曲」と呼ばれる有名なワルツで踊ります。曲の中盤、テンポが少しゆっくりになり、シルフィードたちが横2列(8人×2列または10人×2列)になります。そして、全員でからだを上下に動かしながら「バランセ→バランセ→パ・ド・ブーレ(第24回)→アティテュード・デリエール」のステップを反復し、少しずつ移動してX字のフォーメーションへと変化してゆきます。
この後、詩人が登場するとX字はすぐに消えてしまいますが、いかにも空気の精たちが風に吹かれてゆらゆらと漂っているような幻想的な群舞が見どころです。
- ★動画でチェック!★
- 新国立劇場バレエ団『レ・シルフィード』のリハーサル映像より。50秒からX字のフォーメーションに変化するステップを少しだけ観ることができます。
■『アレグロ・ブリランテ』ほか
20世紀後半の作品もいくつか紹介しましょう。バランシン振付『アレグロ・ブリランテ』は、幕が上がってから踊り始めるのではなく、幕が上がるとすでにダンサーたちが踊っているという珍しい演出です。男女4組のペアが手をつなぎ、十字のフォーメーションになって、反時計回りに回転しながら踊っています。つないだ手を放すと、今度は時計回りに「十字→X字→十字→X字→…」と回転しながら踊ります。十字・X字は30秒ほどにすぎませんが、舞台に引き寄せられる巧みな幕開きではないでしょうか。
- ★動画でチェック!★
- ジョフリー・バレエの『アレグロ・ブリランテ』より。映像の冒頭から十字とX字のフォーメーションを観ることができます。
クランコ振付『オネーギン』では、X字のフォーメーションではないのですが、群舞がX字をなぞって駆け抜ける場面がとても魅力的。第1幕、タチヤーナの暮らす屋敷の中庭で、若い男女が集って踊る場面です。その後半、いったん全員が袖へ入った後、9組の男女が次々と登場し、男性が女性のグラン・パ・ド・シャ(第12回)をサポートしながら舞台を斜めに駆け抜けます。まず上手奥から下手前へと斜めに走り抜けた後、すぐに下手奥から上手前へと走り抜けて、結果としてX字を描くのですが、その群舞が一体となったスピード感が見どころです(注3)。
- ★動画でチェック!★
- ウィーン国立歌劇場の『オネーギン』のトレイラーより。グラン・パ・ド・シャで舞台を斜めに駆け抜けるシーンを9秒から少しだけ観ることができます。
ベジャールには『突然変異X』という変わった題名の振付作品があります。題名通り、ダンサーたちが舞台いっぱいに広がってX字に並ぶ場面があります。
(注1)貴族のアルブレヒトは変装し、ジゼルには「ロイス」と名乗って近づいています。
(注2)十字にはならず、長い1列で回転する振付もあります。
(注3)この踊りは、タチヤーナの妹オリガとオネーギンの友人レンスキーが中心になって、村の若者たち16人と踊ります。なお、2025年1月の英国ロイヤル・バレエの『オネーギン』は、筆者が「英国バレエ通信〈第46回〉」でレポートいたしました。
(発行日:2025年4月25日)
次回は…
第70回は、2群が移動して交差するコール・ド・バレエを取り上げます。発行予定日は2025年5月25日です。
- 【鑑賞のためのバレエ・テクニック大研究!-総目次】
- http://bibliognost.net/umino/ballet_tech_contents.html
筆者による講座の紹介
2025年5~6月、早稲田大学エクステンションセンターの春季講座で「世界史のなかのバレエ~美を追求する舞踊の600年」という講座を行います。全6回で金曜の午前中、早稲田キャンパスで行います。詳細は同センターのウェブページをご覧下さい。
https://www.wuext.waseda.jp/course/detail/65202/
会員資格は4年間有効で、同センターが開講している100を超える講座を会員料金で受講できるほか、早稲田大学中央図書館が利用できるなどの特典があります。
\NEWS!/
本連載の著者・海野敏さんによる書籍が発売されました! ルネサンス期イタリアから21世紀まで、バレエという舞台芸術の600年を通覧する内容です。
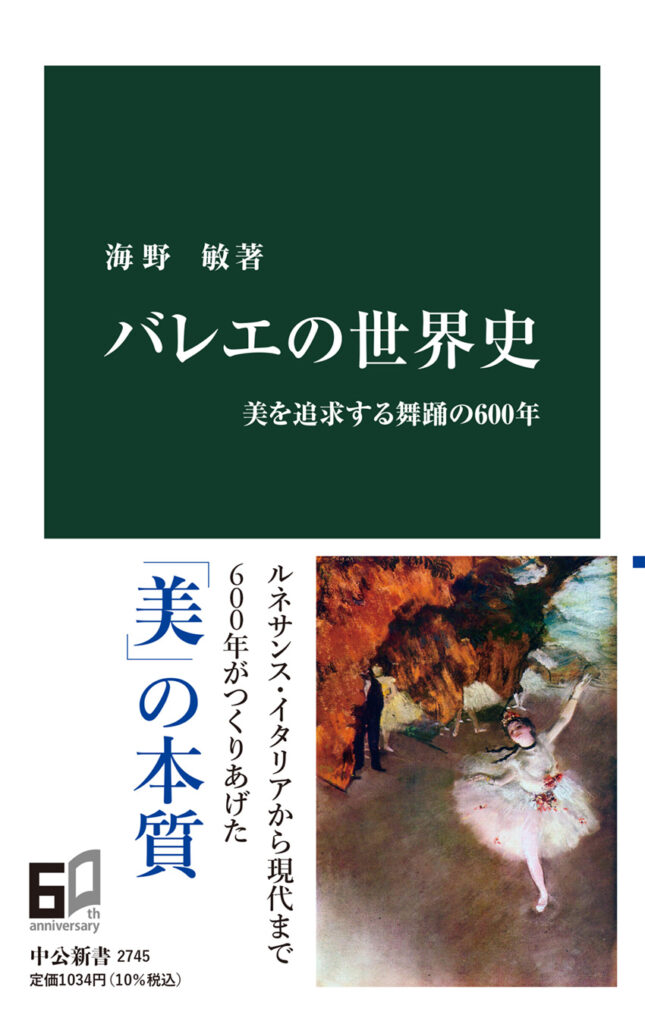
『バレエの世界史:美を追求する舞踊の600年』
海野敏=著
中央公論新社 2023年3月(中公新書2745) 940円(税別)
★詳細はこちら
*
【こちらも好評発売中!】
オーロラ、キトリ、サタネラ、グラン・パ・クラシック、人形の精……等々、コンクールや発表会で人気の 30 のヴァリエーションを収録。それぞれの振付のポイントを解説しています。バレエを習う人にも、鑑賞する人にも役立つ内容です。ぜひチェックを!
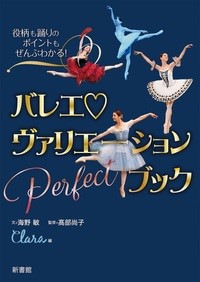
『役柄も踊りのポイントもぜんぶわかる! バレエ♡ヴァリエーションPerfectブック』
海野敏=文 髙部尚子=監修
新書館 2022年3月
★詳細はこちら