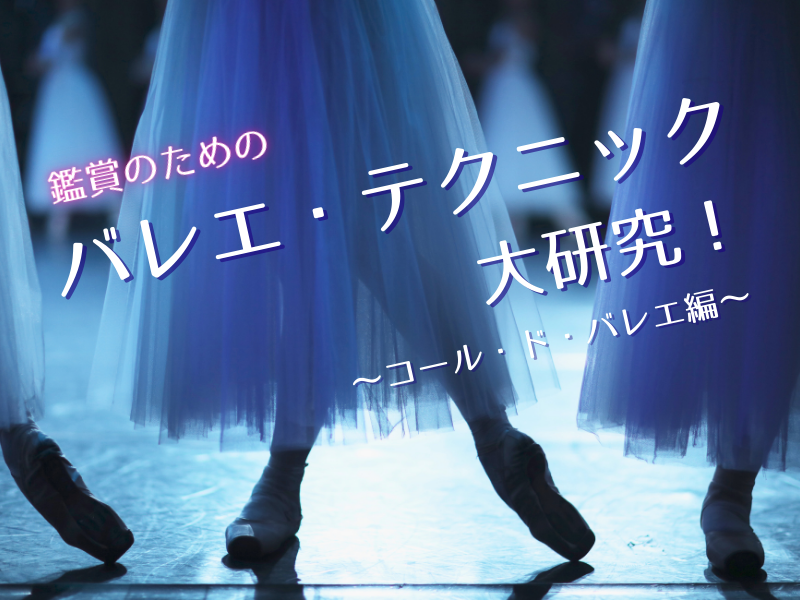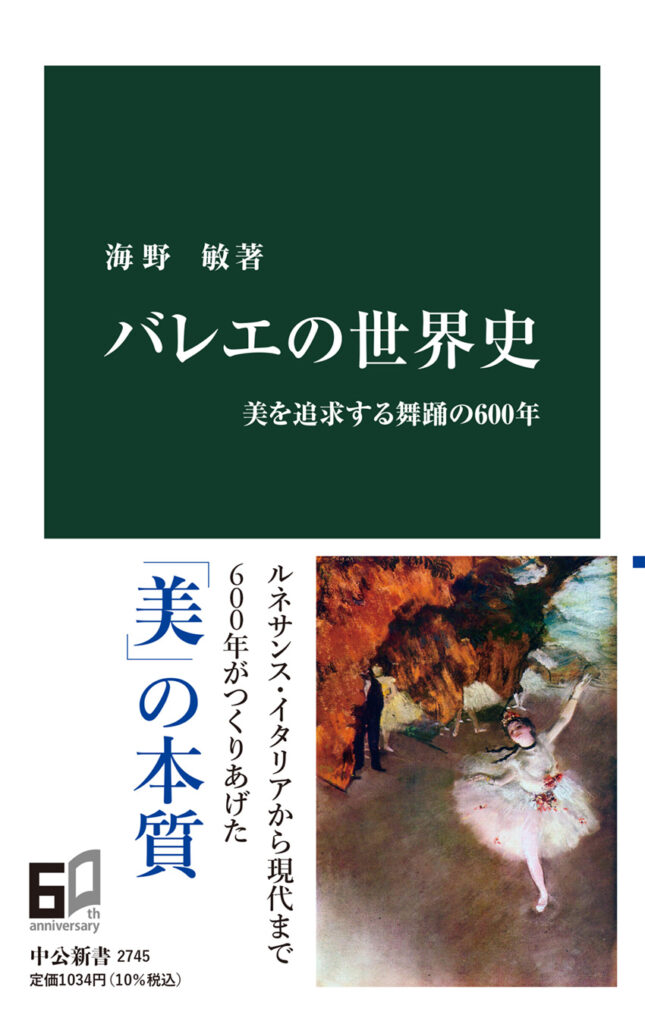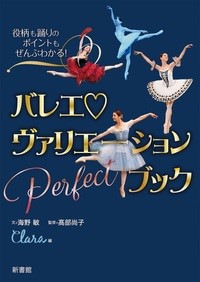文/海野 敏(舞踊評論家)
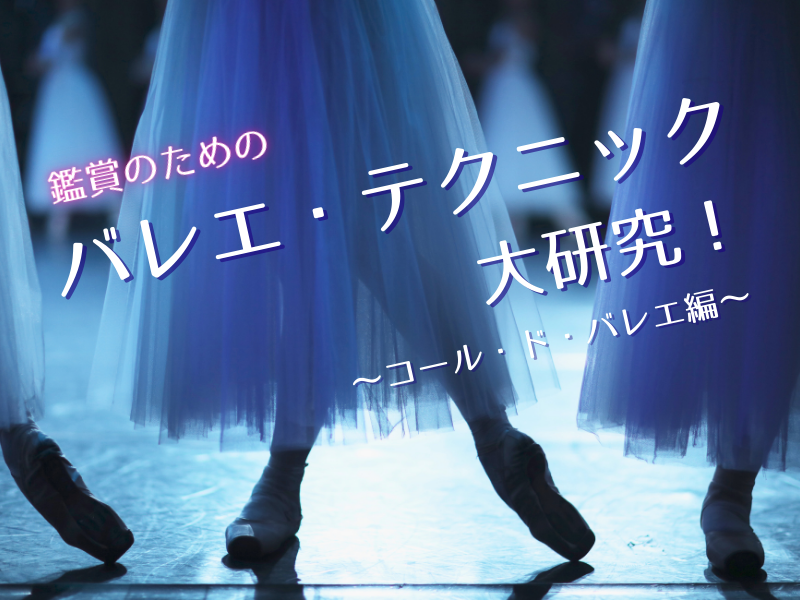
第73回 増えてゆく
■人数が増えてゆく効果
これまでコール・ド・バレエの演出・振付テクニックとして、四角、三角、円形、十字など、ダンサーたちが舞台上に作り出す「かたちの変化」に注目してきました。今回はダンサーたちの「数の変化」に注目します。
バレエに限らず、いずれの舞台芸術(注1)においても、徐々に舞台上の人数が増えてゆく演出はよくあるパターンです。その基本的な効果は、観客の期待感と緊張感を少しずつ高め、舞台の盛り上がりを自然に生み出すことでしょう。
古典バレエの全幕作品では、舞台上の人数が増えてゆく場面に2つの典型的なパターンがあります。①舞台上のダンサーの数が徐々に増え、最後に主役が登場するパターンと、②まず主役のみが登場し、その後で徐々にダンサーが増えてゆくパターンです。
①は、主役の男女がめでたく結ばれる作品で、最終幕の婚礼シーンが典型的です。例えば『眠れる森の美女』、『ドン・キホーテ』、『ライモンダ』、『コッペリア』は、いずれも最終幕の冒頭が、結婚を祝う人々が次々に入場し、最後に主役2人が登場するという流れになっています。舞台上の人数が徐々に増え、満を持して主役が現れることで、その存在を際立たせる効果が加わります。
- ★動画でチェック!★
- ミラノ・スカラ座バレエ『コッペリア』よりフィナーレの映像です。こちらの演出では1分53秒から、人々に囲まれてスワニルダがグラン・フェッテを披露する華やかなシーンを観ることができます。
②は、主役の男女が初登場する幕の冒頭に現れることが多いパターンです。たとえば『ラ・シルフィード』第1幕は主人公2人の場面で始まり、次第に舞台上の人数が増えてゆきます。『白鳥の湖』第2幕は、主人公2人が出会った後に白鳥たちが登場します。『ジゼル』と『コッペリア』の第1幕は、どちらも主役男女が別々に登場し、直後に2人が一緒に演技する場面が続き、その後舞台上の人数が増えてゆきます。これらの作品は①と逆に、まず主役が単独で演技をしてその存在を際立たせ、その後に舞台上の人数が増えてゆくことで物語の世界がダイナミックに立ち上がる流れになっています。
- ★動画でチェック!★
- 新国立劇場バレエ団『ラ・シルフィード』の映像です。ジェームスの前にシルフィードが現れる印象的な場面を観ることができます。
以上は数曲の音楽にまたがって、場面を通して人数が増えてゆく演出についてでした。では、1曲の踊りの中でコール・ド・バレエの人数が増えてゆく振付には、どのようなものがあるでしょうか。
■「1列で進む」再考
じつは「1曲の踊りの中でコール・ド・バレエの人数が増えてゆく振付」の2つの傑作は、本連載で既に詳しく紹介しました。
1つは『白鳥の湖』第2幕で、白鳥を演じるダンサーたちが1列縦隊で登場するシーンです。第58回「1列で進む(1)」で詳述しました。主人公のオデットと王子が退場していったん空になった舞台上に、24羽の白鳥たちが舞台上手奥から長い1列になって登場し、1分足らずで舞台を埋めて、横6×縦4の隊形に並ぶ場面です。音程が上昇してゆくアレグロの音楽とともに、誰もいなかった舞台が白鳥たちで埋まってゆく情景は、観客に「これから何が起こるのだろう」という期待感をもたらします。
- ★動画でチェック!★
- イングリッシュ・ナショナル・バレエの『白鳥の湖』より第2幕。白鳥たちが登場するシーンを映像の冒頭から観ることができます。音楽に合わせて、舞台が24羽の白鳥たちで埋まってゆく情景をお楽しみください。
もう1つは『ラ・バヤデール』第3幕「影の王国」の冒頭で、舞姫を演じるダンサーたちが1列縦隊で登場するシーンです。第59回「1列で進む(2)」で詳述しました。主人公のソロルとニキヤが退場して舞台が空になった後、舞台奥の坂の上に舞姫たちが1人ずつ現れ、だんだんと増えてゆくシーンです。ミンクスの音楽はゆったりとしたラルゴのテンポで、24人(または32人)の舞姫たちが坂を下りて整列するまで約5分かかります。誰もいなかった舞台がじわじわと舞姫たちで埋まってゆく情景は、観客に美しい幻を見るような陶酔感をもたらします。
- ★動画でチェック!★
- パリ・オペラ座バレエの『ラ・バヤデール』より。「影の王国」のコール・ド・バレエを映像の冒頭から観ることができます。舞姫たちによる美しい情景をお楽しみください。
緩急の差はありますが、いずれも無人の舞台から始まって、ダンサーが舞台を埋めてゆく振付です。数ある古典全幕作品のコール・ド・バレエで、筆者は“トップ2”の名場面だと思っています。
■増えてゆく振付のおすすめ
その他の古典全幕作品で、私がつねづね鑑賞のポイントにしている「1曲の踊りの中でコール・ド・バレエの人数が増えてゆく振付」を3つ紹介しましょう。
1つ目は『パキータ』第3幕、「グラン・パ・クラシック」の冒頭部分。これは第60回「1列で進む(3)」で取り上げました。クラシック・チュチュを着たダンサーたちが、4人→4人→2人→2人→2人の順番で登場し、舞台左右に並ぶ人数が4→8→10→12→14と増えてゆき、最後に主役のパキータが颯爽と登場します。ミンクスの音楽は乗りがよく、登場する組ごとに少しずつステップが違う振付はどれも華やかで、2分ほどですがとても見応えのある場面です。
- ★動画でチェック!★
- パリ・オペラ座バレエ『パキータ』より第3幕のアントレの映像です。パキータが颯爽と登場するシーンを観ることができます。
2つ目は『くるみ割り人形』第1幕の終盤、「雪の精の踊り」の冒頭部分。「雪の精の踊り」はヴァージョンによって振付が千差万別ですが、ワイノーネン版を元にした振付は「増えてゆく振付」の傑作です。これも第66回「円形に並ぶ(1)」で詳しく解説しました。チャイコフスキーの軽快なワルツに乗って舞台の四隅からダンサーが4人ずつ登場し、円を描きながら4→8→12→16と増えてゆきます。1分半ほどですが、粉雪が風に吹かれて渦を巻く様子が伝わる素晴らしい振付です。
- ★動画でチェック!★
- イングリッシュ・ナショナル・バレエ『くるみ割り人形』第1幕より「雪の精の踊り」の映像です。雪が舞う情景をみごとに表現しています。
3つ目は『眠れる森の美女』のプロローグで、リラの精を中心とした6人の妖精(注2)とそのお付きの妖精たちが登場する場面。これもヴァージョンによって振付の差が大きい場面ですが、筆者はどのように妖精が増えてゆくのかを鑑賞のポイントにしています。たとえば、(a)お付きの妖精たちが登場した後にリラの精が登場し、5人の妖精を呼び出すパターン、(b)お付きの妖精たちと一緒に5人の妖精が登場し、最後にリラの精が登場するパターン、(c)5人の妖精が登場してから、お付きの妖精たちとともにリラの精が登場するパターンなどがあります(注3)。この場面のチャイコフスキーの音楽は、ハープのアルペジオで始まる優雅なワルツです。『眠れる森の美女』を鑑賞するときには、プロローグでどのように妖精たちが増えてゆくのかにも注目してみて下さい。
- ★動画でチェック!★
- ローマ国立歌劇場『眠れる森の美女』の全幕映像です。6分30秒より妖精たちが登場します。こちらの映像では(a)のパターンを観ることができます。
- ★動画でチェック!★
- パリ・オペラ座バレエ『眠れる森の美女』の紹介映像です。作品解説の合間に、プロローグの妖精たちの場面を一部観ることができます。ヌレエフ版の振付では、(b)のパターンが用いられています。
- ★動画でチェック!★
- 牧阿佐美バレヱ団『眠れる森の美女』の紹介映像です。プロローグの妖精たちの場面は1分3秒から。こちらの映像では、おつきの妖精たちを連れてリラの精が後半に登場する(c)のパターンを観ることができます。
(注1)舞台芸術とは、演技を見せるために設けられた特定の空間において実演される芸術のことで、さまざまなジャンルのダンス、各種の演劇、ミュージカル、オペラ、さらに能・狂言・歌舞伎のような伝統芸能などをすべて含みます。演技を見せるために設けられた特定の空間は「舞台」と呼ばれ、専用の劇場内だけでなく、仮設されることや、路上や広場など日常的な場所に設けられることもあります。
(注2)リラの精(知恵の精)以外の5人の妖精は、ヴァージョンによってさまざまな役名が付いています。チャイコフスキーの原譜では、夾竹桃(花言葉から美の精)、三色ひるがお(花言葉から優雅の精)、パンくずの精(食物の精)、歌うカナリアの精(雄弁の精)、激しさの精(健康の精)です[出典:音楽之友社編『チャイコフスキー』音楽之友社, 1993, p.91]。
(注3)お付きの妖精たちの登場の仕方には、数人ずつ登場の場合と一度に登場する場合があります。5人の妖精も、1人ずつ登場する場合と5人一緒に登場する場合があります。また、リラの精と5人の妖精にはカヴァリエ(従者の騎士)役の男性ダンサーが1人ずつ付き添う場合も少なくありません。
(発行日:2025年8月25日)
次回は…
第74回は、舞台上のダンサーの人数が減ってゆく演出・振付について考えます。発行予定日は2025年9月25日です。
- 【鑑賞のためのバレエ・テクニック大研究!-総目次】
- http://bibliognost.net/umino/ballet_tech_contents.html
\NEWS!/
本連載の著者・海野敏さんによる書籍が発売されました! ルネサンス期イタリアから21世紀まで、バレエという舞台芸術の600年を通覧する内容です。
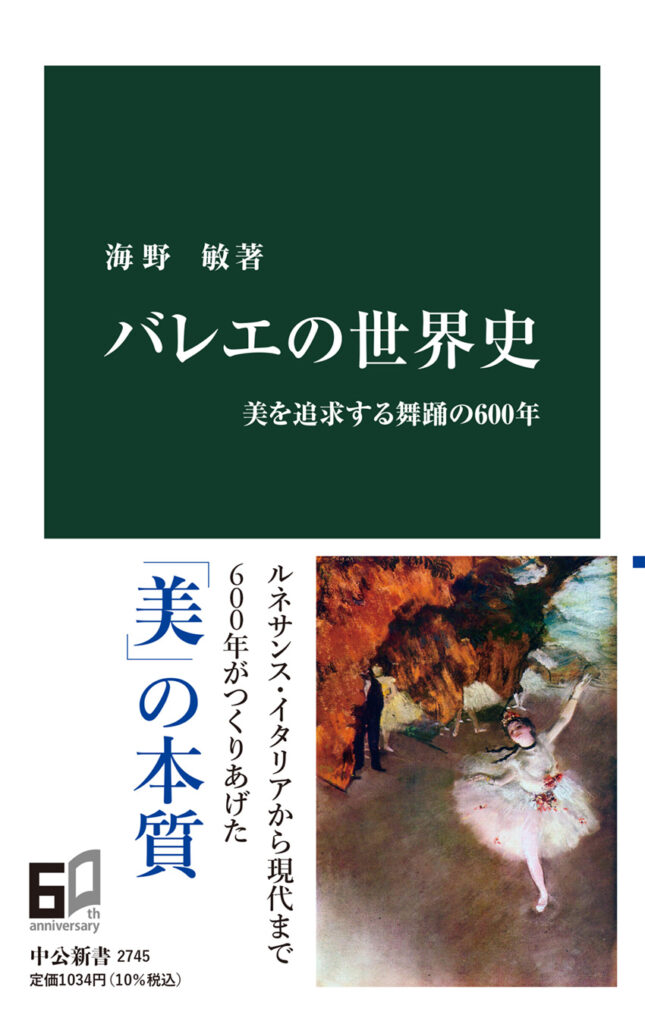
『バレエの世界史:美を追求する舞踊の600年』
海野敏=著
中央公論新社 2023年3月(中公新書2745) 940円(税別)
★詳細はこちら
*
【こちらも好評発売中!】
オーロラ、キトリ、サタネラ、グラン・パ・クラシック、人形の精……等々、コンクールや発表会で人気の 30 のヴァリエーションを収録。それぞれの振付のポイントを解説しています。バレエを習う人にも、鑑賞する人にも役立つ内容です。ぜひチェックを!
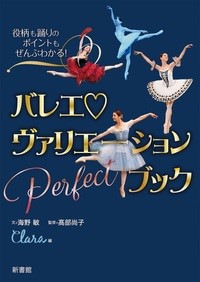
『役柄も踊りのポイントもぜんぶわかる! バレエ♡ヴァリエーションPerfectブック』
海野敏=文 髙部尚子=監修
新書館 2022年3月
★詳細はこちら