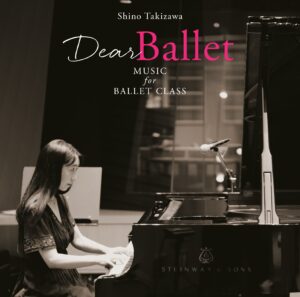新譜レッスンCD「Dear Ballet〜Music for Ballet Class」のPVを公開!
ダンサーは東京バレエ団ソリストの中島映理子さんです
撮影・編集:星野一翔、大久保嘉之
ウィーン国立バレエ専属ピアニスト滝澤志野の新譜レッスンCD「Dear Ballet〜Music for Ballet Class」(ディア・バレエ〜ミュージック・フォー・バレエ・クラス)が、2025年11月下旬より全国のバレエショップにて発売されました。
本CDのライナーノーツより、音楽学者・永井玉藻(ながい・たまも)さんの解説(*)を特別公開します。
*この記事はCD「Dear Ballet〜Music for Ballet Class」添付ブックレットより転載しています
踊ることで見え、聴こえる音楽
文/永井玉藻(音楽学者)
客電が落ち、劇場の中が闇に包まれる。指揮棒が上がるとオーケストラ・ピットから流れ出す序曲の音楽。ああ、いよいよ待ちに待った公演が始まる。その瞬間にドキドキし、笑みが溢れる人も多いだろう。あるいはスタジオで、バーに手を添えると聞こえてくるピアノの音。音楽を身体に取り込むように、ゆっくりと深く呼吸し、身体をすみずみまで動かしていく。バレエにとって音楽は重要なパートナーであり、動力源であり、呼吸であり、物語やキャラクターを彩り生き生きとさせてくれる栄養のようなものである。
しかし、音楽の側からするとどうだろうか。西洋芸術音楽研究の歴史において、バレエ音楽は長いあいだ、考察の対象にはなりづらかった。学術研究の場だけでなく、一般的な芸術音楽愛好家たちにとっても、バレエ音楽の優先度は高くない。19世紀フランスのバレエ音楽作曲で知られるレオ・ドリーブについて、史上初の包括的な研究書を(2017年になってやっと)出版したフランスの音楽学者、ポーリーヌ・ジラールも、論文の中で「バレエ音楽は、一般大衆にはほとんど評価されず、同時に作曲家にもあまり求められていないという悪循環に陥っている。特にバレエ音楽は儲けが少なく、創作の自由が非常に限られているためだ」とバッサリ書いている。チャイコフスキーやプロコフィエフのような、音楽史に名を残した作曲家たちがバレエにも手を出したのは例外中の例外なのであって、シュナイツホーファーやミンクスといった面々は、一般的な西洋芸術音楽史の教科書で触れられることはまずない。せいぜいアダンが、オペラの文脈で言及されていれば良いほうである。
バレエ音楽を軽視する伝統的な音楽学のこうした傾向には、もちろん理由がある。第一に、交響曲や協奏曲といった、芸術音楽のヒエラルキーの中でも頂点に位置付けられる楽曲ジャンルに比べ、バレエの音楽は変動性が高すぎる。19世紀以来の西洋芸術音楽研究は、主に作品およびその創作者である作曲家を、中心的な考察対象として扱ってきた。そこでは作品=固定した状態のものであり、創作者の手によって生み出された作品は変化しないもの、創作者以外の人間が手を入れることはナンセンス、と考えられてきた。ところがバレエでは、プロダクションによって音楽の順番や曲尺が変わったり、他のバレエ作品の楽曲が文脈に関係なくつっこまれたりする。そのため、研究者にとってバレエ音楽は非常に扱いづらいジャンルなのである。クラスレッスンの音楽に関しても同様に、その曲本来の強弱やアクセント、楽曲の長さを臨機応変に変更して演奏するなど、楽譜テクストに対する忠実さに価値を置く芸術音楽の視点から見れば、「ありえない」の一言に尽きるだろう。実際、既存の楽曲を用いたバレエ作品では、振付に適合させるために演奏がデフォルメされることがある。そのため、例えばノイマイヤー振付の《椿姫》第3幕で演奏されるショパンのバラード第1番の演奏に、強烈な違和感を覚える音楽愛好家は少なくない。
第二に、音楽が振付の伴奏になる、という視点からすると、音楽としてすでに出来上がっている芸術に何か別のものがくっついたり、音楽が別の芸術のために奉仕したりする状態は、音楽そのものの深い探究を目指す音楽学の枠内には入りづらい。いや、オペラだって、言葉というプラスアルファがあるじゃないか、というツッコミが瞬時に飛んでくるだろうが、台本や歌詞という、先に出来上がっているものに対して後から音楽をつけるのは、「音楽による解釈」なので、オペラは問題ないのである。同じ文脈で、マリウス・プティパによる音楽への厳しい注文に見事に応えつつ、要求を上回るほどの音楽を生み出したチャイコフスキーや、振付家と密接に関わりながら共同制作をしたストラヴィンスキーやプロコフィエフは、振付に従属しなかったという点で音楽学的な視点からの研究対象になる(もっとも、彼らの楽曲は構成の緻密さや楽器の扱いの巧みさ、完成度などが高いので、そこですでに伝統的な音楽学の考察対象になるのだが)。

レコーディング風景より。撮影は志野さんの1枚目のアルバムからレコーディングを担当しているSony Music Studioエンジニアの房野哲士さん ©︎Satoshi Bono
こうした背景があったので、2024年夏に滝澤志野さんと対談した際、つい「音楽学の分野でバレエのことは完全に無視されているんですよねえ」と愚痴をこぼしてしまった。言い訳をすると、私のこの発言は、その後の影響などを特に考えずにぽろっと口から出たものだった。学術研究の対象としてバレエ音楽は「微妙」、というのは、西洋芸術音楽研究のための伝統的な訓練を受けてきた音楽学者の私にとって、あまりにも自明すぎる事実だからである。しかしその発言は、バレエ・ピアニストとして第一線で活躍している志野さんに、激震を走らせてしまったらしい。「音楽学の世界において、バレエ音楽はほとんど無視されている」という現実へのショックが、やがて「宝石のようなバレエ音楽ーーその真の美しさを、音楽家として伝えたい」という強い思いにつながり、本CDが生まれる契機になったと伺った。
このたびのCDのために彼女が選び抜いたのは、バレエ音楽としては王道中の王道の楽曲ばかりである。「王道」、すなわち、数々の振付家が踊りのための楽曲として向き合い、レパートリーとして受け継がれるプロダクションを生み出してきただけでなく、ダンサーたちがその研ぎ澄まされた身体によって細かなニュアンスまでも表現してきたものだ。そしてもちろん、多くのバレエファンに愛され、口ずさまれてきた楽曲である。クラスレッスン用に作られたCDではあるが、この一枚でバレエの世界を代表する楽曲を聴けるとは、なんと贅沢なことだろう。しかも寄せ集めの名曲集ではなく、踊る人のことを考えて演奏された音源であり、演奏からは身体の動きと呼吸が明確に感じられる。
もしもバレエが、ジャンプの高さや回転数といった、ダンサーの身体能力の高さを愛でるだけのものであれば、バレエに音楽は必須ではない。タイミングやリズム感の訓練をしたいのであれば、先生の手拍子やメトロノームに合わせてレッスンをすれば良い。しかし実際には、長い歴史の中でバレエ音楽は必要とされてきた。それはやはり、音楽が持つ表情や個性、特徴をも含めて人間の身体で踊ることがバレエだ、と考えられているからではないかと思う。だからこそ、クラスレッスンの段階から音楽とともに身体を動かすのであり、その時点から、音楽を表現することは始まっている。これは拙著『バレエ伴奏者の歴史 19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々』で、志野さんを始めバレエに関わるさまざまな方へのインタビューをして、私が痛感したことでもある。
バレエ音楽の中には、ストラヴィンスキー作曲の《春の祭典》や《火の鳥》、ラヴェル作曲の《ダフニスとクロエ》のように、今日ではオーケストラのコンサートピースとしての演奏機会のほうが多いものもある。しかし、そもそもバレエ音楽はバレエのために作られたのだ。バレエ音楽には、踊られることで見え、聴こえてくる音楽としての魅力がある。単純だが忘れられがちなその事実を、志野さんの演奏は私たちに教えてくれるのではないだろうか。

PV撮影現場にて ©︎Yoshitomo Okuda
ダンサー:中島映理子(東京バレエ団)
ヘアメイク:加藤小織
レオタード、スカート、チュチュ:バレエショップ FAIRY
- 永井玉藻(ながい・たまも)
- 東京大学大学院人文社会系研究科 特任研究員(学振RPD)
1984年生まれ。パリ第4大学博士課程修了(音楽および音楽学博士)。専門は西洋音楽史、舞踊史。現在、音楽と舞踊動作の関係をテーマとした研究を行うほか、慶應義塾大学、白百合女子大学他で非常勤講師を勤めている。
ご購入はこちら
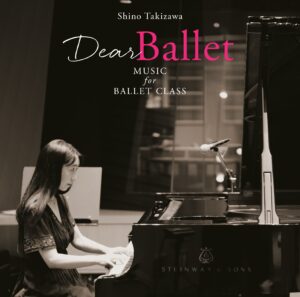
Dear Ballet(ディア・バレエ)〜Music for Ballet Class
滝澤志野(ウィーン国立バレエ専属ピアニスト)
●ピアノ演奏:滝澤志野
●企画・制作協力:阿部さや子(バレエチャンネル)
●製作・販売:新書館
●価格:3,960円(税込)
♪収録曲等の詳細はこちら
♪購入はこちら