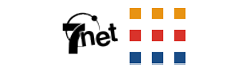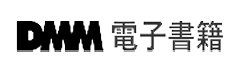“Contemporary Dance Lecture for Ballet Fans”
ダンスにおけるセクシュアリティとLGBTQ+ 〜「本当の愛」は、「本当の自分」の中にあるよ〜
いよいよ最終回である。
身体芸術であるダンスにおけるセクシュアリティは、きわめてデリケートで本質的な問題だ。
古典でもコンテンポラリー・ダンスでも、生きることのアクチュアリティを追求している以上、愛と性の問題は避けては通れない。
それらは隠すべきものとされてきた時代もあったし今も表向きはそういうことになっているが、ダンサーが自分の身体のリアルを突き詰めていけば、とうぜんぶち当たる壁である。
なぜならそれは単なる情欲のみならず恋愛や友情や、家族愛、ひいては人類愛にまで波及していくからだ。さらにそのエネルギーがマイナスに転じれば、嫉妬や暴力や支配といったダークな方向にまで広がっていく。
そしてこの両者の葛藤こそ、古来から現代まであらゆる芸術の原動力になってきた。
もうひとつ重要なのが、ジェンダーやLGBTQ+(性的マイノリティ)の問題である。本人にとって重要な問題であると同時に、社会的な差別(生活上の不利益、ときに直接的な暴力など)という意味からも、アート全体の重要な課題になっている。
むろんみずからの身体をメディアとして表現するダンサーにとっては、「生活する身体」と「踊る身体」は不可分であり、より切実な問題とならざるを得ない。
本稿ではダンスにおける「セクシュアリティの表現」と「ジェンダーとLGBTQ+の表現」について見ていこう。
ダンスにおけるセクシュアリティの表現
●セクシャルな表現
中世以降、ほとんどの西洋美術がキリスト教の影響下で性的表現は押さえられたが、ルネサンス以降はギリシャ・ローマ神話に登場する神々のヤンチャすぎる所業も暗喩や象徴で描かれるようになった。
ミシェル・フーコーが言うように、本質的に人は性的なことを隠したい気持ちと語りたい気持ちの、相反する衝動を持っているのだろう。
たとえばバレエにもよく使われる白鳥も、絵画や彫刻ではギリシャ神話で「美しいレダを誘惑するためにゼウスが白鳥に変身した」ことが画題となっている。その多くはレダが白鳥の長く伸びた首を優しく愛撫するなどの暗喩が多く描かれている。
そして拙書『ダンス・バイブル』に詳しいが、モダンダンス(バレエ以外の新しい芸術的ダンス)の誕生には、紳士淑女が通うミュージックホールはもちろん、オリンピック内のアトラクションとしてもストリップティーズ(サリー・ランドなど)が重要な役割を果たしてきた。切っても切れない仲なのである。
そこでダンスにおけるセクシャルな表現を、以下の3つに分類してみよう。
- 〈ダンスに見るセクシャルな表現〉
-
- その1:愛情の結果として
- その2:欲望の結果として
- その3:暴力の結果として
●その1:愛情の結果として
最もオーソドックスな表現といえる。
『ロミオとジュリエット』の第3幕で、初めての夜を共に過ごした二人がベッドの中で目を覚ますなど、一対一の関係から、愛情の交歓が描かれる。
そして第4幕では、ジュリエットが仮死状態で横たえられた地下墓地の棺桶台はベッドを想起させる。
短剣でみずからの身体を貫き、互いの死をもって結ばれるラストは、エロス(愛)とタナトス(死)のひとつの完成形といえるだろう。
●その2:欲望の結果として(個人的なもの)
性的な欲望は、本来的にカオティックなものなので、欲情が爆発することもあれば、生殖を含めた「生きることの根源的なエネルギー」に昇華することもある。
「個人的な欲望の暗喩」としての名作はバレエ・リュスでミハイル・フォーキンが振付けた『薔薇の精』である。
舞踏会から帰ってきた乙女が、肘掛け椅子でまどろんでいる。手にした一輪の薔薇が床に落ちる。それは舞踏会で好意を寄せる相手から手渡されたものかもしれない。すると官能的な香りが受肉したかのように肉感的な薔薇の精が現れて、二人はワルツを踊りはじめる。
まだ未分化な乙女の恋の衝動が、薔薇の精とのワルツという形をとっているのだ。
初演時は、乙女にタマラ・カルサーヴィナ。技術はもちろんだが、可憐な容姿と、私生活でも派手さを好まない清純な真面目さが、当時のパリで人気を高めていた。
対する薔薇の精はヴァスラフ・ニジンスキーである。第13回「ダンスにおける『美しさ』問題」でも触れたように、蠱惑的な衣裳だ。天才的な跳躍力を誇るニジンスキーの太ももは写真で見てもむっちりしている。
ジャン・コクトーがこの乙女を「愛すべき生け贄」と評しているのは両者の力関係からもっともだが、じつは乙女が「自分を奪いに来る存在としての薔薇の精」を欲望し、夢想のうちに召喚したともいえるのである。
Embed from Getty Images
『薔薇の精』タマラ・カルサーヴィナ、ヴァツラフ・ニジンスキー
●スキャンダルを呼んだ『牧神の午後』
同じバレエ・リュスでもニジンスキーが振付け踊った『牧神の午後』は、より直接的な表現で一大スキャンダルを巻き起こした。
水遊びをするニンフ達に逃げられた牧神が、残された布を愛撫し、その上に身を横たえる。そのまま自慰をし、絶頂を迎えて終わる。
これは詩人マラルメの『半獣神の午後』からインスピレーションを得てドビュッシーが作曲した『牧神の午後への前奏曲』に振付けたものである。
牧神(パン)は半身半獣で好色・絶倫の象徴である。パンに追いかけられた美しいニンフが純潔を守るため、捕まる直前にみずからの身体を葦に変えてしまったギリシャ神話は有名だ。パンがいつも吹いている葦笛はそれであり、ドビュッシーの曲でも笛(フルート)を中心に構成されている。
つまり初演当時の観客も、「牧神」というだけである程度の予想はついていたわけだが、それでもラストの行為には紳士淑女の皆さんから「汚らわしい!」「いやこれこそが新時代の芸術だ!」と賛否両論が巻き起こった。
ちなみに「パンの雄叫びは聞いたものを混乱状態に陥れる」とされ、パニック(panic)の語源なのだが、みごと混乱を引き起こしたことになる。
とはいえ、両作品とも、現代でも普通に上演される。
コンテンポラリー・ダンスでも、追いかけられるニンフをスポットライトで表したり、美少年を追い回すおっさんに置き換えたりと色々なヴァージョンがある。
●重要性は減るいっぽうだが
とはいえ、現代人の性的嗜好は激変している。
日本でも20代男性の40%は性交渉がないなど、「若者の性欲離れ」が定期的に報道される。
また他人に性的魅力を全く感じない「アセクシュアル」という特性も徐々に認知されてきた。
それは病気だとか、可哀想な存在などではなく、たんにそういう生き方、感じ方がある、というだけのことだ。
フロイト以降、我々は、恋愛感情や性衝動に重きを置きすぎたのかもしれない。
「全てのハリウッド映画は恋愛映画だ」という言葉があるが、オペラもバレエもたいがいそうだ。
これからのアートは、恋愛の呪縛から解放するための作品が増えてくるかもしれない。
そういう意味でも、恋愛の成就よりも自慰での満足を約100年も前に(初演は1912年)描いて見せたニジンスキーは、やはり天才というほかはない。
―― この続きは電子書籍でお楽しみいただけます ――
※この記事ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。