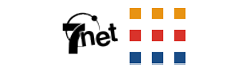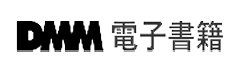“Contemporary Dance Lecture for Ballet Fans”
言葉とダンスーー魅惑の罠からの脱出
●モーリス・ベジャール『バレエ・フォー・ライフ』
今回は、ダンスと言葉の関係 について見てみよう。
そこには陥りやすい罠があり、「新しさ」を出そうと安易に言葉を使うと大失敗することになる。コンテンポラリー・ダンスがいかにその罠を察知して回避してきたか、というスリリングな知恵比べの歴史 をひもといていこう。
一般的にバレエで台詞を使う作品はあまりない。いわゆる「説明」が必要な部分でも、必要ならばマイムや特定のゼスチャーで補完される。
もっともバレエはその誕生からオペラと密接な関係にあるので、歌との相性は悪くはない。2020年2月上演の「アリーナ・コジョカル ドリーム・プロジェクト」でナンシー・オスバルデストンが演じた『エディット』 はピアフのシャンソンに合わせて踊った。自身の振付・出演ソロだが、小品ながらも情緒豊かで見応えのある作品だった。
歌で踊る長編のバレエ作品もある。ローラン・プティ には、『ピンク・フロイド・バレエ』 (1972年初演、2004年に新制作版として牧阿佐美バレヱ団が上演)や、同団の創立45周年に振付けた『デューク・エリントン・バレエ』 (2001年初演、2012年改訂版を上演)などがある。プログレの王者ピンク・フロイドは魔的な魅力が溢れるスケールの大きな曲想であり、またジャズのビッグ・バンドの巨匠デューク・エリントンはオーケストラもあるくらいなので、バレエとの相性はまずまず。とはいえ、ミュージカルでも活躍したプティの才気は堪能できるものの、どうしてもボードヴィル的な寄せ集め感は否めない。
2020年5月に上演予定のモーリス・ベジャール『バレエ・フォー・ライフ』 (1997年)は、2018年に映画『ボヘミアン・ラプソディ』が大ヒットしたイギリスのロックバンド、クイーンの曲(とモーツァルトの曲)で構成されている。かつてベジャールのダンスを最も体現していたジョルジュ・ドンと、クイーンのボーカルのフレディ・マーキュリーは、ともにAIDSで亡くなっている。これはそうした天才達へ捧げられた傑作なのである(ちなみに1991年に坂東玉三郎とともにドン自身が作った舞台のタイトルが『デス・フォー・ライフ』)。
VIDEO
『バレエ・フォー・ライフ』の来日公演では、ぜひ注目してほしいシーンがある。
ではなぜこのシーンにこの映画のパロディが使われるのか。『オペラは踊る』の原題が『A Night at the Opera(オペラ座の夜)』だからである。クイーンのファンならピンとくるだろう。あの名曲『ボヘミアン・ラプソディ』が収録されているアルバムのタイトルが『A Night at the Opera(オペラ座の夜)』と、マルクス映画のタイトルから採られている。アルバム発売時にはマルクス兄弟から「僕らと同様の成功を祈る」という祝電をクイーンが受け取っているのもファンの間では有名な話だ。
……と以前某書に書いたときに、とある大学の先生が「マルクス・ブラザーズの顔は出てこなかった」とクレームをつけてきた。よくよく聞くと、授業で使ったビデオの話をしているらしい。そりゃあハリウッドは俳優の肖像権にうるさいから、そこだけカットしたんじゃないの? と答えた。ビデオだけで文句を言われても困るよ。みなさんは、ぜひ劇場で確かめて欲しい。
「言葉とダンス」
さてあらためて今回のテーマ「言葉とダンス」を考えてみよう。「わかりやすさ」という甘い罠 がある。そこに乗ってしまってはダンスの負けだ。「それ、言葉だけでよくね?」 と思われたら、そのダンスは力不足だということだ。そんな気持ちを圧倒するダンスこそが、深く観客の心を共振させる のである。
しかし頭ではわかっていても、言葉の力が持つ強烈な引力からは、なかなか逃れられるものではない。人間とは「言葉で世界を理解する生き物」だから である。我々は様々な感情、事柄や関係性も、言葉にされると「腑に落ちた」とスッキリする。気持ちいい。この快感は、何千年も文明を積み重ねる原動力のひとつでもある、強烈なものだ。
だがダンスも負けてはいない。本能に直結した強さ を持っている。ダンスに心揺さぶられる感動も、また強烈なものだ。「言葉とダンス」とは、ともに人間の本能と知性が渦巻く戦場 なのである。
●言葉とダンスの関係を整理してみると
ではダンサー達は、言葉という諸刃の剣と、いかに対峙してきたかを見てみよう。
〈言葉の使い方の分類〉
A:歌を使う B:言葉を使う a:第三者や音響で流す b:本人が発する
A の「歌」に関しては、
〈Aa:他人の歌で踊る〉
〈Ab:本人が歌う〉
―― この続きは電子書籍でお楽しみいただけます ――
※この記事ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。