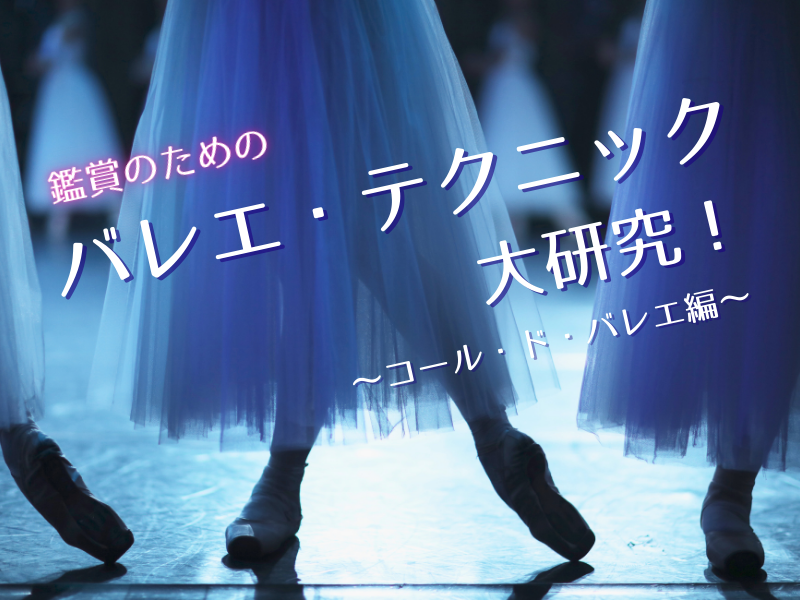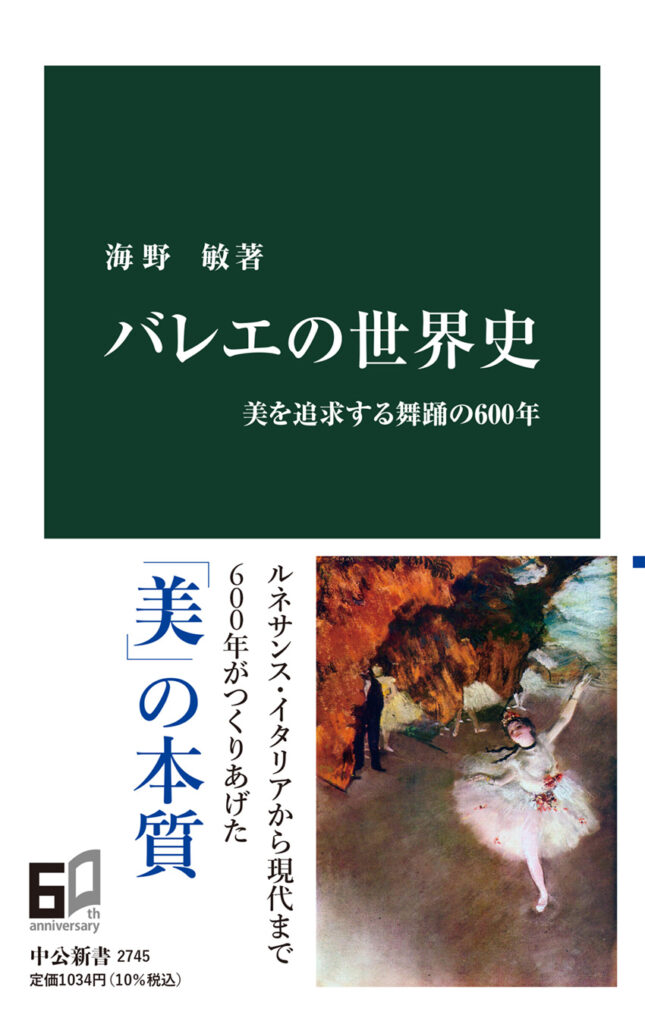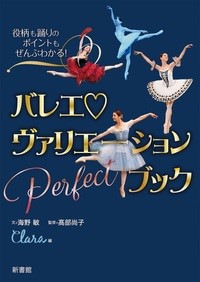文/海野 敏(舞踊評論家)
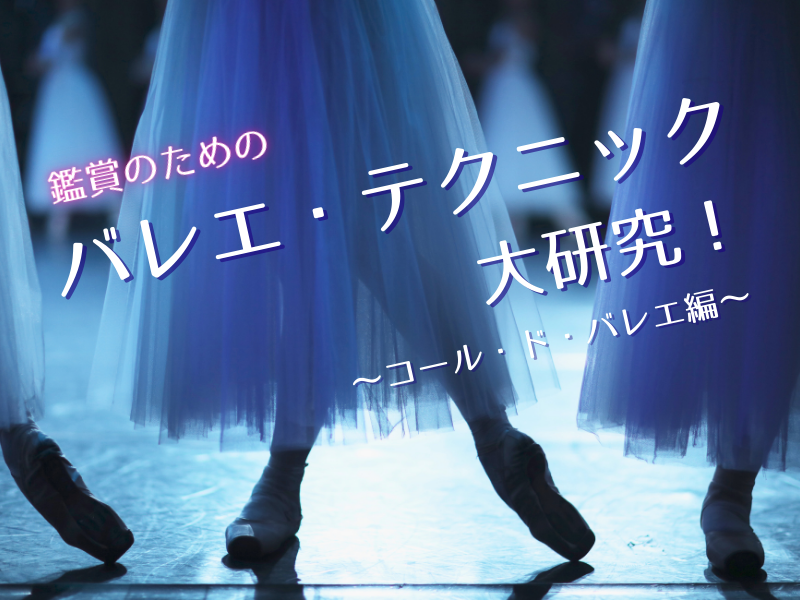
第68回 コの字とロの字
■四角形の3辺と4辺に並ぶ
群舞のフォーメーションとして、横6列×縦4列=24人、横8列×縦5列=40人など四角形の並び方は、第64回で取り上げました。いっぽう今回取り上げるのは、四角形の辺にのみ並ぶフォーメーションです。
コの字のフォーメーションは、舞台両袖の縦1列ずつと舞台奥の横1列がつながって、左へ90度倒した「コ」のかたちを作る並び方です。漢字の「冂」(けい)の字のフォーメーションと書いたほうが、かたちは伝わりますね(注1)。これは、舞台中央で踊る主役ダンサーまたはソリストを、コール・ド・バレエが3方向から取り囲む配置として、古典全幕作品では珍しくありません。主役・ソリストなしで群舞がコの字になって踊ることもあります。
いっぽう、ロの字のフォーメーションは、コの字のフォーメーションに舞台手前の横1列が加わり、四角形の4辺にダンサーが並んでカタカナの「ロ」の字、あるいは漢字の「口」(くち)の字を作る配置です。この場合も舞台中央で主役またはソリストが踊ることはありますが、舞台手前の横1列が観客の視界を妨げるので、あまり長く続くことはありません。後ほど紹介するように、コール・ド・バレエのみの踊りで、フォーメーションを変えてゆく途中でロの字になることもあります。
では、古典全幕作品に登場するコの字とロの字の群舞を紹介しましょう。
■『眠れる森の美女』のコの字
『眠れる森の美女』第2幕、デジレ王子とオーロラ姫のアダージオで、森の精の群舞が2重の円を作る振付は「第66回 円に並ぶ(1)」で紹介しました。その少し後にコの字のフォーメーションが登場します。
アダージオの中盤で、リラの精、オーロラ姫、デジレ王子の3人がいったん退場すると、音楽のテンポが上がります。するとコール・ド・バレエは四角に並び、全員で脚を空中で「後ろ→前→後ろ」へ上げる小さな跳躍を9回行います。パの名前で言いますと、「カブリオール・デリエール→カブリオール・ドゥヴァン→カブリオール・デリエール」×3回です(「第18回 カブリオール」参照)。その後、フォーメーションをコ(冂)の字に変えて、再び同じ振付で9回跳躍します。森の精たちが一斉に繰り返し跳びはねる振付は、いかにも妖精らしい軽やかな様子を伝えて、群舞の見どころになっています。
なお、ここではフォーメーションの変化を「四角形→コの字」と説明しましたが、バレエ団によっては「コの字→四角形」の順番です。また、コの字になったときに、奥の横辺が2列になるバターンもあります(注2)。
- ★動画でチェック!★
- ローマ国立歌劇場『眠れる森の美女』第2幕より。1時間29分50秒から一連のシーンを観ることができます。
■『白鳥の湖』のコの字とロの字
『白鳥の湖』第2幕では、オデットのヴァリエーションの後、コーダの冒頭でコの字になるのが定番の振付です。オデットがヴァリエーションを踊っている間は、白鳥たちは左右の袖の前で縦1列になり、両手を前で軽く交差させてポーズしています。ヴァリエーションが終わってオデットがいったん袖へ退場すると、左右の縦1列に加えて正面奥に横1列をつくり、全体でコ(冂)の字となります。
コーダの音楽が始まると、奥の横1列は小さな跳躍を繰り返して前方へ進み、群舞は一瞬「H」の字になった後、同時に再び奥に横列をつくるので、全体でロ(口)の字になります。続いて別のダンサーが奥に横1列をつくってから前方へ進むので、全体は再びHの字になり、さらに別のダンサーが奥に横1列をつくって再びロの字になります。文字で隊形の変化を表現しますと「冂→H→口→H→口→・・・」となります。
バレエ団によって細かい振付は違いますが、コーダの冒頭で「冂」「H」「口」の3つのかたちが現れる点は、だいたい共通していると思います。短いシーンですが、群舞の流れるようなフォーメーション・チェンジは見逃せません。振付によっては、漢字の「凵」(かん)の字が現れることもあります(注3)。
- ★動画でチェック!★
- オランダ国立バレエ『白鳥の湖』第2幕より。映像の冒頭からコーダのフォーメーションを観ることができます。
■『パキータ』のコの字
『パキータ』第3幕の「グラン・パ・クラシック」は、本連載「コール・ド・バレエ編」ではすでに第60、63回で取り上げましたが、コの字のフォーメーションも現れます。アントレの終盤、コール・ド・バレエがコ(冂)の字となってポーズし、主役パキータが3方向を囲まれて16小節のソロを踊る場面です。
続けて主役と群舞がユニゾンで踊るときも、フォーメーションはコの字のままです。全員がそろってカブリオール・ドゥヴァンを「右前→左前→右前」と繰り返すのですが、もともとカブリオールが3拍子の跳躍(「1、2、3」のリズム)なので、ミンクス作曲のノリのよい3拍子の音楽にぴったりな、爽快感のある振付になっています。ただし、バレエ団によっては正面奥の横1列が少し前へ出て、コの字でなくHの字のフォーメーションになることも少なくありません。
- ★動画でチェック!★
- パリ・オペラ座バレエの『パキータ』より第3幕。「グラン・パ・クラシック」のアントレ終盤は、映像の冒頭から観ることができます。
(注1)「冂」は2画の漢字で、「円、内、冊、同、再」などの部首としては「けいがまえ」「えんがまえ」「どうがまえ」などと呼ばれています。
(注2)例えば、英国ロイヤル・バレエの振付では「四角形→コの字」ですが、コの字になったときに奥の横辺が2列になります。パリ・オペラ座バレエでは「コの字→四角形」で、コの字になったときは3辺とも1列です。
(注3)「凵」は2画の漢字で、「凶、出、凹、凸」などの部首としては「かんがまえ」「かんにょう」「うけばこ」などと呼ばれています。
(発行日:2025年3月25日)
筆者による講座の紹介
2025年5~6月、早稲田大学エクステンションセンターの春季講座で「世界史のなかのバレエ~美を追求する舞踊の600年」という講座を行います。全6回で金曜の午前中、早稲田キャンパスで行います。詳細は同センターのウェブページをご覧下さい。
https://www.wuext.waseda.jp/course/detail/65202/
なお、同センターでは3月31日まで「春の入会金無料キャンペーン」を実施しており、入会金(8,000円)が無料になります。会員資格は4年間有効で、同センターが開講している100を超える講座を会員料金で受講できるほか、早稲田大学中央図書館が利用できるなどの特典があります。
次回は…
第69回は、十字、X字など、その他の形に並ぶコール・ド・バレエを取り上げる予定です。発行予定日は2025年4月25日です。
- 【鑑賞のためのバレエ・テクニック大研究!-総目次】
- http://bibliognost.net/umino/ballet_tech_contents.html
\NEWS!/
本連載の著者・海野敏さんによる書籍が発売されました! ルネサンス期イタリアから21世紀まで、バレエという舞台芸術の600年を通覧する内容です。
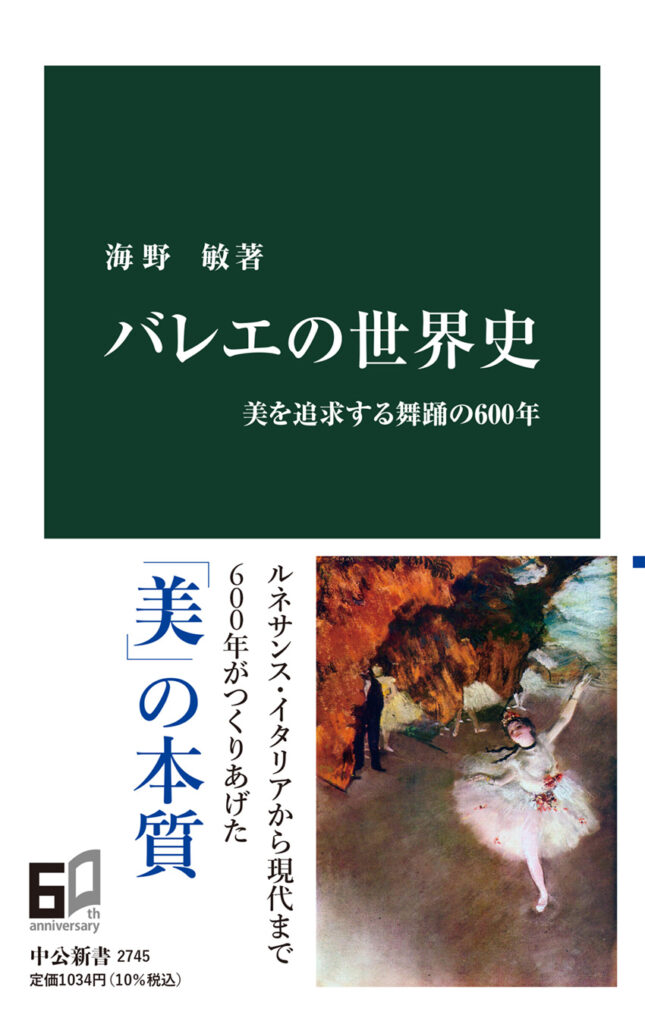
『バレエの世界史:美を追求する舞踊の600年』
海野敏=著
中央公論新社 2023年3月(中公新書2745) 940円(税別)
★詳細はこちら
*
【こちらも好評発売中!】
オーロラ、キトリ、サタネラ、グラン・パ・クラシック、人形の精……等々、コンクールや発表会で人気の 30 のヴァリエーションを収録。それぞれの振付のポイントを解説しています。バレエを習う人にも、鑑賞する人にも役立つ内容です。ぜひチェックを!
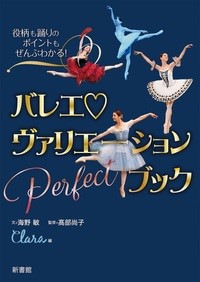
『役柄も踊りのポイントもぜんぶわかる! バレエ♡ヴァリエーションPerfectブック』
海野敏=文 髙部尚子=監修
新書館 2022年3月
★詳細はこちら