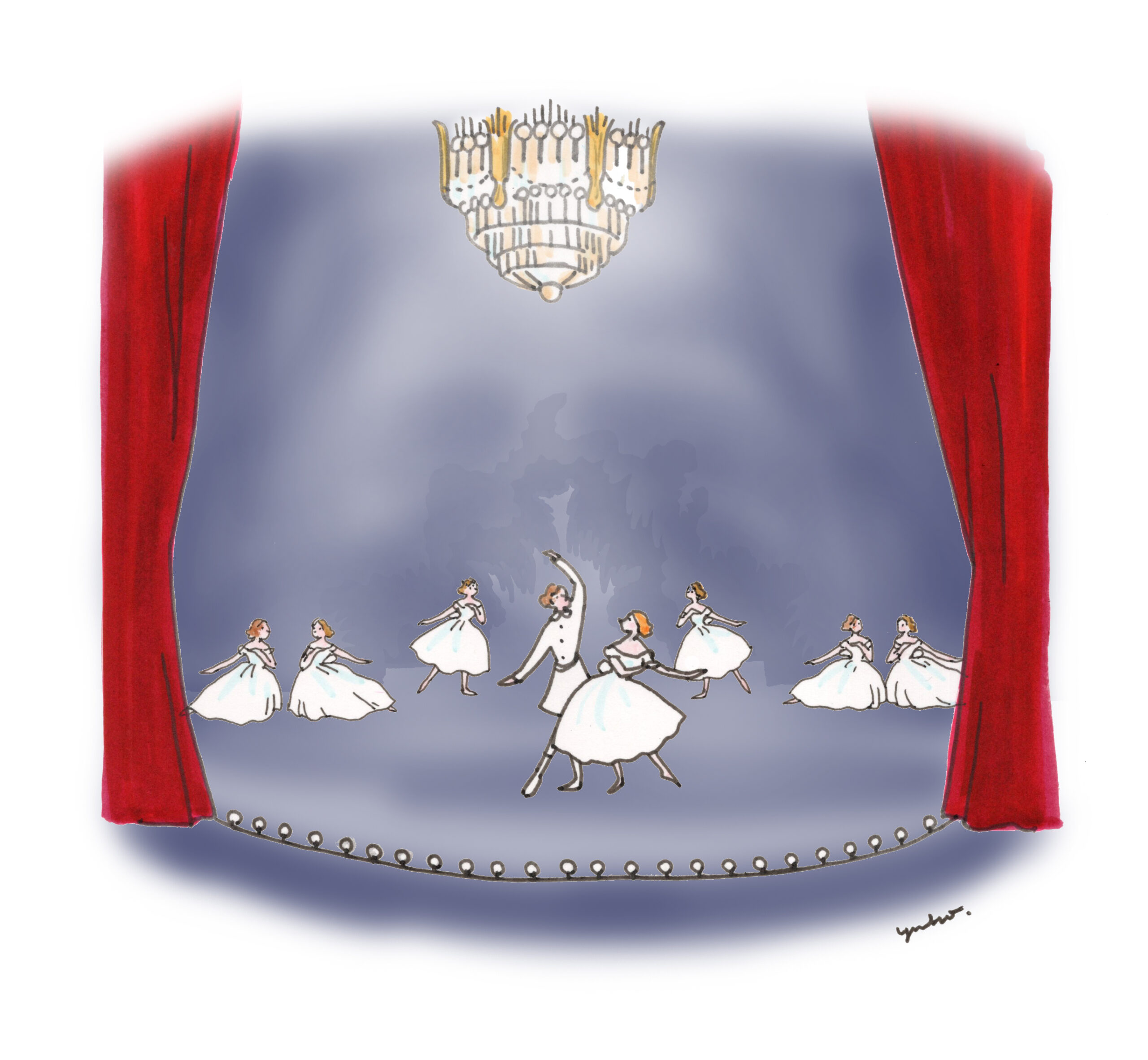パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!
1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。
「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」
そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。
- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」
- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」
- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…
……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。
ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!
イラスト:丸山裕子
🇫🇷
「総合芸術」と言われるバレエは、じつにさまざまな構成要素から成立しています。その一つが照明です。時にはドラマティックに、時には幻想的に舞台を彩る照明の演出は、視覚面での強い印象を残します。この連載が舞台としている19世紀のパリ・オペラ座、とくにル・ペルティエ劇場は、当時のヨーロッパでは最大級、かつ最新の設備を持つ歌劇場でした。《ラ・シルフィード》や《ジゼル》などのロマンティック・バレエの上演では、ガス燈の青白い炎が、月夜の森をふわふわと漂う妖精や幽霊の演出に、良い効果を発揮したことが知られています。
とはいえ、電化されていない19世紀の劇場では、現代とは異なるいろいろな制約があっただろうことは想像に難くありません。そもそも19世紀のパリ・オペラ座では、どのような照明機材が使用されていたのでしょうか? 今回は、第二帝政下の1858年に作成された、照明総責任者の契約書をもとに、当時の劇場内の照明事情についてご紹介します。
上演中も明かりは点けっぱなし! 19世紀の客席内
資料を読み解いていく前に、まずは19世紀のオペラ座の照明について、ちょっとした前提を押さえておきましょう。それは、当時の上演中の客席部分は暗くなかった、ということです。……って、(現代でいう)客電をつけた状態で公演をしていたの? まさしくその通りで、19世紀のオペラ座では、そもそも客席部分の明かりを上演中に消す、という習慣がありませんでした。
もっとも、後でご説明するように、19世紀のほとんどの時期のパリでは、まだ電化した照明が普及していません。ですので、「消さない照明」といっても、現在のコンサートホールや劇場のように、煌々と明かりが灯っているわけではないのですが、ある程度の明るさがある中で観劇するのは、当時の人々にとっては普通のことでした。客電が落ちることで公演の始まりを実感する私たち現代の観客には、ちょっと想像し難いですが、客席部分のこのような状況を踏まえて、舞台上の照明による演出効果を考える必要があるでしょう。
オペラ座で上演中の客席の明かりに対して改革が行われたのは、20世紀半ばになってからです。その功労者は、1930年からオペラ座バレエの監督となったセルジュ・リファール(1905-1986)。彼は、バレエ公演の客席内に照明が灯り、ガヤガヤと騒がしい客席に我慢がならず、上演中の客席部分の照明は消すように指示したのでした。上演中は集中して舞台とダンサーを見て欲しい……というのが、リファールの望みだったのですね。

資料について
今回取り上げる資料は、「帝室オペラ座の照明請負契約に関する義務書Cahier des Charges de l’entreprise de l’éclairage du Théâtre impérial de l’Opéra」と題されたもの。1858年当時にオペラ座総裁を務めていたアルフォンス・ロワイエと、オペラ座で照明の総責任者を務めていたエミール・ムロンとのあいだで交わされた契約書です。
「照明の総責任者」と聞くと、ムロンは上演作品の演出としての照明を統括していたのか、と思われるかもしれませんが、彼の責任が及ぶ範囲はもっと広く、建物としての劇場全体の照明にも関わっていました。つまり、「オペラ座のすべての部門とすべての建物の照明、通常または臨時の公演、全体的または部分的なリハーサル、舞台美術のテストやオーディション、休日や昼夜の監視、消防隊や警察の見回りや訪問のためのすべての照明」(第1条)に関する責任者がムロンだったのです。そのため、この契約書では、使用する照明器具に始まり、その設置場所、メンテナンスの方法、照明システムを稼働させるために必要な人員についてなど、ありとあらゆる事項が36の条項として事細かに記されています。
ところで、パリの公共の場で、初めて電気による照明が使われたのは1844年のことでした。ただし、この時点ではまだ実験段階で、電気照明による街灯の本格的な運用は、1878年5月31日夜9時からのことなのだそうです(しかも、パレ・ガルニエ前のオペラ大通りでの話です)。それ以前にパリの公共の場で主に用いられていた照明は、世紀の前半はオイルランプ、中頃から後半にかけてはガスランプが主流でした。1831年にパリの街中で使用されていたオイルランプの数は1万2941個でしたが、1848年には2608個に数を減らします。いっぽう、ガスランプの数は、1831年に69個だったのが1848年には8600個に、1852年には1万3733個に増加しており、ガスランプが急速に普及していった様子が伺えます。
ろうそく? オイル? それともガス?
屋外ではガスランプが主流になっていた1858年には、オペラ座でもガスランプが積極的に導入されていたようで、資料においてもガスランプに対する言及が頻繁に見つかります。ただし、契約書の第2条に、オペラ座の固定の照明として「ガス、オイル、ろうそくによる固定の器具」とあるように、場所や機会に応じて多様な使い分けがされていました。
オイルランプは出演者の楽屋や、客席内の廊下や階段になどに設置されており、「完全に精製された高品質の菜種油のみ」(第11条)が原料として使われていました。使用されるオイルランプの器具は、すべてサンプルが劇場の管理部に預けられており、サンプル以外の器具を使用することは禁止されていたようです。ろうそくよりは光量のあるオイルランプですが、煤や火の粉が多く出たり、熱くなった油が頭上から落ちてきたりすることもあったそうで、なかなかデンジャラスな照明だったようです。
ろうそくは、オーケストラの演奏者の譜面台や、特定の作品の上演に必要な場合(当時のオペラ座を代表するオペラ作品、《ユグノー教徒》などが挙がっています)があったようです。また、皇帝ナポレオン3世の専用席には、公演ごとに22本の新しいろうそくが、オペラ座総裁であるロワイエのボックス席も、2本のろうそくを置くことが義務付けられていました。雰囲気のあるろうそくの光ですが光量は弱く、オイルランプの登場より昔の舞台では、演者の顔の見分けがつかないうえ、火が衣裳に燃え移る危険もありました。
建物の照明に関わる部分の主流はガスランプで、ムロンは「各ガス灯と口径から得られる最大光度と同等以上の光を提供」しなければいけませんでした。また、作品の上演に関わる照明にもガスランプが使用され、上演中に照明を操作する作業員は、最低でもムロン以外に11人が必要、と記されています。彼らは「ガスの取り扱いや操作に精通し、そのうち少なくとも3人は、配管や装置に関わるすべての修理を、迅速かつ完璧に実行できる状態でなければ」ならず(第22条)、ムロンが人員を手配し、オペラ座側に報告することになっていました。ガスの購入はパリ市内のガス会社とムロンが契約し、上演前に厳重なチェックと管理をした上で、明かりを点灯することになっていました。
さまざまな種類の明かりの管理と、それらに適した細かなメンテナンスは、ムロンたちにとってなかなかの重労働だったはずです。しかし、上演中や劇場設備からの出火が原因で、何度も火災事故を経験しているオペラ座にとって、明かりの管理は極めて重要な事項の一つでした。また、照明器具の明るさは、舞台上のスペースを広く使うことや、ダンサーの配置や動きの可能性を左右します。それはつまり、踊り手の身体や振付をじっくり見る/見られる時代のバレエに、大きな影響をもたらした要素とも言えるのです。
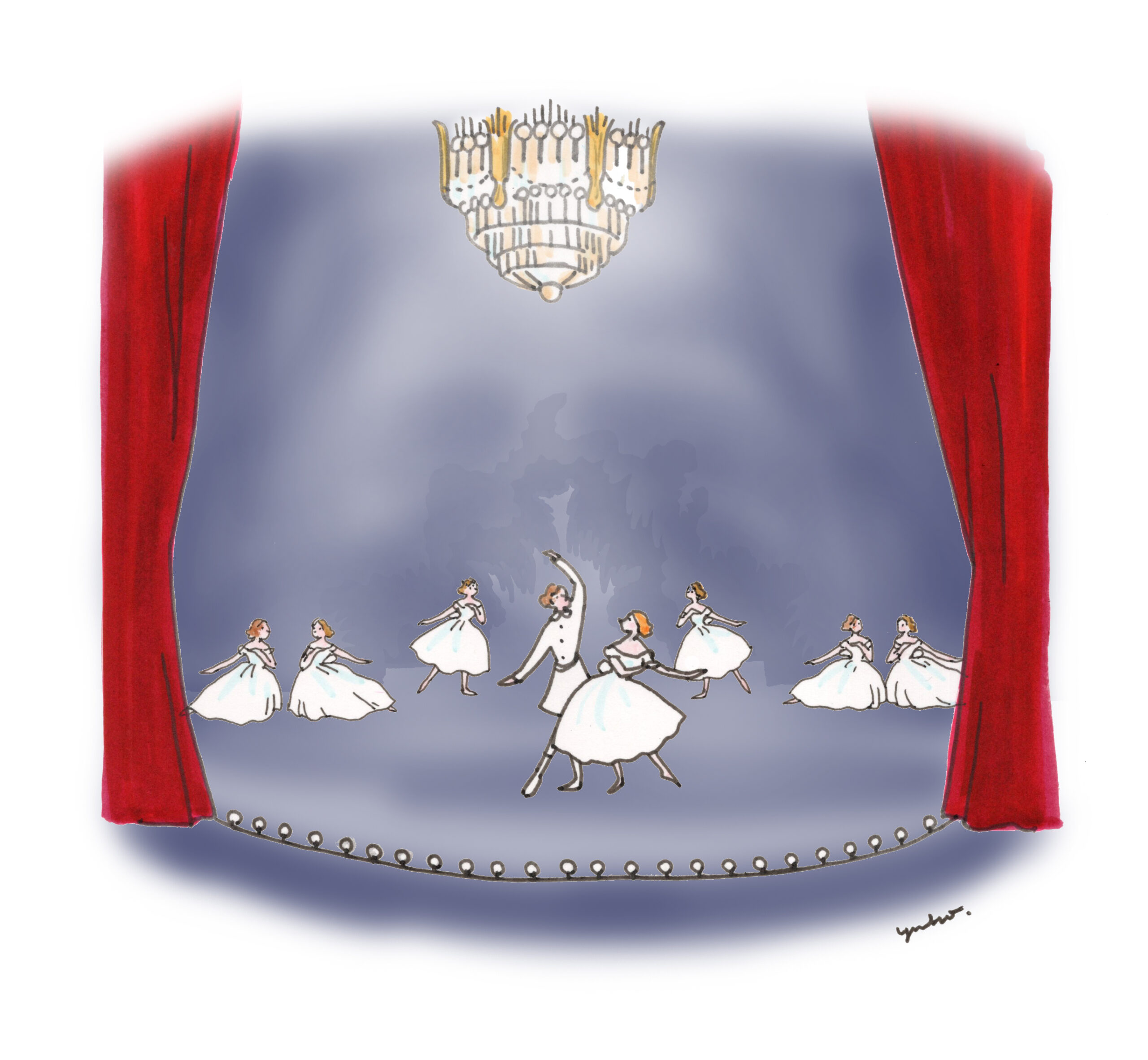
参考資料
Archives Nationales. AJ/13/443. Cahier des Charges de l’entreprise de l’éclairage du Théâtre impérial de l’Opéra. 1858 Août 5.
高橋信良、2021。「19世紀後半のパリ演劇事情:照明の発達と演出家の登場」、『千葉大学国際教養学研究』第5巻、千葉大学国際教養学部、p.55-70.
Mémoire de l’Électricité, du Gaz et de l’Éclairage public, « Histoire de l’éclairage public à Paris » https://mege-paris.org/2021/02/19/histoire-de-leclairage-public-a-paris/ (2024年9月12日最終閲覧)
【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!
「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。
●永井玉藻 著
●四六判・並製・224頁
●定価2,420円(本体2,200円+税10%)
●音楽之友社
●詳しい内容はこちら
●Amazonでの予約・購入はこちら