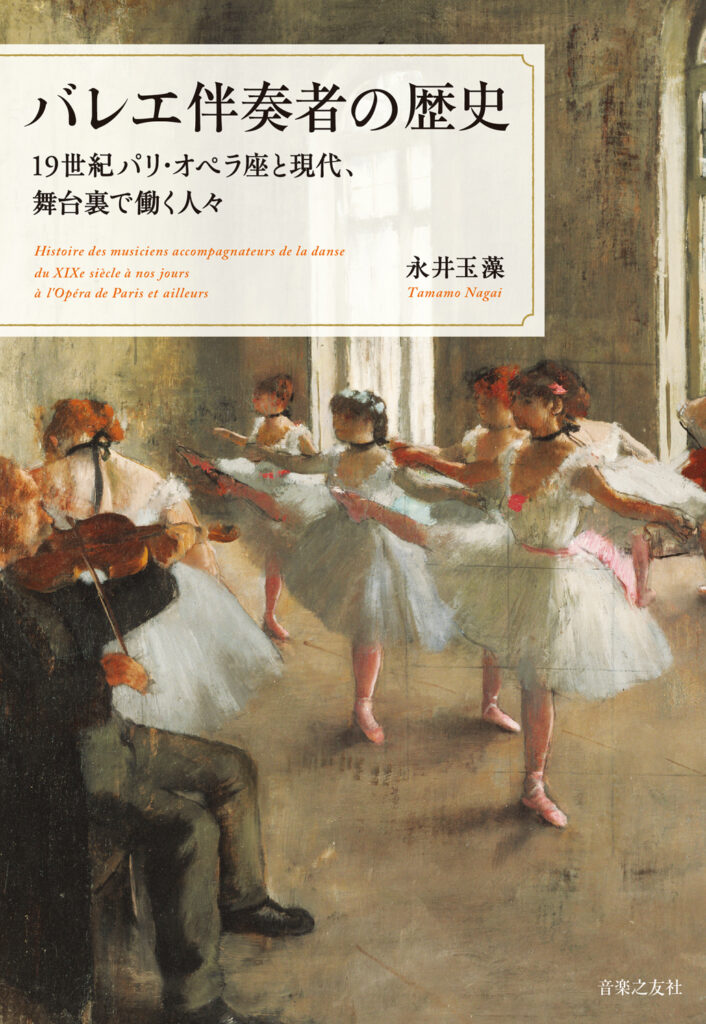パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!
1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。
「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」
そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。
- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」
- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」
- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…
……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。
ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!
イラスト:丸山裕子
🇫🇷
19世紀のパリ・オペラ座バレエは、スター級の女性ダンサーが次々に脚光を浴びた華やかな舞台です。その中で、彗星のように登場し、短い生涯を駆け抜けた一人のダンサーがいました。彼女の名はジュゼッピーナ・ボザッキ。わずか16歳でオペラ座バレエの頂点に立ち、観客を魅了した早熟の天才です。
彼女の最も輝かしい功績は、今日でも世界中で愛されるバレエ《コッペリア》の初代スワニルダ役を演じたことです。この作品が初演された直後から数年間、フランス社会は困難と混乱の時期を迎えるのですが、この時期は同時に、バレエ史上でも一つのターニングポイントにあたります。では、そんな時期にオペラ座の舞台で一瞬の輝きを放ったボザッキは、どのようなダンサーだったのでしょうか? 今回は、ボザッキの短い生涯を追いながら、《コッペリア》と、その背景となる激動の時代をご紹介します。

ジュゼッピーナ・ボザッキ Giuseppina Bozzacchi(1853-1870)写真は「コッペリア」スワニルダ役の時のもの
喜劇《コッペリア》の誕生
明るく楽しいハッピーエンドのバレエとして知られる《コッペリア》ですが、その原作は、幻想的で少し不気味な物語で知られるドイツの作家、E.T.A.ホフマンの短編小説である『砂男』です。主人公の青年(バレエでのフランツに当たります)が自動人形に恋をする、という流れは同じなのですが、原作での青年は最終的に正気を失い、投身自殺するという結末に……。このちょっとおどろおどろしい物語を喜劇のバレエへと作り変えたのが、振付家のアルチュール・サン=レオン(1836-1891)と、作曲家のレオ・ドリーブ(1836-1891)でした。
では、バレエ版のあらすじをおさらいしておきましょう。《コッペリア》の舞台は、ポーランドのガリツィア地方ののどかな村。村一番の美少女スワニルダは、恋人のフランツが、広場に面した家の窓辺に座る美しい娘に心を奪われているのを見て、やきもきしています。ところが、コッペリアという名のこの娘は、じつは人間ではなく、変わり者のコッペリウス博士が作った自動人形だったのでした。博士の留守中に家に忍び込んだフランツは、帰宅した博士に魂を狙われます。ところが、コッペリアに扮したスワニルダの機転によって、二人は無事に博士の家を脱出、最終幕で無事に結婚式を迎えます。原作に見られる青年の狂気は、バレエではユーモアに置き換えられ、作品全体が陽気で和やかな雰囲気に。また、ドリーブが取り入れた、マズルカやチャルダッシュといったスラブ地方由来の民族舞踊曲も、地域色を与えるだけでなく、生き生きとしたリズムで作品を彩っています。

イタリアの新星、現る
《コッペリア》の制作に先立つ数年前、オペラ座バレエで注目を集めていた女性ダンサーは、ドイツ出身のアデル・グランツォフでした。ロシアで評判を得ていた彼女は、1865年に初演されたサン=レオンの作品《フィアメッタ》で主演し、それ以来、振付家のお気に入りのダンサーとなります。パリ・オペラ座でも1866年から舞台に立っていたグランツォフに、サン=レオンは自身の作品で主役を踊らせたい、と考え、《コッペリア》の制作に着手します。ところが、ロシアとフランスを行き来しながら仕事をこなしていたサン=レオンはなかなか振付を進められず、あっというまに2年半が経過。さらに間の悪いことに、グランツォフは病に倒れてしまったのです。
そこで白羽の矢が立ったのが、伝説のバレエ教師マダム・ドミニク(本連載の第32回を参照)が指導していたボザッキでした。1853年にミラノで生まれた彼女は、オペラ座で踊ったこともあるイタリア人ダンサー、アミーナ・ボチェッティの指導を受けたのちに渡仏し、マダム・ドミニクのもとで稽古にはげんでいたのです。恋にやきもきしながらも、機知に富んだ行動力で困難を乗り越えるスワニルダの人物造形が、当時15歳のボザッキにフィットしたのか、1869年5月末には、《コッペリア》の主役を彼女が踊ることが新聞で告知されました。ドリーブののんびりした仕事ぶりにサン=レオンがブチ切れながらも(本連載の第31回を参照)、作品は1870年5月25日に初演を迎えます。初演に対する新聞評の大部分は、新星ダンサーのボザッキに関するものでした。
作品は8月の末までに18回上演され、順調な成功を収めていました。しかし、ボザッキの輝かしい日々には、暗い影が徐々に忍び寄っていました。じつはこの年の7月、普仏戦争の勃発によってフランス第二帝政は崩壊し、オペラ座も閉鎖を余儀なくされたのです。
フランスからロシアへ バレエの地殻変動
《コッペリア》の初演からわずか2ヵ月後の1870年7月19日、フランスはプロイセン(後のドイツ帝国の中核)に宣戦布告し、普仏戦争が勃発します。フランス軍は連敗を重ね、9月には皇帝ナポレオン3世が捕虜となり、パリはプロイセン軍によって完全に包囲されました。オペラ座の閉鎖によってバレエ公演はストップし、パリ市内でも生活は厳しくなっていきます。そのさなかの1870年11月23日、ボザッキは天然痘に感染し、17歳の誕生日にひっそりと息を引き取りました。天然痘は高熱や全身に発疹が出る感染症であり、特効薬もなかったため、かつては発症すると死に至る病気でした。また、若きダンサーの生活環境も、良いものだったとはいえなさそうです。実際、ボザッキの親族と思われる人物は、当時のオペラ座監督、エミール・ペランに宛てて、借金の申し入れをする手紙を複数回送っていました。彼女の死は、《コッペリア》の初演からわずか半年後のこと。そして、時を同じくして、バレエの中心地もまた大きな転換期を迎えます。
普仏戦争の敗北後も、パリの混乱は続きました。1871年には労働者階級による自治政府「パリ・コミューン」が樹立されますが、政府軍によって鎮圧され、市街戦で多くの命が失われました。さらに1873年、当時のオペラ座の本拠地であるペルティエ通りの劇場が、原因不明の火災で焼失。芸術面でも、パリのバレエはロマンティック・バレエの時代から続く「妖精や悪魔が登場する幻想的な物語」によってマンネリ化し、男性ダンサーにとっては活躍の場が少なくなっていました。いっぽう、その頃ロシアでは、バレエが黄金時代を迎えようとしていました。19世紀半ばから《ラ・シルフィード》や《ジゼル》などの演目をあまり時間差なく上演し、フランスで人気のダンサーたちが踊りに来ていたロシアでは、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場を中心に、着々と「バレエの完成」への道が敷かれていたのです。さらに、サン=レオンやマリウス・プティパといった有能な振付家がロシアで活動したことで、人材も、革新的なアイデアも、観客の熱狂も、パリからサンクトペテルブルクへと移っていきました。
では、没落の道を歩み始めていたオペラ座が生んだ《コッペリア》は、フランス・バレエの最後の輝きなのでしょうか? じつはこの作品、来たるべき「チャイコフスキーの三大バレエ」の時代を予見するような、重要な要素を持っています。
物語の大筋が解決した後、第3幕はスワニルダとフランツの結婚を祝う祝祭の場面となります。ここでは「時」「曙」「祈り」「仕事」などをテーマにした踊りが、次々と披露されます。「ディヴェルティスマン」と呼ばれるこうしたセクションは、物語の筋とは直接関係なく、純粋に踊りそのものを見せるための場面です。この「クライマックスや作品の後半に壮大なディヴェルティスマンを置く」という構成は、《眠れる森の美女》(1890年)や《くるみ割り人形》といった、バレエの代名詞とも言える作品の形式そのもの。その点で、《コッペリア》は、ロマンティック・バレエの時代の終わりを告げ、クラシック・バレエの時代の幕開けを橋渡しする、歴史的な役割を担った作品だったと考えられています。
ジュゼッピーナ・ボザッキの生涯は、あまりにも短く、悲劇的でした。しかし、彼女が踊った《コッペリア》は、さまざまな振付家による改訂演出で、今日でも世界中で愛される作品の一つとなっています。

参考資料
Archives Nationales. AJ/13/477, Lettre de G. Bozzachi à Émile Perrin.
Girard, Pauline. 2018. Léo Delibes Itinéraire d’un musicien des Bouffes-Parisiens à l’Institut. Paris, Edition Vrin.
【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!
「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」
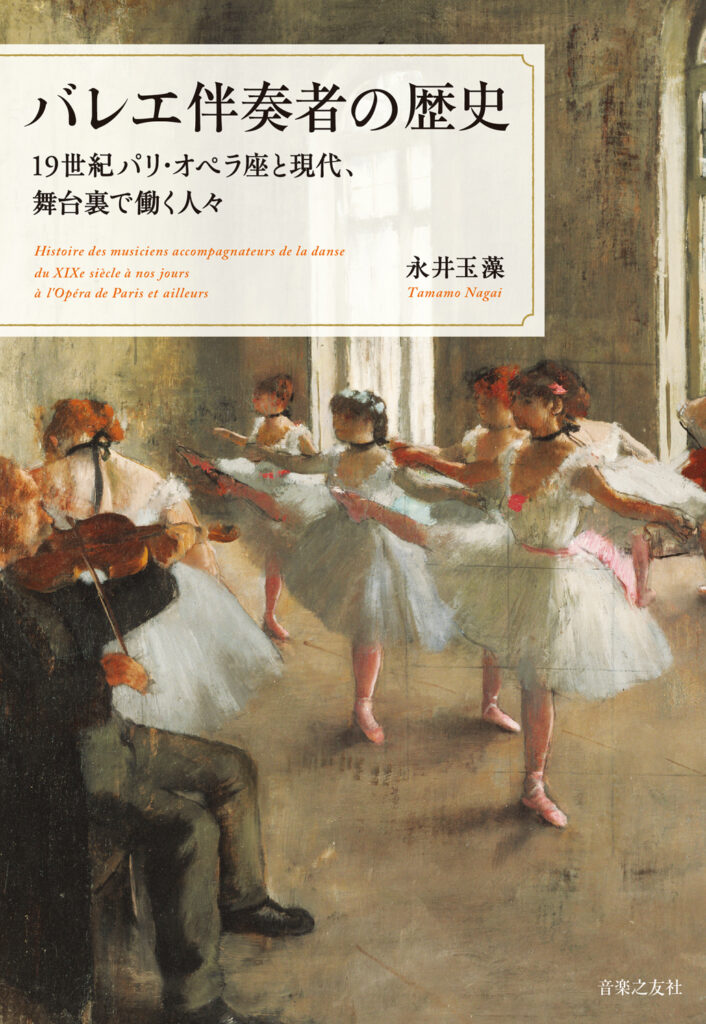
バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。
●永井玉藻 著
●四六判・並製・224頁
●定価2,420円(本体2,200円+税10%)
●音楽之友社
●詳しい内容はこちら
●Amazonでの予約・購入はこちら