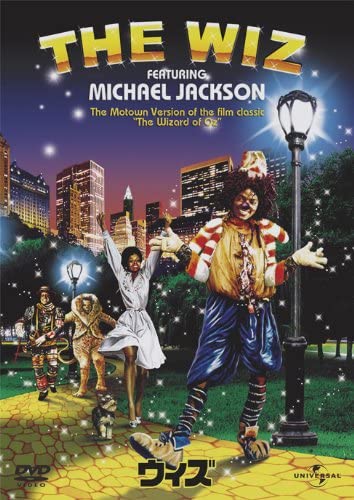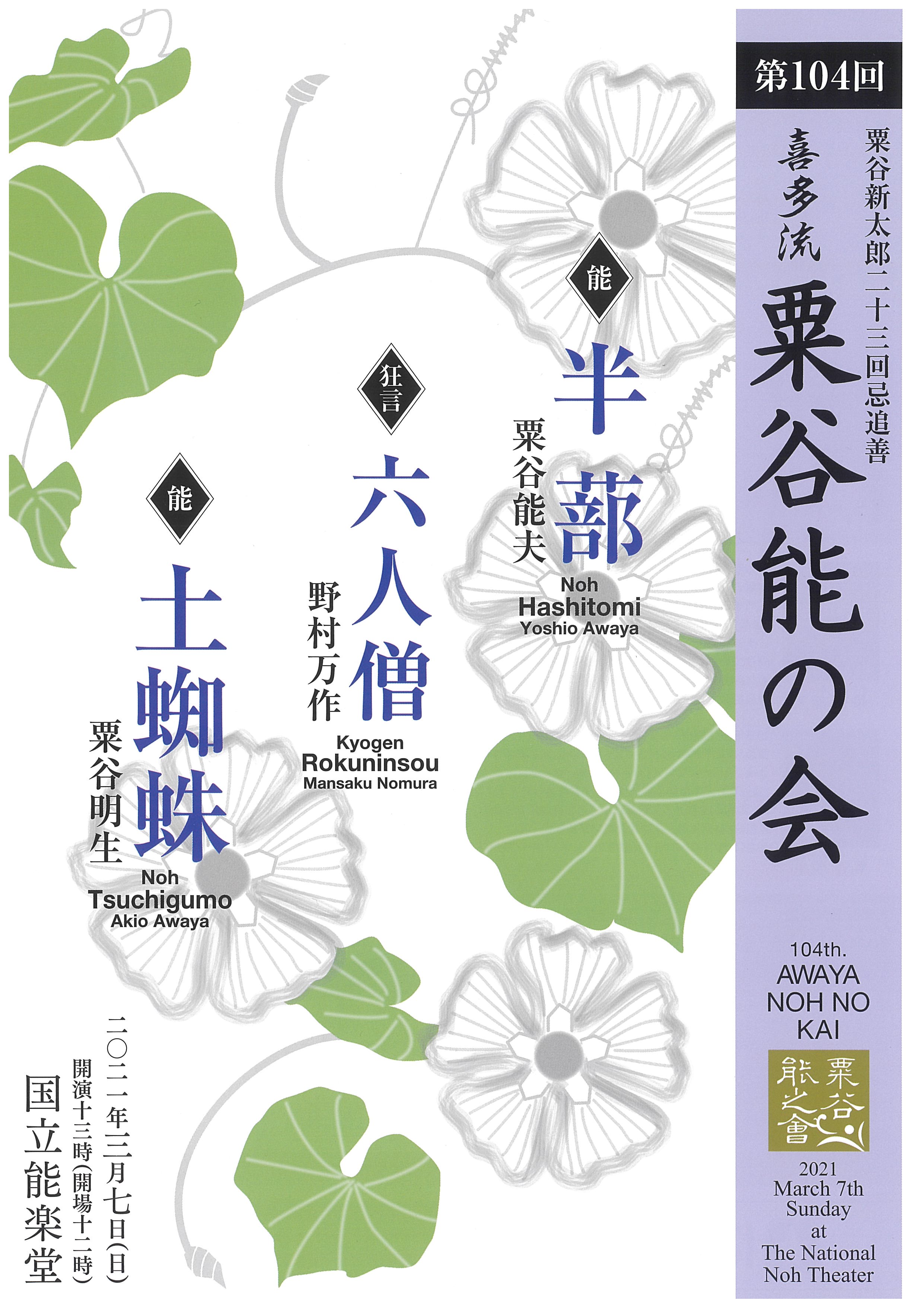ダンス、バレエ、オペラ、演劇、文楽、歌舞伎、ミュージカル……〈舞台芸術〉のあらゆるジャンルを縦横無尽に鑑賞し、独自の切り口で世界を見わたす舞踊・演劇ライターの高橋彩子さん。
「いろんなジャンルを横断的に観ると、舞台はもっとおもしろい!」ーー毎回ひとつのキーワード(テーマ)をピックアップして、それぞれの舞台芸術の特徴やおもしろさ、共通するところや異なるところに光を当てていただきます。
***
悪の魅力〈後編〉
明快に悪を貫くキャラクターたちを中心にご紹介した前編。しかし舞台芸術における悪者像の中には、複雑な背景を持ち、変化するものもある。後編では、こうした観点から、幾つかの作品を見ていきたい。
劇の中で悪から善へ〜人形浄瑠璃&歌舞伎『義経千本桜』権太
イヤな人だと思っていたらイイ人だった、というふうに印象が変わることは日常生活でもあるが、その極端な例(?)が、人形浄瑠璃(文楽)や歌舞伎での「もどり」。有名なのが『義経千本桜』すしやの段の権太だ。
| 釣瓶すし屋の弥左衛門は、平家が源氏に敗れた後、かつて恩を受けた平重盛の息子である平維盛を匿っている。弥左衛門の留守中、不品行から勘当されている息子の権太がやって来て母に金をせびるが、ほどなく弥左衛門が帰ってきたため、もらった金をすし桶に隠す。ところが弥左衛門も、維盛を追う梶原平三景時に維盛の首と偽って渡すために持ち帰った死人の首をすし桶に隠す。権太は帰る際、首が入っているほうのすし桶を持ち帰ってしまう。いよい景時の詮議が迫り、弥左衛門が首入り(と信じる)のすし桶を景時側に渡そうとすると、権太が再び現れ、維盛の首に加えて維盛の妻子、若葉の内侍と六代君も景時に引き渡し、褒美をもらう。弥左衛門は激怒し息子を刀で刺すが、虫の息の権太は、渡した首こそ弥左衛門が持ち帰った首であり、維盛の妻子として引き渡したのは自身の妻子であると明かし、維盛一家や両親らに見守られながら死んでいくのだった。 |
強請(ゆす)り騙(かた)りの悪行三昧から「いがみの権太」と呼ばれるならず者の権太が、誤って持ち帰った偽首を見て事態を察し、妻子すら差し出すというどんでん返し。息子を勘当してその家族にも会っていなかったため、弥左衛門らも、引き渡されたのが権太の妻子であることに気づかなかったのだ。一般に、権太はあくまで小悪党として演じられ、最後の最後に善人としての顔が明かされることになっている。やっていることはどうしようもないがどこか愛嬌のある権太が、打って変わって悲劇の中で死んでいくラストはあまりにもドラマティック。
なお、「もどり」としては他に『摂州合邦辻』玉手などが有名だ。
揺らぐ善悪〜人形浄瑠璃『冥途の飛脚』歌舞伎『恋飛脚大和往来』八右衛門
もとを正すと一つの物語なのに、作品によって善人になったり悪人になったりする人物もいる。近松門左衛門が書いた人形浄瑠璃の名作『冥途の飛脚』の八右衛門もその一人だ。
| 大和国新口村から飛脚屋・亀屋の養子に入った忠兵衛は、越後屋の遊女・梅川と恋仲になるが、彼女が別の男に身請けされそうになり、なんとか自分のほうで請け出したいと考える。そのためにまず必要な手付けの金50両として、忠兵衛は、友人・八右衛門の店である丹波屋に届ける為替金を使い込んでしまう。本来なら大罪だが、事情を知った八右衛門は支払いを待ってやることに。その後、忠兵衛が、武家屋敷へ届ける急ぎの金300両を懐に入れたまま越後屋に立ち寄ると、先客として八右衛門が来ており、遊女たちに忠兵衛との手付金の話をした上で、身請けなどできる立場ではなく、このままではろくなことにならないから店に入れてくれるなと言っている。逆上した忠兵衛は、300両を自分の金と偽って懐の金の封印を切り、梅川を身請けしてしまう。公金の封印を切った者は死罪。忠兵衛と梅川は死を覚悟しつつ新口村へと向かい、忠兵衛の父親と会うが、やがて罪人として捕らえられるのだった。 |
八右衛門が遊女たちに聞かせた話は正論そのもの。忠兵衛のためにも梅川のためにも、これ以上無駄な時間と金を使わせないようにという配慮なのだが、顔に泥を塗られた格好の忠兵衛の憤慨もよくわかる。結果的には、八右衛門も決して望まない悲劇を招いてしまうのは残念だ。
歌舞伎『恋飛脚大和往来』は、この『冥途の飛脚』の改作である『けいせい恋飛脚』を歌舞伎化したもの。この改作と原作との大きな違いが、八右衛門の設定だ。
こちらの八右衛門は、亀屋の先代の甥である利兵衛と共謀し、忠兵衛を陥れる。そんなわけで、封印切に至る場面でも、実に憎らしく忠兵衛を煽っていく。このため八右衛門の演技も一つの見どころとなり、また、八右衛門が悪役を担う分、観客の忠兵衛への同情は増すため、わかりやすいとも言えるだろう。とはいえ、口は悪いが友達思いの男から、友を陥れる悪役へと“キャラ変”させられた八右衛門は、いささか気の毒に思えなくもない。
人形浄瑠璃の『冥途の飛脚』は、2月文楽公演で見ることができる。人形は、忠兵衛に桐竹勘十郎、梅川に吉田勘彌、八右衛門に吉田文司。人形たちが息づき、太夫の千歳太夫が豊澤富助の三味線で語る、迫真の「封印切」に注目だ。

『冥途の飛脚』2019年1月 国立文楽劇場 人形左から、忠兵衛、梅川、八右衛門
ミュージカル『ウィキッド』エルファバ
悪役として知られるキャラクターに新たな光を当てた作品もある。ここでご紹介したいのは、ミュージカル『ウィキッド』。作家グレゴリー・マグワイアが『オズの魔法使い』の前日譚として書いた小説の舞台化だ。
まず、オズの魔法使いの簡単な物語は、以下の通り。
| 竜巻に飛ばされてカンザスからオズの国にやってきたドロシーは南の良い魔女グリンダの助言により、家に戻るため、知恵がほしいかかし、勇気がほしいライオン、心がほしいブリキのきこりとともにオズの魔法使いのもとに向かう。西の悪い魔女を倒せば願いをかなえてやるという魔法使いの言葉を信じ、西の悪い魔女と戦う一行。ドロシーが水をかけると西の悪い魔女は溶けてしまい、目的は達成されるが、魔法使いには魔法を操る力はなく、ドロシーたちを助けることはできなかった。しかし、グリンダの助言により、彼らは願いを叶え、ドロシーも無事に家に帰るのだった。 |
この物語は『ウィズ』のタイトルでミュージカル化され、映画版も誕生。ダイアナ・ロスがドロシーを演じ、かかし役にはマイケル・ジャクソンが扮している。
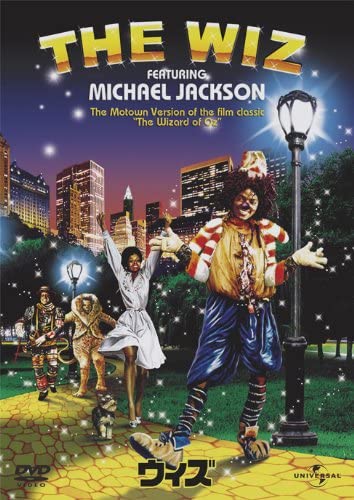
さて、『ウィキッド』では、『オズの魔法使い』でドロシーたちに立ちはだかる“西の悪い魔女”が、どのようにして悪役になったかが描かれている。
| 緑色の肌で生まれたことで周囲から疎まれて育ったエルファバは、魔法を学ぶ全寮制の大学で、明るく人気者のグリンダとルームメイトになる。強い魔法の力を持つエルファバはある日、オズの魔法使いから招待され、グリンダを伴って会いに行くが、魔法使いが、実際には魔法の力を持たない人間であり、学校長マダム・モリブルと結託してエルファバの力を悪用しようとしていた。そのことに気づいたエルファバは正義のために戦う決意をするが、マダム・モリブルらに先手を打たれ、悪い魔女に仕立て上げられてしまう。グリンダはそんなエルファバの逃亡を助けつつ、自らは国に残る。そして同級生のフィエロとの婚約を発表するが、フィエロにとってそれは寝耳に水であり、彼の心はエルファバにあった。悪い魔女として追われ続けるエルファバをみつけ、愛し合っていることを確認するフィエロ。しかしエルファバを取り巻く状況は悪化し続け、遂に彼女は、自分は悪役を引き受けて自らの理想をグリンダに託すことにし、ドロシーに水をかけられて姿を消す。悪い魔女の終焉を宣言するグリンダ。その姿を、実は生きているエルファバとフィエロが遠くから見守るのだった。 |
全編、魅力溢れる楽曲(作詞&作曲:スティーブン・シュワルツ)に彩られているが、中でも、エルファバが自らを解き放ち、悪との戦いを心に決めて高らかに歌う「Defying Gravity」は、ほうきに乗って高く舞い上がる演出と相まって、屈指の名場面となっている。正反対のグリンダとエルファバが反目し合いながらも友情を育み、それでいて、互いに相手にはあって自分にはないもののために苦しむさまは、切なくリアル。差別や偏見などの社会問題を独自の視点で描いた作品でもある。ライオン、カカシ、ブリキのきこりが原作とは別の形で登場するのも興味深い。
世界各地で上演され、日本では劇団四季のレパートリーとなっている本作。映画版も制作されており、当初は2019年に公開される予定だったが、一旦延期され、さらに昨年10月、監督を務める予定だったスティーヴン・ダルドリーが、コロナ禍での変更などを理由に降板。完成・公開が待たれる。
被差別者という“悪”〜能『土蜘蛛』土蜘蛛、演劇『ヴェニスの商人』シャイロック
肌の色から差別され、不本意な経緯から悪人となった『ウィキッド』のエルファバだったが、芸術作品において、弱者、敗者、被差別者が悪者として描かれた例は少なくない。武将・源頼光が化物「土蜘蛛」を退治するという、『平家物語』などの逸話から生まれた能『土蜘蛛(土蜘)』にも、その要素がある。
| 源頼光が病気で臥せっているところへ、深夜遅く、謎の僧(前シテ)がやってくる。自らが土蜘蛛であることをほのめかした僧は頼光に糸を放って苦しめるが、頼光が枕元の刀を抜いて切りつけると姿を消す。駆けつけた独武者(ワキ)らが土蜘蛛の血のあとを辿り、葛城山の古い塚をみつける。塚を崩すと土蜘蛛の精(後シテ)が現れ、幾筋もの糸を放って戦うが、やがて退治される。 |
土蜘蛛を演じるシテ(主役)が糸を投げつける華やかな演出で知られ、歌舞伎舞踊など様々なバージョンが生まれている名作だ。
だが、「土蜘蛛」とはもともと、「熊襲」「蝦夷」などと同じく、大和朝廷に従わなかった土着民の蔑称だった。穴居生活をしていたことが呼び名の由来のようだ。能『土蜘蛛』の土蜘蛛は退治される前、「自分は葛城山に長年住んだ土蜘蛛の精魂であり、大君の世をかき乱そうとして頼光に近づいた」と言うのだが、『日本書紀』には、「葛城」の地名はそこに住んでいた土蜘蛛を皇軍が葛で編んだ網を使って殺したことから生まれたという記述がある。つまり、鬼と同様、朝廷に刃向かって滅ぼされた先住民が化物として表されたのである。
ちなみに、源頼光の子孫である源頼政は帝を悩ませた鵺(ぬえ)という怪物を退治しているが、これを題材にした能『鵺』では、鵺の亡霊が僧の前に現れて、滅ぼされた際のことを切々と語り、自らを弔ってくれと訴える。
能『土蜘蛛』は3月、「第104回 粟谷能の会」で上演される。シテは粟谷明生。初めて演じた(能では「披(ひら)く」と言う)のは16歳で、ワキは同い年の森常好が演じたそうだが、今回もやはり森がワキを勤める。粟谷は2010年に後シテを演じたあと、「落ち着いた威勢の中に土蜘蛛族の精魂の復讐心を演じることが大事で、千筋の糸を吐きかけ独武者たちを苦しめながらも、勢いが次第に弱って最後は退治されてしまう、その無念さをも演じなければ土蜘蛛を勤めたとは言えない」「退治される鬼たちの悲劇は、我々芸能者にも通じるものがある」と記していたが、65歳という能楽師としての充実の時を迎えて臨む今回、どのような土蜘蛛の姿を見せてくれるだろうか?
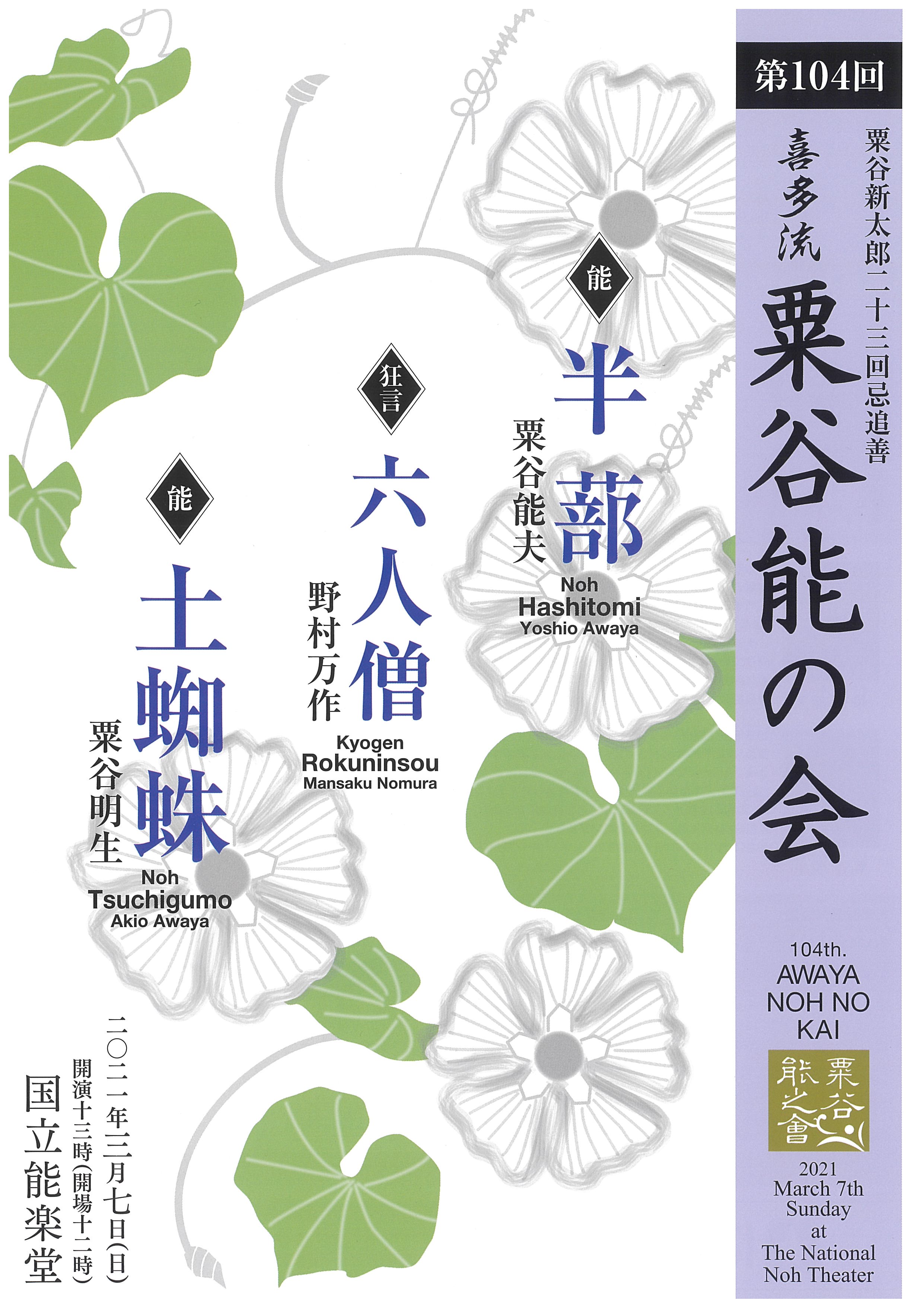

第104回 粟谷能の会で使用予定の能面「顰(しかみ)」粟谷家蔵 写真提供:粟谷明生
さて、国も時代も違うが、シェイクスピアが書いた『ヴェニスの商人』において狡猾で冷酷な高利貸しとして描かれるユダヤ人シェイロックにも、やはり差別され迫害される者の怒りや悲しみを感じずにはいられない。
| 水の都ヴェニス。親の財産を使い果たしてしまっている青年貴族バッサーニオは、ベルモンドの美しい遺産相続人ポーシャに結婚を申し込むため、親友のアントーニオに金の都合を頼むが、交易商人であるアントーニオの財産は今、海の上。そこで彼はバッサーニオに、船が戻るまでの間、自らが保証人となってシャイロックから金を借りさせる。アントーニオのことを嫌うシャイロックは、アントーニオが保証人となり期限までに金の返済がなければ保証人の肉1ポンドを切り取るという条件をつけるが、アントーニオはこれを飲む。やがて、ポーシャの心を射止めるバサーニオだったが、アントーニオの船が帰って来ず、難破したとの知らせが入り、借金返済は不可能に。
裁判が開かれるとシャイロックは、今やポーシャの夫となり財産を得たバッサーニオが大金を払うと言っても聞かず、あくまでアントーニオの肉を切り取ることを主張する。そこへ法学博士になりすましたポーシャが登場し、切り取る肉は1ポンドで、それ以上でも以下でもいけないし、血は1滴も流してはならないと告げると、シャイロックは敗北。さらにアントーニオの命を狙ったかどで財産を没収され、死刑を言い渡されるが、減刑され、財産の半分は娘ジェシカ(バッサーニオとアントーニオの友人ロレンゾと駆け落ちしキリスト教徒になっている)に与えられ、シャイロック自身もキリスト教に改宗させられる。
裁判後、アントーニオの命を助けた法学博士がポーシャであることが夫たちに対して明らかにされ、アントーニオの船も無事帰港し、物語は大団円のうちに幕となる。 |
確かに残忍でやり口があくどいシャイロックだが、彼がユダヤ人として、金貸しとして、価値観の違うアントーニオを嫌うのに相応の理由があることは、劇の中でシャイロック自身が述べる通り。落ち度があるのは、そんなシャイロックを蔑みながら軽率な契約を交わしたアントーニオやバッサーニオのほうなのだ。シャイロックの殺人を阻止するまではいいとしても、彼にとって最も大切な財産と宗教を奪っておきながら善行を施した気になっているキリスト教徒達の残酷さ、無神経さよ。
その意味でも、劇中、本当にアントーニオの肉を取るのかと聞かれたシャイロックが、自分がいかにユダヤ人として差別されてきたかを語り、「ユダヤ人には目がないか? 手がないか? 内臓が、四肢が、五感が、感情が、激情がないのか?」と怒りも顕に訴える台詞は象徴的。シャイロックは、勧善懲悪的な悪役には決して収まらず、終幕後もこちらをじっと見続けているような存在だ。
表象され積み重ねられた悪を、どうとらえるか
思い返せば前編の最後に触れた『藪原検校』の杉の市も『メディア』のメディアも、社会の弱者だった。
杉の市が悪事を重ねたのは、社会の底辺から這い上がるため。貧しい盲目の男である彼にとって、正攻法での出世など考えられなかっただろう。だからこそ、自らの弱点をも用いながら、のし上がっていった。
一方、メディアの残虐な行為は、古代ギリシャにおいて辺境であるコルキスから来た“外国人の女”だという二重のマイノリティと無関係ではない。他民族を、英語のbarbarian(野蛮人)の語源である「バルバロス(バルバロイ)」と呼んで差別した古代ギリシャ人。実際、イアソンはメディアを罵倒する際、コルキスを「野蛮な国」と呼ぶ。故国を裏切って尽くし、子まで儲けた相手が、自分を離縁して、より条件の良い相手と一緒になるという、『東海道四谷怪談』のお岩にも通じる状況下、岩のように自身や子供を殺されなかったメディアが弱者から強者に転じる唯一の手段こそ、子供たちやイアソンの新たな結婚相手を殺すことだったのだ。それにしても一般的に、男性の「悪人」とは異なり、魅力的な「悪女」に男女の恋愛や性愛が絡むケースの、なんと多いことか。そこには、社会の中での不平等や、作者の多くが男性である事実なども関係していると言えるだろう。
悪事・悪人の背後には、歴史や地域を含め様々な因果関係が見え隠れする。舞台芸術における悪は多くの場合、愉しく美しく濃密にドラマを盛り立ててくれるものだが、それらをどうとらえ、表現/享受していくかは、舞台芸術に関わる全ての人々に常に問われていることなのではないだろうか。
★次回は2021年2月1日(月)更新予定です