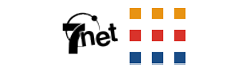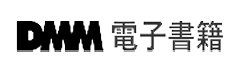“Contemporary Dance Lecture for Ballet Fans”
群舞とユニゾン〜強すぎて危険な魅力、その光と影〜
前回は「舞台におけるセンター問題』を取り上げたが、今月はそれと対になる問題、すなわち群舞、そしてユニゾンについて語っていこう。
「同じ動きをする=ユニゾン」には強烈な魅力があり、人間は本能的にキモチイイと思ってしまう。
それはときにダンスが独裁政権やカルト宗教に利用される「黒い歴史」をも生み、以後のダンス作品にも影を落としてきた。
今回は群舞の意味と意義、そしてそもそも、なぜ我々はユニゾンをキモチイイと思ってしまうのか? その秘密にも迫っていきたい。
バレエを支える群舞の魅力
●『セレナーデ』は空気に生命を与える
群舞の美しさは、バレエの醍醐味のひとつである。一糸乱れぬ精度が要求され、ダンサー達の背の高さまで完璧にそろえていたりする。
名作といわれる作品は、主役のみならず群舞も珠玉の美しさを見せてくれるものだ。
数ある美しい群舞の中でも、幕が上がると同時にグッと胸を掴まれるのが、ジョージ・バランシンの『セレナーデ』である。
切なさとドラマが同時にこみ上げてくるようなチャイコフスキーの「弦楽セレナーデ ハ長調」に乗せて、たたずんでいる17名のバレエダンサーが、ふっと右手を挙げる。腕の動きだけで舞台上の空気がひとつの塊のように息づき、景を創り出してしまう名シーンだ。
これはバランシンが渡米後初めて振付けた作品といわれ、冒頭のシーンは「クラスの最中に窓から入ってきた西日がまぶしくて皆が一斉に手を挙げた仕草から発想した」という説もある。
その真偽はともかく、「何かを動かすのが振付」だとするのなら、西日がまぶしくて光を遮るために手を挙げたダンサー達は「太陽によって振付けられた」といえる。しかもユニゾンのダンスをだ。
●『ラ・バヤデール』の『影の王国』は空間を制する
「空間を大きく使う」のは群舞の魅力のひとつだが、マリウス・プティパの『ラ・バヤデール』はその真骨頂を味わえる。
恋人を亡くした勇士ソロルが、悲しみからアヘンを吸い「影の王国」へ没入していくシーン。寺院の踊り子であるバヤデール達の幻影が、短い振りを繰り返しながらゆっくりと斜面を降りてくる。
3人、5人……舞台の端に達しても止まることなく折り返してなおも陸続として登場する。
10人、15人……反対側の端に達すると、また折り返した!
いつ終わるんだろう、と思っている間にも続々と出てきて止まらない。
やがて全員が舞台上に降りてきて、4人×8列=32人の精霊が広い舞台一面を満たすのである。
ボリショイ・バレエ「ラ・バヤデール」ザハーロワ&ラントラートフ(DVD)発売元:新書館
初めて見たときはその斬新さに感嘆した。
群舞というと、まず全員がポジションに着いてから一斉に踊り出すことが多い。
しかし「影の王国」は「ポジションに着くまで」を作品化しているのである。
しかもその過程にゆっくりじっくりけっこうな時間をかける。ひとつの振付の繰り返しだけで、変化はない。ともすれば退屈になってしまうシーンを、尋常ではない振付とダンサーの力で見せきるのである。
この「過程を見せる」には、もうひとつの効果がある。
もしも降りてくる過程がなく、はじめから舞台全体に全員がびっしり並んでいるのを見せられても、「たくさんいるな」で終わるだろう。
しかし傾斜面を進むたびに舞台にダンサーが満ち、なにもなかった空間が徐々に狭まっていく過程が、最終的な舞台の広さをあらためて実感させてくれるのである。
『セレナーデ』は板付きではじめからポジションについていて、とくに冒頭はその場から動かずに踊る。
「影の王国」は斜面の移動から平場へと拡散し、舞台空間全体を満たす。
このふたつは、それぞれ群舞の違う魅力を志向している。
それはおいおい見ていくことにしよう。
●『ジゼル』の群舞は意思を拡張する
もうひとつ、ぜひ触れておきたいのが『ジゼル』の第2幕である。精霊の女王であるミルタの指揮の下、ジゼルを死に追いやったアルブレヒトを死の踊りに誘うウィリ達。整然とした動きのなかに、ミルタの意思を受けウィリ達によって増幅された殺意が舞台いっぱいに拡張し、アルブレヒトひとりに差し向けられる瞬間は、ぞっとさせられる。
この「数の威力」も群舞の魅力のひとつ。『ジゼル』では殺意の具現化だが、ダンサー達は表情を使うわけでもなく、整然とした仕草だ。しかしそれが群舞になることで「意思」を持つのである。
この群舞のポイントは「数の威力」による「意思の拡張」である。
これは主人公の激烈な感情を表現するときに効果的な使い方だ。
―― この続きは電子書籍でお楽しみいただけます ――
※この記事ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。