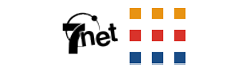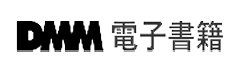“Contemporary Dance Lecture for Ballet Fans”
ダンスと照明 〜光の向こうに、深淵がある〜
はじめにお詫びを言わなければならない。
前回、今回のテーマは『照明と映像』とお伝えしていたが、やはりというか、「照明」について書いているだけで規定枚数を大幅に超えてしまった……
ので、今回は照明について、そして次回映像について述べていきたい。
申し訳ない!
照明で、ダンスはこんなに変わる
……さて舞台芸術は「見る芸術」である。対象を照らした光が観客の目に入って像を結ぶ。
同じ物を見ても、照明によって全く印象が違ってしまう。
だが日本のダンス作品は、照明をただ「照らす」以上の重要性を理解していない作品が多いのである。
ちょっと想像してみよう。
光に満ちた舞台で溌剌とした振付で踊るダンスがあるとする。見ていると楽しげで心が弾む。
しかし同じダンスでも、真っ暗な中で照らされた小さな円の中で踊っているとなると、必死に明るく見せようとしている感が増してこないだろうか。
あるいは右側だけ照明を当て、顔や身体の陰影が深く刻まれたまま踊っていると、何かの闇を抱えているように見えるかもしれない。
炎のように真っ赤な照明の中で踊っていたら、あるいは氷のように青い照明の中で楽しげに踊っていたら。
収容所のような蛍光灯の下だったらどうだろう?
あるいは床に置かれた小さなランプの前で楽しげに踊っていたら……
受ける印象は全く違ってくるだろう。
このように照明はダンスそのものの意味合いまでも変えてしまう恐るべき力を持っているのである。
どれだけ素晴らしい動きを作っていても、照明がいい加減では台無しになってしまうかもしれない。
繊細な和食にジャムを塗って出すようなことをしてはいかん。
正しい照明の力を知っていると、ダンスを作るのも見るのも俄然違ってくる。
今回はそこを見ていこう。
●月の光で踊る
バレエの照明、とくに『白鳥の湖』『ジゼル』といったロマンティック・バレエでは、森の中、月光を思わせる青い光の印象が強くないだろうか。
日本のバレエ照明に多大な功績を残した梶孝三が作る月光の青は有名だった。
青といっても冷凍庫のような冷たいだけの光では駄目で、冴え冴えとしていながら森の奥の湿度をも感じさせる青でなくてはならないのだ。「青い光は、昔の限られた照明設備で白いバレエを美しく見せるためだった」という説もあるが、いずれにしても作品世界と深く結びついた舞台照明だといえる。
もっとも現在は海外のバレエ団や、日本でもバレエやダンスを数多く手がける足立恒などの照明は、従来の青だけでなく、より自由な照明デザインも出てくるようになった。
100点と思われていた舞台照明も、常に進化し続けているのである。
●モーリス・ベジャール『ボレロ』の三位一体
ベジャールの不朽の名作『ボレロ』は、ダンスと音、そして照明までもが三位一体となった作品である。
ラヴェルが作曲した『ボレロ』は、同じ旋律を繰り返しながら、次第に演奏する楽器の数が増えていく。
冒頭はスネアドラムが音を刻む中、フルートから始まった旋律が次第に成長していき、最後には大オーケストラとなって鳴り響く。
振付も同じ構造で、最初は大きな赤い盆の上で踊る「メロディ」のソロから、廻りを取り囲む「リズム」達の群舞へと展開していって、最後で一体となるのだ。
照明もまた(バージョンはいくつかあるが)同じように展開する。最初は「メロディ」がゆっくりと上げていく右手だけを射貫くように小さな光が当たる。頂点まで上がると、次に光は左手を捉えて同様に追いかけていく。
大劇場であれば照明から舞台上までは何十メートルも離れている。シーリングスポットライト(客席の上部や後方から狙うライト)で、小さな人間の手のひらにドンピシャで照明を当てなければならない。今はほとんどがコンピュータ制御だが、昔は手動で移動する手の軌跡を追っていったのだろう……だが昔は小さな劇場であっても、パッと振り上げた右手に一発で光を当てる技を持った職人はゴロゴロいたという(逆に態度が悪いダンサーはずっと顔を映さない等のイジワルをされたとか)。
やがて光は手のひらから顔、全身へと続き、メロディが乗っている中央の赤いテーブル全体を映し出す。
さらに曲が進むと、少し離れた場所にぐるりと取り囲むよう男たちが座っている全体像が、順を追って照らし出されていく。
照明の範囲は徐々に広がっていき、そのたびに多くのダンサー達が踊りに加わり、最後にクライマックスを迎える。
『ボレロ』は、曲と振付の構造を、照明でも展開しているわけである。
●全ては電気の時代から
とはいえ、考えてみれば現在のような綿密に設計した照明デザインは、電気が普通に使えるようになった、ここ百年ちょっとのことにすぎない。
人類の歴史のなかでは、長い間、日光こそが最大の照明器具であった。ヨーロッパの教会でステンドグラスが発達し、白い壁が多いのも効率よく光を乱反射させて光を建物内に行き渡らせる工夫である。日本の障子や坪庭なども同様だ。
ヨーロッパでも特に裕福な人々はシャンデリアに大量の蝋燭を使ったが、洋の東西を問わず照明用の燃料は高価だった。
歌舞伎は河原乞食といわれた時代を経て劇場を組むようになっても屋根を葺くことは禁じられていた。屋根の許可が下りたのは享保三年(1718年)からと言われている。朝から公演していたのも、天窓の開け閉めによって照明を調節していたからだ。
能などは登場人物のほとんどがこの世ならざる者なので、薪能のようにゆらめく光のほうが幽玄度が増したりもする。
今でも舞台上で本火を使うのは消防法によって厳しく規制されているが、火しか照明器具がなかった時代には、しばしば不幸な事故も起きた。
有名なのは1863年、バレリーナのエンマ・リヴリーが、ドレスリハーサル中に照明のガス灯の火が衣裳に燃えうつって焼死した事件だろう。
リヴリーはロマンティック・バレエの代名詞だったマリー・タリオーニの愛弟子で将来を嘱望されており、21歳という若さだったのだ。
ちなみにガス灯の発明は1792年。1872年には日本(横浜)に上陸している。1891年に発明された白熱ガス灯は人間が初めて手にした太陽光に近い「白い光」だったが、まもなく電気照明に取って代わられた。
19世紀から20世紀にかけて、電気が広く大量に安定的に使えるようになったことで、舞台照明は大きな変革期を迎えることになるのである。
―― この続きは電子書籍でお楽しみいただけます ――
※この記事ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。