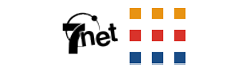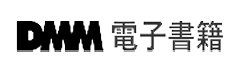“Contemporary Dance Lecture for Ballet Fans”
ダンスと衣裳〜すごく近くて、ものすごく深い〜
今回はダンスと衣裳について語っていこう。
まったくの偶然なのだが、現在発売中の「ダンスマガジン」2020年9月号でも特集が「バレエ衣裳の世界」なので、ぜひとも合わせてご覧いただきたい。
さて衣裳は舞台芸術にとって付加的な存在だと思われるかもしれないが、衣裳がダンスに与える意味と影響は実に大きなものだ。
それはバレエファンのほうが深く実感していることかもしれない。
なぜならトウシューズとチュチュの発明が、今日のバレエという芸術のスタイルを決定づけたといっても過言ではないからである。
バレエの衣裳は、それだけで展覧会が開かれるほどに人気がある。
公演のたびにオペラグラスで衣裳のデザインを隅々まで観賞されるファンも多いだろう。
同じ演目・同じ役柄であっても、時代によって、あるいは役柄の解釈によって意匠が様々に変わってくるので、見比べるのも楽しい。
歴史や作品が変わったり、振付を生みだしたり、衣裳には様々な力がある。
衣裳を中心に見てみると作品がまた違った顔を見せることもある。
「物語」「役割」が希薄なコンテンポラリー・ダンスの時代、衣裳の意義は変わってくるのか。
そして全裸は衣裳か?……などなど。今回は、身近なようで底抜けに深い、衣裳について掘り下げていきたい。
衣裳がダンスの歴史を変える
●衣裳によるバレエの革命『ラ・シルフィード』
フィリッポ・タリオーニが娘マリーに振付けた『ラ・シルフィード』(1832年)は、ロマンティック・チュチュとトウシューズによる様々な技法を見せた。儚さ・浮遊感・妖精・異界といったロマン主義との完璧な合致は、ロマンティック・バレエの幕開けを告げたと言われる。
マリーが演じた風の妖精シルフィードは、結婚を控えたスコットランドの農夫ジェームズを誘惑する。現代よりも長めの釣鐘型のチュチュが揺れるたびに風を感じさせ、ジェームズと戯れながらも、スルリとその腕から抜け出てしまう軽やかな浮遊感は、新しい感覚で観客を魅了したのである。
この『ラ・シルフィード』の凄まじい成功から、チュチュとトウシューズはバレエの代名詞として定着していった。
そしてルイ14世の時代から男性が中心だったバレエは、これ以降、女性ダンサー中心の芸術へと転回していくことになったのだった。
時代が下って1900年代初頭にイザドラ・ダンカンがバレエに対抗する形で「新しい(モダン)ダンス」を提唱したときに、攻撃の対象としたのもやはりチュチュとトウシューズだったのである。
彼女はチュチュではなくギリシャ・ローマ時代の彫刻のようにゆるやかな衣裳をまとい、トウシューズを脱ぎすてて踊る彼女の姿は「裸足のイザドラ」として、人々の記憶に永く刻まれることになったのだった。

イザドラ・ダンカン Everett Collection / Shutterstock.com
●マシュー・ボーンの白鳥は猛禽化する
これ以降、バレエの古典に挑戦する者は、まずチュチュとトウシューズというバレエアイコンと戦わなくてはならなくなった。
その強固さには歯が立たず、ほとんどの作品が消えていったが、みごと一矢報いたのがマシュー・ボーンの代表作『白鳥の湖』(1995年)である。
女性美の極致と思われていた白鳥を、なんとすべて男性が踊ったのだ。
しかもいまだに世界中でヒットし続ける、驚異的な作品となった。
「男が『白鳥の湖』を踊る」というアイデアじたいは特に目新しいものではない。トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団などは、長く人気を博している。
しかしやはりパロディ以上のものには、なかなかならない。
ボーン版『白鳥の湖』が、お笑いでなく正統な読み替えの芸術作品として成立させるうえで、衣裳デザインのレズ・ブラザーストンの功績はきわめて重要である。
なにより革新的だったのは、男が踊る白鳥(ザ・スワン)を、まるで猛禽類のような激しさと野性味に溢れた姿として描いたことだ。
ブラザーストンがデザインした衣裳は、上半身は裸で下半身は白い羽根で覆われている。ただし腿の部分がガッツリ大きく膨らんで、細く伸びた脛がむき出してキュッと締まっている。
これは白鳥ではない。鷲や鷹といった、獲物を捕まえる鋭い鉤爪を持った猛禽類の脚である。
またバレエでは、伸ばした腕で白く長い白鳥の首を表現したりする。
ボーン版ではかわりに額へ黒い逆三角が描かれており、遠目で見ると猛禽類の鋭いクチバシに見えるようになっている。どう見ても黄色く平たい白鳥のそれではないのだ。
ポスターによく使われている「男性が正面を向いて中腰になってポーズを取っている写真」をみると、その腕の形は、獲物を見つけた猛禽類が一直線に滑空するときの翼の畳み方になっている。
「ザ・スワン」は、ボーン作品の定番である「平穏をかき乱す粗暴で魅力的な闖入者」が、気弱な王子とその周辺を、男も女もいろんな意味で食い散らかしていく(そしてラストは屍肉に集まるハゲタカのような衝撃のシーンがある)。まさに猛禽だ。
並の衣裳デザイナーならば「ザ・スワン」の衣裳を「黒一色のダークスーツでちょっと黒い羽根がついている」ようなデザインにするだろう。いわば抽象化だ。無難だし、じっさいそういう舞台を何度か見たことがある。具象的な白鳥に寄せていっても、せいぜいドナルドダックみたいになってしまうだろう。
しかしブラザーストンは抽象と具象の両方をあきらめなかった。
新しい想像力の地平で両者を一致させてみせたのである。
演出振付の革新的なコンセプトが、衣裳によって具体的なイメージに変換され、強烈に観客の目に焼き付けられる。
これは稀に見る成功例といえるだろう。
―― この続きは電子書籍でお楽しみいただけます ――
※この記事ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。