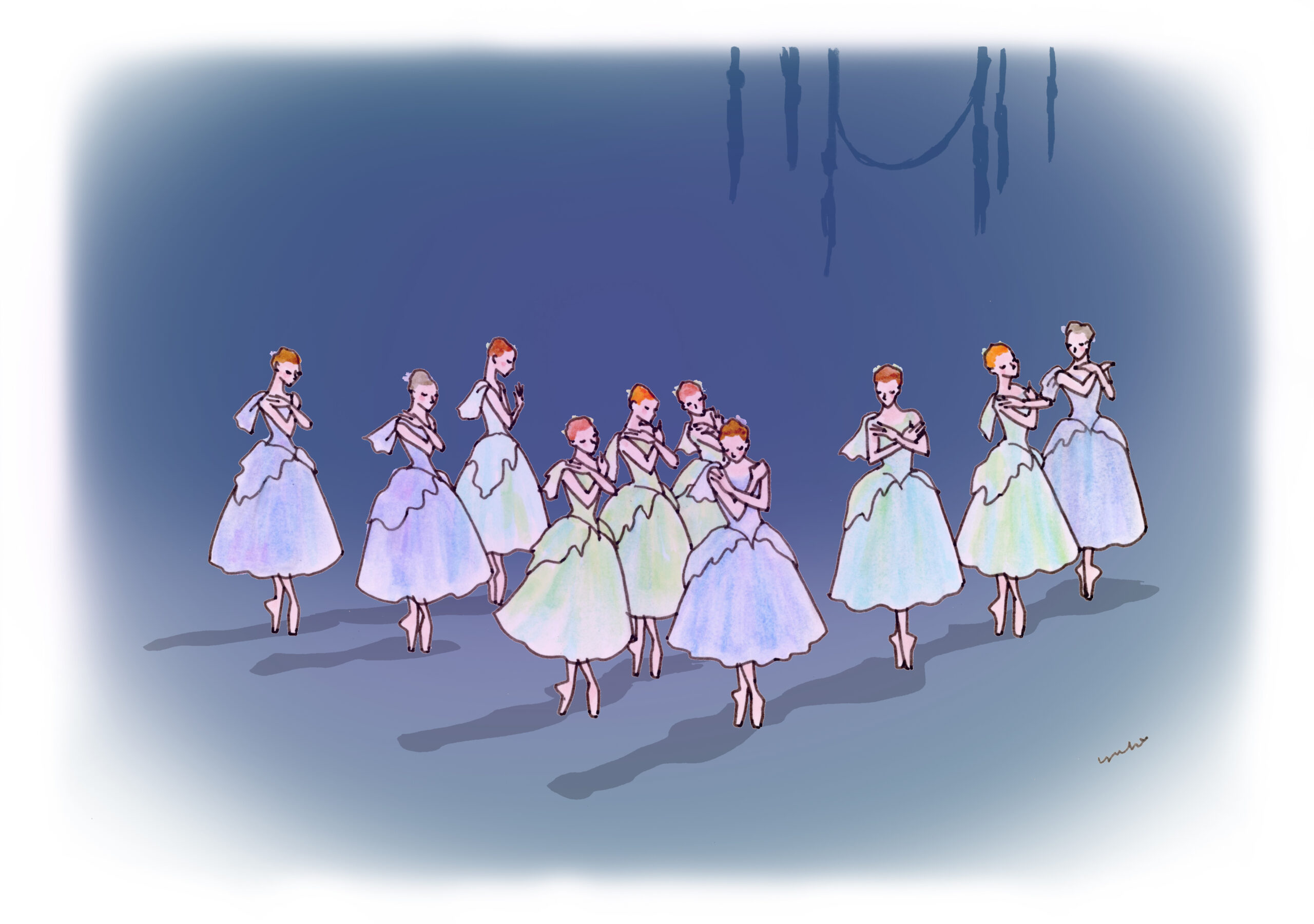パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!
1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。
「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」
そんなあなたのための、マニアックすぎる連載をお届けします。
- 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」
- 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」
- 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…
……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。
ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!
イラスト:丸山裕子
🇫🇷
「バレエ団の年間公演プログラムには、そのバレエ団の方向性や方針、社会の雰囲気や流行などが少なからず影響する」というのは、「バレエチャンネル」読者の、そしてこのマニアックな連載を愛読してくださっているバレエ沼の住民のみなさまには、おなじみの話でしょうか? プログラミングの理由については、シーズンプログラムの発表時に芸術監督が自ら説明することがありますが、公になる情報は限られた範囲のものであり、その裏には、大小様々な事情が潜んでいたりもします(そうした背景を考えるのが、観客にはまた興味深かったりするわけですが)。
では、19世紀のパリ・オペラ座バレエの場合、どのような意図によって上演演目が決定されていたのでしょうか? 今回は、1875年にパレ・ガルニエが開場したときの記念ガラに着目し、このガラにおけるバレエ《泉》の抜粋上演を取り巻いていた、さまざまな状況をご紹介します。
《泉》ってどんな作品?
今回の記事の中心となる《泉》(注1)は、19世紀のパリ・オペラ座で初演されたバレエ作品のひとつです。オペラ座バレエは、この作品を2011年にジャン=ギョーム・バールによる改訂振付で上演しており、クリスチャン・ラクロワによる豪奢な衣裳とともに話題になりました。
作品の初演は1866年11月12日。振付は、《コッペリア》の原振付家であるアルチュール・サン=レオンが、音楽はリュドヴィク・ミンクス(《ドン・キホーテ》や《ラ・バヤデール》の作曲家)と、レオ・ドリーブが担当しています。ドリーブにとって、《泉》は本格的に手がけた初のバレエ音楽で、彼はこのあと、《コッペリア》や《シルヴィア》といった作品に名旋律を残しました。
泉の精のナイラと猟師のジェミル、コーカサスの美しい娘のヌレッダによる三角関係の恋愛模様と、作品全体の異国情緒(ただし19世紀の西ヨーロッパ的視点による)は、19世紀のオペラ座バレエが大好物なテーマそのもの。19世紀後半のフランスで活躍した「ダンスの画家」ことエドガー・ドガも、初演でヌレッダを演じたダンサー、ウジェニー・フィオクルの姿を題材にした絵画作品を残しています。

エドガー・ドガ作「バレエ『泉』でのウジェニー・フィオクル嬢」(1908年)
とはいえこの《泉》、オペラ座の大人気作品だったか、といわれると、ちょっと躊躇してしまうのです。初演の1866年以降、《泉》が全幕で上演されていたのは1876年までで、その10年間の上演回数は69回。当時のオペラ座はほぼ隔日で何らかの公演を行っており、大ヒット作はロングランが普通でしたから、この回数は決して多いとは言えません。しかもこの10年の間には、《泉》の上演自体がいったん途絶えていたのです。では、なぜ《泉》が開場記念ガラという重要な機会の演目に選ばれたのでしょうか?
(注1)バレエ《泉》あらすじ:泉の精ナイラは、ジプシーが水に毒を混ぜようとしていたところを猟師のジェミルに救われる。ナイラはジェミルに思いを寄せるものの、恩を返すために彼が恋人のヌレッダと結ばれるように手助けをする。
栄光を演出するプログラム、と思いきや…
1875年1月5日のパレ・ガルニエの開場は、当時のフランスにとって国家的なイベントでした。首都のパリは、1870〜71年の普仏戦争や、その後のパリ・コミューン時の激しい市街戦で疲弊しており、国の政体も不安定なまま。そこに、かねてから建設中だった新しいオペラ座がやっと完成し、フランスを代表する第一の劇場の不在が解消されたのです。19世紀のパリにとって、オペラ座は文化的・社会的中心地のひとつだっただけに、これはニュースになる出来事でした。
そのため、開場記念ガラには、当時のフランス大統領のパトリス・ド・マクマオンをはじめ、政府関係者や貴族たちが出席したほか、近隣諸外国の王族、貴族らが招待され、パレ・ガルニエは現在まで続く華々しい歴史を始めることになります。
ではここで、その開場記念ガラのプログラムを見てみましょう。
- オベール作曲のオペラ《ポルティチのもの言えぬ娘》より序曲
- アレヴィ作曲のオペラ《ユダヤの女》より第1幕、第2幕
- ロッシーニ作曲のオペラ《ウィリアム・テル》より序曲
- マイアベーア作曲のオペラ《ユグノー教徒》より第4幕の剣の奉献式の合唱
- バレエ《泉》より第2幕
この日のメインの演目は《ユダヤの女》でした。1835年に初演されたこのオペラは、19世紀のオペラ座を代表する作品の一つ。記念ガラの内容を知らせるポスターでも、一番大きく、目立つようにタイトルが書かれています。そのほかに上演されたどのオペラも、1820年年代後半から1830年代にかけての、超黄金期を享受したオペラ座を彩る人気作品ばかりです。
しかし、オペラ部門に19世紀前半の大ヒット作が居並ぶのであれば、《ラ・シルフィード》や《ジゼル》、《海賊》といった、同時期のメガトン級ヒットバレエ作品からの抜粋があっても、おかしくないはずですが……。この背後には、《泉》を取り巻くオペラ座バレエの、そしてオペラ座の事情がありました。
一時代の終わりへ向かって
まず考慮したいのは、新オペラ座であるパレ・ガルニエが華やかに開場したこの時期、オペラ座バレエの衰退がじわじわ進んでいた、ということです。パレ・ガルニエの建設が始まった1860年代は、19世紀前半にオペラ座の客席を沸かせたロマンティック・バレエが、次々に劇場のレパートリーから無くなっていった時代でした。《ラ・シルフィード》は1860年を、《ジゼル》は1868年の上演を最後に、オペラ座から消えます。この年は他に《海賊》がレパートリーから落ち、《泉》の上演も止まりました。
さらに、この時期は作品だけでなくバレエの上演回数自体も減少しており、1868年にオペラ座で公演が行われた全180日のうち、プログラム中にバレエ作品の上演が含まれていたのは、たったの27日。翌1869年にはさらに悲惨で、183日のうち6日しか、バレエ作品の上演がなかったのです(ただし、19世紀のオペラ座で上演されたオペラ作品には、ほぼ100%の確率でバレエのシーンがあるため、バレエが踊られなくなっていたわけではありません)。
じつは、1860年代以前に初演されそれなりのヒットを記録したバレエ作品の中で、不遇の時期へ向かう流れをなんとか乗り越えようとした作品こそが、《泉》だったのです。オペラ座では1870年に《コッペリア》の初演が行われ、大成功を収めますが、その直後に普仏戦争が勃発し、オペラ座も閉鎖。再開後もバレエ上演の数は決して多くなかったものの、《泉》は1872年にオペラ座の舞台に戻り、《コッペリア》とともに継続的に上演されていきます。《ジゼル》や《海賊》が時代の変わり目に消えたことをふまえると、1875年のオペラ座にとって、《泉》は「以前の華やかなオペラ座を体現できる作品の一つで、かつ、今の観客にとって古すぎないもの」だったと言えるでしょう。
でも、《コッペリア》が大ヒットしたのなら、ガラでの上演はこの作品でも良かったのでは? ハッピーエンドで終わる作品だし、誰も死なないし、第3幕のディヴェルティスマンは踊りの連続だし……新劇場開場の場ですから、幸せムードがある作品はぴったりですが、おそらくオペラ座側にとって重要だったのは、《泉》の物語のほうだったのではないでしょうか。
アメリカの文化理論研究者、フェリシア・マッカランは、1875年当時のフランスが北アフリカへの植民地政策を進めていたことをふまえ、女性化された自然(泉の精ナイラ)の犠牲によって幕切れとなるこのバレエの物語に、「植民地での天然資源と人間の管理」という、政策上の重要ポイントが見出された可能性があることを指摘しています。「オリエンタル」な雰囲気、泉の精の力を従える人間、異国の粗暴な男性たちと顔を覆った美しい女性たち……さらにマッカランは、これらの要素が、2011年の改訂再演に関しても影響している、と述べています。(注2)
19世紀のオペラ座の場合、劇場のあり方自体が国と深く結びついていたので、社会の雰囲気と作品上演が連動しやすいほうではあります。しかし、それは決してこの時期のオペラ座に限った話ではありません。バレエ上演が社会の中で行われる文化的活動の一つである以上、時には観客の私たちもちょっと立ち止まって、客入りや作品の知名度だけではない要素、つまり「なぜ今この作品なのか」を考えることが必要かもしれませんね。
(注2)2011年の改訂再演に関して、マッカランは、前年(2010年)にフランスでイスラム教徒の女性が公の空間で顔や体を覆う衣装を着用することを事実上禁じる法律が成立したことと、2011年のいわゆる「アラブの春」の動きについて、《泉》との関連を指摘しています。作品冒頭、ヌレッダがベールで顔を隠した状態で登場するという「異国感」、またそのベールをジェミルが同意なしに剥ぎ取って彼女の顔を見る、という行為に見られる女性と男性の力関係などは、同時期にフランスや中東世界で起こっていた出来事と無関係ではない、というのが、彼女の見解のようです。
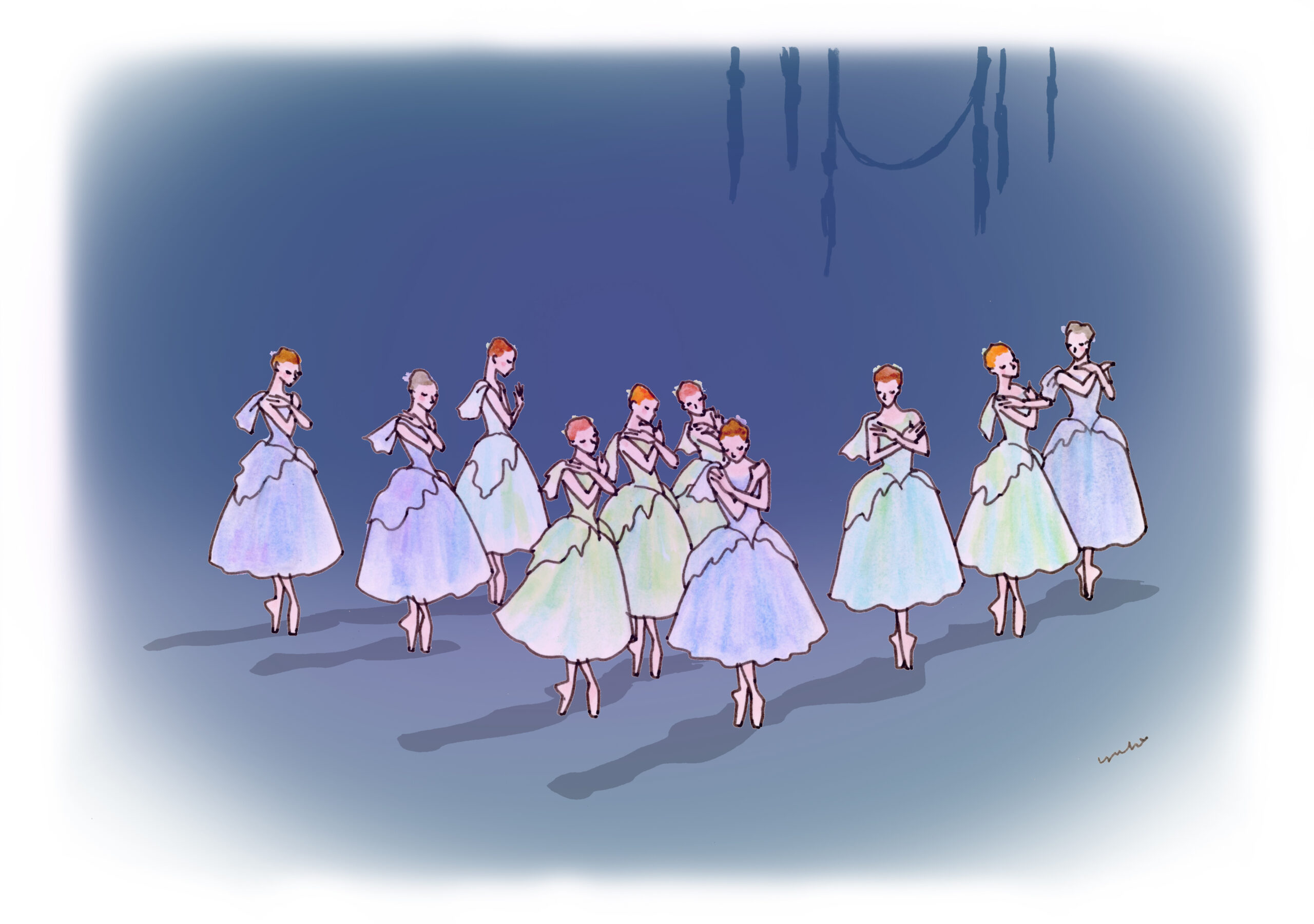
参考資料
Chronopera http://chronopera.free.fr//index.php?menu=accueil&contenu=accueil_questce
Opéra national de Paris, Ballet de l’Opéra La Source Jean-Guillaume Bart. Programme de la saison 2011-2012.
平林正司、2000。『19世紀フランス・バレエの台本 パリ・オペラ座』東京、慶應義塾大学出版会。
McCarren, Felicia. 2020. One Dead at the Paris Opera Ballet: La Source 1866-2014. New York, Oxford University Press.
【NEWS】永井玉藻さんの新著が好評発売中!
「バレエ伴奏者の歴史〜19世紀パリ・オペラ座と現代、舞台裏で働く人々」

バレエにおいて、ダンスと音楽という別々の芸術形態をつなぐために極めて重要な役割を果たしている存在、それがバレエ伴奏者。その職業が成立しはじめた19世紀パリ・オペラ座のバレエ伴奏者たちの活動や役割を明らかにしながら、華やかな舞台の“影の立役者”の歴史をたどります。
●永井玉藻 著
●四六判・並製・224頁
●定価2,420円(本体2,200円+税10%)
●音楽之友社
●詳しい内容はこちら
●Amazonでの予約・購入はこちら