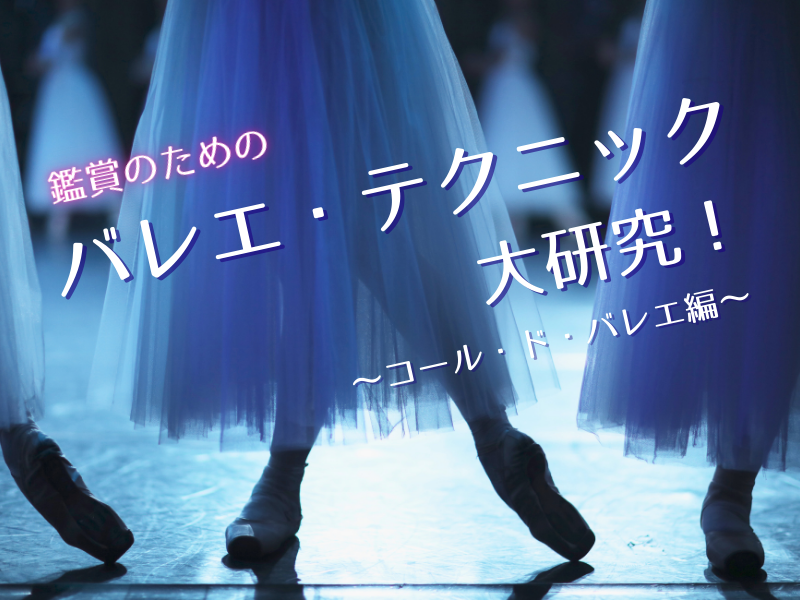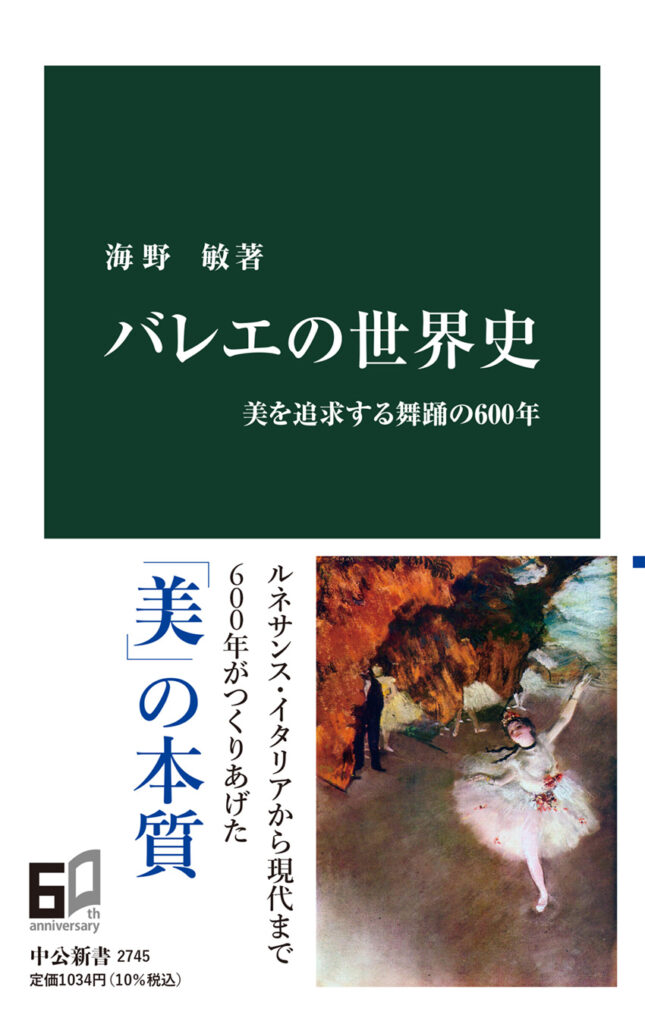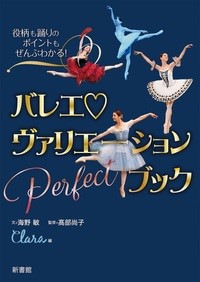文/海野 敏(舞踊評論家)
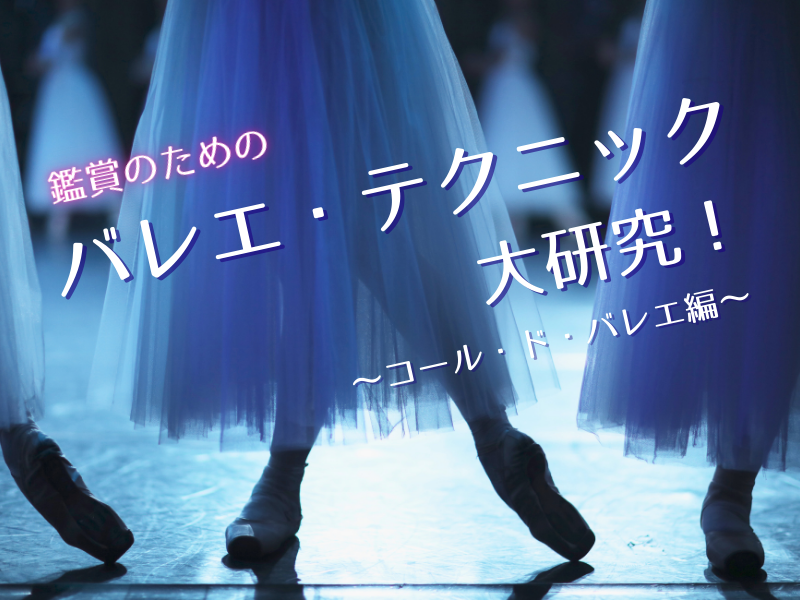
第75回 増減の工夫
■ベジャールの『ボレロ』
この連載はさまざまなバレエ・テクニックを、おもにバレエの古典全幕作品を例として解説しています。そしてバレエの古典全幕作品は、その大半が19世紀に初演され、上演され続けているものです(注1)。
しかし、今回は20世紀に創作されたバレエ作品を例にして、コール・ド・バレエの人数が増えてゆく、または減ってゆく演出の工夫について解説します。取り上げる作品は、いずれも巨匠振付家による傑作ばかりです。
まずモーリス・ベジャール振付『ボレロ』(1961年初演)から。本作は映画『愛と哀しみのボレロ』(1981年公開)で、カリスマダンサー、ジョルジュ・ドンがクライマックスシーンで踊ったため、映画のヒットに伴ってバレエファン以外にも広く知られるようになりました。本連載では第67回「円形に並ぶ(2)」でも取り上げました。
主役の「メロディ」が独り円卓の上で踊り始め、やがて円卓を囲んで椅子に座っていた数十人の群舞「リズム」が数人ずつ立ち上がって踊り始めます。ラヴェルの音楽が盛り上がるにつれて、群舞の人数が「2人→4人→8人→10人→14人→18人」と増え、最後に約40人のリズムがメロディを2重の円陣で取り囲みます。ラヴェルの音楽と共に、振付も「漸進上昇」してゆく構成が鑑賞のポイントです。
- ★動画でチェック!★
- ベジャール・バレエ・ローザンヌ『ボレロ』のダイジェスト映像です。躍動感あふれるステージをお楽しみください。
- ★動画でチェック!★
- 映画『愛と哀しみのボレロ』の予告映像より。1分11秒からジョルジュ・ドンの踊る姿を少し観ることができます。
■マクミランの『マノン』と『ロミオとジュリエット』
ケネス・マクミランの『マノン』(1974年初演)は、第1幕冒頭が魅力的です。幕は、マスネの序曲が終わるよりも前に上がります(注2)。すると暗闇の中央に丸く光があたっていて、一人の男性が特徴的な形の黒い三角帽(トリコーン)をかぶり、黒いマントを広げて座っています。ご覧になったことがあれば、このインパクトのあるビジュアルはご記憶でしょう。
序曲が終わって舞台が明るくなると、まず浮浪者たちが十人ほど集まり、そこに町人が加わり、さらに豪華な馬車が到着して貴族たち、高級娼婦たちが降り立ち、次第に舞台上の人数が増えてゆきます。冒頭の男性はおもむろに立ち上がり、貴族たちに挨拶を始めます。実はこの男性は主人公マノン・レスコーの兄でした。
主人公が登場するのは幕が上がってから約9分後なのですが、それまでの場面も見応えがあります。なぜならコール・ド・バレエが徐々に増えてゆくことで、浮浪者、町人、貴族、娼婦、学生などが広場に集う18世紀のパリ郊外の光景が、とても生々しく、かつ生き生きと描写されているからです。
- ★動画でチェック!★
- 新国立劇場バレエ団『マノン』のリハーサル映像より。16秒から黒いマントを羽織ったレスコーの印象的なシーンを観ることができます。
いっぽう、マクミラン版『ロミオとジュリエット』(1965年初演)第2幕の幕切れは、コール・ド・バレエが徐々に減ってゆく演出で印象的です。ジュリエットの従兄のティボルトは、ロミオの親友マキューシオを刺し殺し、それを見て逆上したロミオに刺し殺されてしまいます。そこへジュリエットの母であるキャピュレット夫人が現れ、ティボルトの死骸にすがって慟哭します。
キャピュレット夫人が現れてから幕が下りるまで約2分。最初は死骸を取り囲んでいた40人ほどの群舞はだんだんとその場を去り、幕が下り時には、ティボルトの死体にすがるキャピュレット夫人、遅れて到着したキャピュレット卿と、ほか2人のみとなります。こぶしを自らに打ちつけて嘆くキャピュレット夫人の悲しみがいっそう引き立つ演出になっています。
- ★動画でチェック!★
- 英国ロイヤル・バレエ『ロミオとジュリエット』の紹介映像です。一瞬ですが、21秒からキャピュレット夫人のシーンを観ることができます。
■プティとライトの『コッペリア』
最後のロマンティック・バレエと言われる『コッペリア』は、ローラン・プティが1975年に、ピーター・ライトが1995年に、それぞれ独自の振付・演出のバージョンを創作しました。いずれも最終幕のエンディングはコール・ド・バレエが舞台上から退出し、コッペリウス博士とコッペリア人形だけが残って幕が下りるのですが、どちらも奇抜なエンディングで見逃せません。
プティがマルセイユ・バレエのために作ったバージョンでは、誰もいなくなった舞台上でコッペリウス博士が人形のコッペリアを抱きしめるのですが、何と人形の手足が外れてばらばらに壊れてしまいます。『コッペリア』はコメディー・バレエですが、この幕切れは笑いを誘うものではなく、老博士の人形愛ゆえに切なく感じられます(注3)。
- ★動画でチェック!★
- バイエルン国立バレエ『コッペリア』の紹介映像より。4分23秒から幕切れのシーンを観ることができます。幸せそうなスワニルダとフランツをよそに、コッペリアを抱きしめる博士の哀愁漂う表情にも注目です。
ライトがバーミンガム・ロイヤル・バレエのために作ったバージョンでは、コッペリウス博士が人形を椅子に乗せて誰もいなくなった舞台に現れるのですが、何と博士の願いが突然叶い、人形に命が宿って動き始めます。そして博士とコッペリアが楽しげに踊る場面で幕が下ります(注4)。
プティ版とライト版では正反対と言えるエンディングです。しかし、どちらもエンディングの直前に群舞が次第に減っていなくなることで、幕切れの演技を際立たせる効果が加えられている点で共通しています。
- ★動画でチェック!★
- スターダンサーズ・バレエ団『コッペリア』の紹介映像です。博士とコッペリアの楽しげな幕切れは6分25秒から。
(注1)次の古典全幕作品は、すべて19世紀に初演されました(括弧内は初演年)。『ラ・シルフィード』(1832)、『ドナウの娘』(1836)、『ジゼル』(1841)、『ナポリ』(1842)、『エスメラルダ』(1844)、『パキータ』(1846)、『海賊』(1856)、『ファラオの娘』(1862)、『ドン・キホーテ』(1869)、『コッペリア』(1870)、『ラ・バヤデール』(1877)、『白鳥の湖』(1877)、『眠れる森の美女』(1890)、『くるみ割り人形』(1892)、『ライモンダ』(1898)。
(注2)マクミラン版『マノン』の音楽はマスネ作曲ですが、マスネのオペラ『マノン』は全く使われていません。マスネ作曲の他の楽曲で構成されており、序曲も他のオペラの楽曲です。
(注3)プティ自身によるコッペリア博士の演技が最高でした。
(注4)もっともライト版『コッペリア』のエンディングは、コッペリア博士の見る幻想だったという解釈もありえるでしょう。
(発行日:2025年10月25日)
次回は…
第76回は、コール・ド・バレエのダンサーたちが舞台を埋め尽くす演出についてご紹介する予定です。発行予定日は2025年11月25日です。
- 【鑑賞のためのバレエ・テクニック大研究!-総目次】
- http://bibliognost.net/umino/ballet_tech_contents.html
\NEWS!/
本連載の著者・海野敏さんによる書籍が発売されました! ルネサンス期イタリアから21世紀まで、バレエという舞台芸術の600年を通覧する内容です。
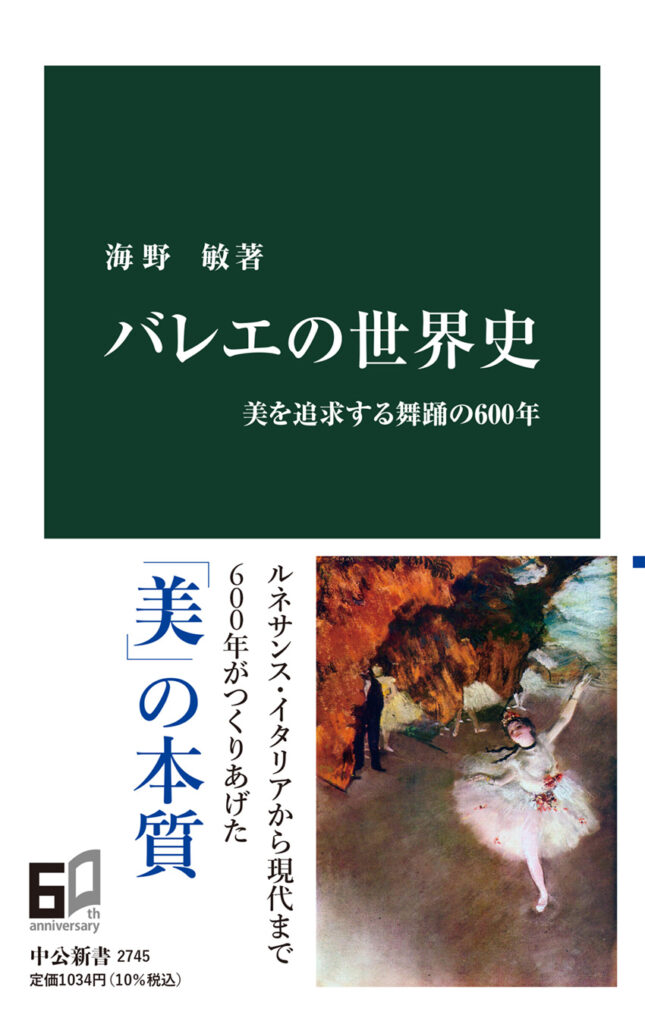
『バレエの世界史:美を追求する舞踊の600年』
海野敏=著
中央公論新社 2023年3月(中公新書2745) 940円(税別)
★詳細はこちら
*
【こちらも好評発売中!】
オーロラ、キトリ、サタネラ、グラン・パ・クラシック、人形の精……等々、コンクールや発表会で人気の 30 のヴァリエーションを収録。それぞれの振付のポイントを解説しています。バレエを習う人にも、鑑賞する人にも役立つ内容です。ぜひチェックを!
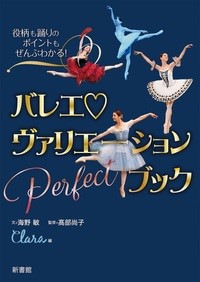
『役柄も踊りのポイントもぜんぶわかる! バレエ♡ヴァリエーションPerfectブック』
海野敏=文 髙部尚子=監修
新書館 2022年3月
★詳細はこちら